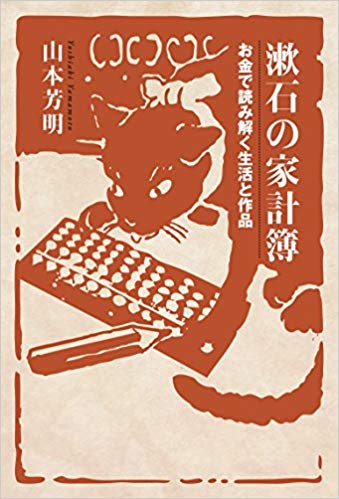「経済人(ホモ・エコノミクス)」としての夏目漱石・・・【情熱の本箱(252)】
『漱石の家計簿――お金で読み解く生活と作品』(山本芳明著、教育評論社。出版元品切れだが、amazonなどで入手可能)は、夏目漱石を経済的視点から考察したユニークな著作である。
私にとって、とりわけ興味深いのは、①漱石は貧乏文士だったのか金持ち文士だったのか、②漱石の稼ぎはどのくらいだったのか、③漱石の経済状態は彼の作品にどういう影響を与えたのか――の3点である。
漱石は、『吾輩は猫である』第4章で、主人公の珍野苦沙弥に『俺は実業家は学校時代から大嫌だ。金さへ取れゝば何でもする』と放言させている。漱石は、この後の作品でも、「権門富貴」に対する批判や嫌悪感をたびたび表明している。漱石は「金持ち」が嫌いだったのである。
「(娘婿の)松岡の推測に基づけば、朝日新聞入社以降の漱石の年収は、5000円に達していたことになる。年平均2000円の印税は、『国民作家』夏目漱石のイメージを考えれば多いとはいえないだろうが、花袋と比較すれば天と地ほども違っている。漱石はこの時期の小説家として稀に見る経済的な成功を収めたのである。・・・漱石は、朝日新聞の月給・賞与に支えられていたとはいえ、トップクラスの官吏・会社員並の収入を得ていたことになる」。
「漱石は『日記一二』に『十二月から会計を自分がやる事にする。一一月は小使をのぞいて四百十円か二十円である』と記しているので、その言葉どおりに実践したと思われる」。支出が年に換算すると5000円前後にもなることに疑問を感じたのだろう。妻・鏡子に対する不信感が、漱石に家計簿を付けさせたのである。『日記』にこういう一節がある。「妻は万事こんな風に凡て自分に都合のわるい事は夫に黙つてゐる女である。さうして出来る限り夫を甘く見又甘く取り扱へば夫(それ)が自分の資格でも増すやうに考へてゐる女である」。
「大正3年末には、漱石――夏目家は、贅沢な生活をすると同時に、朝日新聞社からの給料・賞与1年分にあたる金額を(岩波書店に)出資できる財政的余裕があった。その際に提供したのが、3000円の株券だったことは興味深い。夏目家の資産運用の中心は、土地や家屋でも美術品でもなく、株式の運用だったのである」。大正3年には、株の取引によって、3万円に及ぶ資産を形成していたのである。あの漱石が株取引をやっていたとは!
「漱石は文学市場の頂点に立ったうえに、獲得した資金で金融市場に参入して、『資本主義の精神』を実践する『経済人』として市場社会で成功を収めていたのである」。「金持ち嫌悪」に取り憑かれていたはずの漱石自身が、「金持ち」になってしまったのだ。
漱石は、大阪朝日新聞に寄稿した「文士の生活」の中で、自分の『清貧』をイメージづけようとしている。「漱石は『巨万の富』をもつ富豪たちと比較して、自分の収入の少なさを強調する一方、同時代の小説家とは比較にならないぐらい多額の収入を過剰に低く印象づけようとしている。朝日新聞社からの給料・賞与の額については、『社の方で聞いて貰ひたい』と言明を避けてしまう。年収3000円だといってしまっては、説得力がなくなってしまうからに他ならない。印税収入については、4版以降が30パーセントのきわめて高い院税率になっていることを隠し、『幾割の印税を取った処が、著書で金を儲けて行くと云ふ事は知れたものである』と、実態とは異なる説明をしている」。
「『その日暮らし』をする『清貧』な小説家として自らを語る発言は、印税と株の運用によって実現している豊かな生活を隠蔽するものといわざるを得ない。漱石は自分が文学市場の頂点を極め、金融資産を保持する『経済人』であることを忘れてしまったのだろうか」と、著者は手厳しい。
成功した「経済人」でありながら、「清貧」の小説家を装わねばならない漱石は、その後の作品を紡ぐに当たり、その大きなギャップに悩まされ続けたことだろう。
本書では、漱石没後に夏目家、鏡子に訪れた経済的成功と、その後の窮乏ぶりにも筆が及んでいる。しかし、この部分にはあまり興味が湧かないので、漱石の弟子・安倍能成の鏡子批判を挙げるに止めておきたい。「わたしは漱石先生は尊敬しているが、その家族は尊敬していない。漱石の門下と言われることはいゝが、遺族の人々から弟子あつかいにされる間柄ではない。遺族の人達は三十年にわたつて、漱石先生の労作によつて非常に富有なぜいたくな生活とも思われる生活をして来た。岩波書店からは出版書店という関係以上に随分厚意を受けていた。だから岩波を置いて桜菊書院に(『夏目漱石全集』の著作権を)許したことは徳義的ではないと思う。・・・遺族の人達は三十年間漱石先生の労作によりひたいに汗せずしてぜいたくな生活を送つてこられたのだ。もうこれ以上は先生の労作を国民の前に解放していゝのである」。安倍は、これまでの鏡子のライフスタイルに対する積年の不満を表明しているのだろう。
本書を読み終わって、漱石が泰然自若とした作家ではなく、私たちとあまり変わらない面も持ち合わせていたことを知り、漱石に親近感を覚えてしまった。