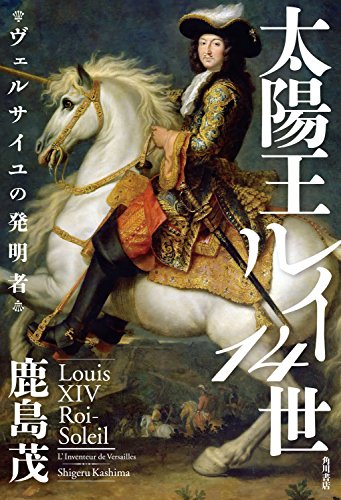ヴェルサイユ宮殿は、ルイ14世の「中央集権」と「宮廷」の蝶番だった・・・【情熱の本箱(190)】
ルイ14世については、高校の世界史の教科書レヴェルのことと、その出生にまつわる鉄仮面のことぐらいしか知らなかったが、『太陽王ルイ14世――ヴェルサイユの発明者』(鹿島茂著、KADOKAWA)によって多くのことを学ぶことができた。
著者・鹿島茂のルイ14世という人物の全体像の捉え方が、実に的確で見事なのだ。「『ルイ14世における中央集権化の問題』というものこそまさにヴェルサイユの造営の動機と強く結び付いていると理解するに至ったのです。中央集権化とヴェルサイユの『発明』はルイ14世の二つの業績であるどころか、一つだけの関心事の二つの現実化にほかならないということになるのです」。
私の関心事である鉄仮面については、残念ながら、あっさりした記述に止まっています。「真相は闇の中ですが、いずれにしても、23年に間に数えるほどしか性交渉のなかった(国王)夫婦にまるで『神』の思し召しであるかのように子供(ルイ14世)ができたことが、人々の想像力を刺激して、さまざまな伝説や物語をつくりあげることになったのです。その一つが有名な『鉄仮面』伝説で、これはルイ14世には双子の弟がいて里子に出されたが、後に(宰相のジュール・)マザランに発見され、鉄仮面を被せられて一生、牢獄に幽閉されたというものです。(アレクサンドル・)デュマや(フォルチュネ・デュ・)ボアゴベーはこれを膨らませて、波瀾万丈の鉄仮面物語に仕立てました。しかし、こうした伝説が広まったのは、ルイ14世が成人して、父王のルイ13世とまったく似ていないことが明らかになった後のことで」あった。
私にとって一番勉強になったのは、ニコラ・フーケの失脚の経緯である。「ルイ14世は宰相を置かず、忠実で有能な重臣だけを国王顧問会議の構成員として、親政をスタートさせましたが、その重臣の中でもひときわ大物ぶりを発揮していたのが財務卿のニコラ・フーケでした。フーケは国家運営の要である財政を文字通りたった一人で握り、王としても一目置かざるをえない超実力者となっていたのです。そして、ルイ14世の親政の第一幕は、このフーケと国王との隠れた反目から始まって、劇的な結末を迎えることになるのです」。
「フーケのこうした美点が彼にとって災いの元になったのです。つまり、フーケの『才能発見者としての才能』に激しく嫉妬した人物がおり、しかも、それが絶対君主のルイ14世だったというのが、フーケ最大の悲劇だったということなのです」。
「マザランが(死の直前)腹心の(ジャン・バチスト・)コルベールを『王へのプレゼント』として提供し、フーケの足元に送りこむように勧めたことです。ルイ14世は親政開始と同時にこの忠告にしたがい、コルベールを財務部長に任命し、フーケの金の出し入れを監視するよう命じたのです。・・・しかし、絶大な権力に酔いしれていたフーケはうかつにもコルベールによって足元が切り崩されている事実に気づくことはありませんでした」。
「(ルイ14世の)心をひとことでいえば、『王は二人要らない。一人でいい』というものでしょう。逮捕の段取りはコルベールによって入念に練りあげられていました。・・・逮捕に当たるのは、近衛の銃士隊隊長であるシャルル・ド・バッツ・カステルモール。すなわち、アレクサンドル・デュマが『三銃士』の主人公としたあのダルタニャンです。コルベールは、5、6年前、ダルタニャンがマザランの部下だったときに金を用立ててやったことがあり、二人はいわば御恩と奉公の関係で結ばれていたのです」。
フーケの逮捕こそ、「絶対君主ルイ14世の劇的な誕生の瞬間です。フーケの裁判は3年を要し、パリ高等法院は王とコルベールの期待に反して国外追放刑を宣告しました。しかし、これを不満とする王によって終身刑に変えられた結果、フーケは1665年にピニュロールの城塞に送られ、1680年まで生きて獄死しました。その間、フーケを恩人と慕う文学者や詩人によって減刑の請願が行われたり、擁護の書が書かれたりしました。・・・アレクサンドル・デュマはフーケを『ブラジュロンヌ子爵』の主人公とし、ルイ14世の双子の弟を伝説の鉄仮面として登場させました。・・・フーケ事件は人々の記憶に『朕は国家なり(正しくは、<国家とは私のことだ>)』というルイ14世の強烈な意志を強く刻み込み、親政を円滑に開始するきっかけとなったのです」。
「王を蝶番にした官僚機構と宮廷社会の同時併存を可能にするには、一つ、絶対的な要件がありました。それは双方を同じ空間に併設できるような王宮の造営です。ルイ14世の想像力にあっては、王宮そのものが自分を脳髄とした一つの身体として機能するような構造になっていなければならないのです。さらにいうなら、王宮の外に広がるフランスが、いやヨーロッパ全体が、世界そのものが、そのような構造になることが望ましいということです。・・・ルイ14世は王宮を自分の思いどおりに造ることで、臣民の無意識を支配下に置き、従属を永遠的なものにしようと考えたのです」。ヴェルサイユ宮殿誕生には、このような背景があったのだ。
この後も、ヴェルサイユ宮殿の造営、そこで繰り広げられた愛妾たちの激しい闘い、ナントの勅令廃止、気晴らしとしての侵略戦争、絶対主義の実態――などが記述されていく。当時を彷彿とさせる生き生きとした筆致はさすが鹿島だが、私にとっては、フーケを追い落とし、大きな権力を手にしたコルベールのその後が気にかかる。「間接税の増加でコルベールは念願の財政バランスの確立に成功したかといえば、これは否と答えるほかありません。歳入をいくら増やしても、ルイ14世が戦争とヴェルサイユの拡大にのめり込んだために、歳入は歳出の急増には追いつけず、毎年2千万リーヴルの赤字を計上してしまったのです。・・・そのため、コルベールはヴェルサイユの増改築に際してはルイ14世に対してあまりいい顔を見せることができませんでした。しかし、この予算の出し渋りがヴェルサイユ宮殿の天井崩落事件をきっかけに失寵を招くことになるのですから、コルベールとしては泣くに泣けない気持ちだったことでしょう」。ルイ14世の不興を買ったコルベールは、晩年を不遇のうちに過ごしたのである。昔も今も、絶対権力者に振り回される人間たちの運命に思いを馳せると、複雑な気持ちになるのは私だけだろうか。