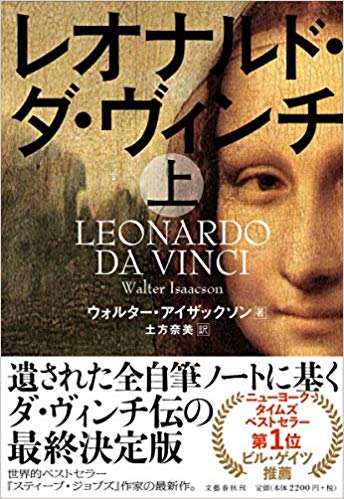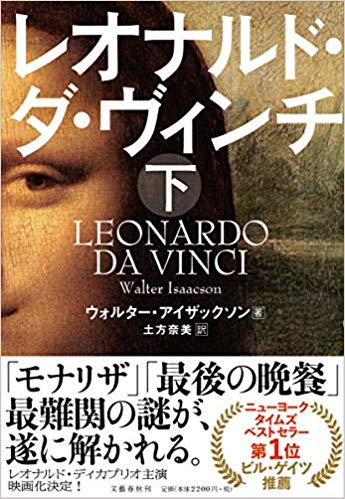7200ページに及ぶレオナルド・ダ・ヴィンチのメモが教えてくれた7つのこと・・・【情熱の本箱(290)】
奇跡的に今日まで残存しているレオナルド・ダ・ヴィンチの7200ページに及ぶメモや走り書きから再現・構成された『レオナルド・ダ・ヴィンチ』(ウォルター・アイザックソン著、土方奈美訳、文藝春秋、上・下)から、7つのことを教えられた。
第1は、レオナルドは生涯を通じて、記録魔だったこと。
「何世代も続く公証人の家系に生まれたためか、レオナルドには事細かに記録を残そうとする習性があった。観察したもの、さまざまなリスト、アイデア、スケッチを日常的にノートに書き込む習慣は、ミラノに到着してまもなく1480年代初頭に始まり、生涯にわたって続いた。タブロイド紙ほどの大きさの紙に書いたものもあれば、ペーパーバック本ほどの大きさの革表紙のついたノートを使うこともあった。後者は常に持ち歩き、見聞きしたことを書き留めた。ノートを持ち歩く目的の一つは、興味を引いた光景を記録するためだ。特に注目したのは人間とその感情である。『町を歩くときには人々の会話、口論、笑い、殴り合いといった場面や行動をよく観察し、記録し、吟味すること』という記述がある」。
「現存する7200ページ以上のノートは、おそらくレオナルドが実際に書いたものの4分の1程度だろう。それでも作成されて500年も経っていることを思えば、良く残っているほうだ」。
第2は、レオナルドは同性愛者であることを隠さず、そういう人生を楽しんでいたこと。
「レオナルドは恋愛対象として、また性的対象として、男性に惹かれた。そしてミケランジャロとは違い、それをまったく気に病んでいなかった。同性愛者であることを公言はしていなかったが、隠しもしていなかった。ただ、それは自らが異端であり、公証人という一族の伝統的職業を継ぐような人物ではないという意識につながっていたのかもしれない。生涯にわたりレオナルドは、工房や自宅に多くの美しい若者を住まわせている。・・・最も長い期間にわたって真剣に交際した相手は、1490年からレオナルド邸に住むようになった若者だ。天使のような外見とは裏腹に人格は悪魔のようで、『小悪魔』を意味するサライというニックネームをつけられていた。・・・レオナルドが書いた性的なつぶやきや意味深なメモの多くはサライに関するものだ。レオナルドに女性の恋人がいた形跡はなく、異性とのセックスについての不快感を吐露している」。
「同性愛者であることは、レオナルドの心の深い部分に影響を与えた。それは彼に人とは違う、社会に居場所のないアウトサイダーという意識を植えつけた。・・・腹違いの弟たちが生まれたことで、嫡出子ではないという事実を改めて思い知らされることになった。非嫡出子であり、芸術家で、しかも男色でに二度も告発された同性愛者。まさに自他ともに認めるはみだし者だった。ただ芸術家のご多分に漏れず、それは彼にとって弱みではなく、むしろ強みだった」。
「同性愛はフィレンツェの芸術界において、またヴェロッキオの仲間うちでも珍しくはなかった。ヴェロッキオ自身一度も結婚したことはない。ボッティチェリも同じで、何度か男色で有罪判決を受けている。ほかにもドナテッロ、ミケランジェロ、ベンヴェヌート・チェリーニ(男色で二度の有罪判決)などの例がある。レオナルドが『アモーレ・マスキュリーノ(男の恋愛)』と呼んだ男色が当時のフィレンツェであまりにも盛んだったことから、『フロレンツァー』がドイツ語で『ゲイ』を意味する俗語になったほどだ。・・・ただレオナルドも苦々しく振り返っているように、それでも男色は犯罪で。事件として裁かれることもあった。・・・教会も同性愛を罪とみなしていた」。
「レオナルドの生きざまやノートからは、自らの性的欲求をまったく恥じていなかったことが明らかだ。むしろそれを楽しんでいるかのようだ」。
第3は、私が「モナ・リザ」より気に入っている「白貂を抱く貴婦人」のモデルが辿った人生が明らかにされていること。
「チェチリア・ガッレラーニは驚くべき美貌の持ち主で、ミラノの知的な中流階級の家に生まれた。父親は外交官であると同時にミラノ公の財務担当を務め、母親は著名な法学教授の娘だった。とりたてて資産家だったわけではない。・・・チェチリアは、実質的なミラノ公、ルドヴィーコ・スフォルツァに見初められた。ルドヴィーコは無慈悲な男だったが趣味は良く、チェチリアの内面と外面の美しさに惚れ込んだ。15歳であった1489年、チェチリアは家族のもとを離れ、ルドヴィーコに与えられた部屋に住んでおり、翌年にはルドヴィーコの息子を身ごもった」。
「しかし二人の関係は一つ大きな問題を引き起こした。ルドヴィーコは1480年にフェラーラ公エルコレ・デステの娘、ベアトリーチェと婚約を結んでいた。この婚約はイタリアきっての由緒ある名家とルドヴィーコとの重要な同盟の象徴であり、ベアトリーチェが5歳のときに結ばれ、彼女が15歳になる1490年に結婚式を挙げることが決まっていた。盛大なパレードや式典が催されるはずだったが、チェチリアに夢中になったルドヴィーコはまるで興味を示さなくなった」。
しかし、結局、延期されていたベアトリーチェとの結婚式が挙行され、ルドヴィーコは次第にベアトリーチェを心から尊敬するようになる。そして、チェチリアが息子を出産すると、ルドヴィーコは富裕な伯爵とチェチリアを結婚させた。「チェチリアは優れた文芸のパトロンとして新たな人生を送ることになった」。
「チェチリアの美貌は時代を超えて記憶されることとなった。二人にとって最良の時期であった1489年、ルドヴィーコは当時15歳のチェチリアの肖像画をレオナルドに注文した。ルドヴィーコがレオナルドに絵を描かせたのは、これが初めてだ。・・・こうしてすばらしく美しい、また革新的な傑作が誕生した。多くの意味で、レオナルドの絵画のなかでも最も魅力的なものと言える。『モナリザ』をのぞけば、私の一番好きな作品だ。クルミ材の画板に油絵の具で描かれたチェチリアの肖像画は、『白貂を抱く貴婦人』として知られる。きわめて革新的で、感情豊かで生き生きとしたこの作品は肖像画のあり方を一変させた。・・・当時一般的であった横向きではなく、斜め前から見た姿を描いている。体は鑑賞者から見て左を向いているが、顔は光の差す方向からやってきた何か(おそらくルドヴィーコだろう)を見るために、ぱっと右に向けたようだ、チェチリアが抱いている白貂も何かを警戒して、耳をそばだてている。どちらも生き生きとしていて、・・・空虚でぼんやりとした目をしていない。この場で何かが起きている。レオナルドはある瞬間に映し出された、登場人物の外面と内面の物語をとらえている。手や前足、目、謎めいた微笑のメドレーからは、身体と心の動きがともに伝わってくる」。
「この絵には内なる心の動きがとらえられている。チェチリアの瞳、謎めいた微笑、白貂を抱き、愛撫する可能的なしぐさは、その感情をはっきりと示すとまでは言わなくても、少なくともほのめかしている。明らかに何かを思い、その表情には心の動きが表れている。レオナルドはチェチリアの心や魂の動きを描きながら、観る者の内なる思いに働きかけている。それまでの肖像画とは、そこが根本的に違う」。
第4は、私にとって最も興味深い人物、チェーザレ・ボルジアとレオナルドとの関係が生々しく記されていること。
「ミラノにおいてレオナルドのパトロンだったルドヴィーコ・スフォルツァは、その冷酷さで知られた。ミラノ公の座を手に入れるために甥を毒殺したことなど、それを物語る逸話は枚挙にいとまがない。しかし次にパトロンとなったチェーザレ・ボルジアと比べれば、ルドヴィーコなど聖歌隊の少年のようだ。殺人、背信、近親相姦、放蕩、残虐性、裏切り、汚職など、いまわしい行為全般においてチェーザレは名人級だった。権力に飢えた残酷な独裁者であったうえに、血に飢えたソシオパス(反社会性パーソナリティ障害)でもあった。・・・歴史的に唯一評価されたのは(評価されるいわれもなかったが)、マキャベリの『君主論』で狡猾さを体現する人物として描かれたことで、マキャベリはチェーザレの冷酷さこそが権力の源泉であったと書いた」。
「レオナルドはチェーザレ・ボルジアに恭順の意を示したいというマキャベリとフィレンツェ指導部に要請されて、チェーザレのもとへ赴いたのかもしれない。・・・あるいはフィレンツェ政府は、ボルジア家にスパイを紛れ込ませるつもりでレオナルドを遣わしたのかもしれない。どちらの面もあったのかもしれないが、いずれにせよレオナルドは単なる人質でもスパイでもなかった。自ら行きたいという気持ちがなければ、レオナルドはこの話を受けなかったはずだ」。
「チェーザレはレオナルドのために大仰な『パスポート』をしたためた。1502年8月18日付のこの書状は、レオナルドに特別な待遇と通行権を与えるという内容だった。・・・チェーザレのパスポートには、レオナルドは画家ではなく軍事技術者であり、イノベーターだと書かれている。20年前にミラノ公に求職の手紙を書いて以来、レオナルドがずっと夢見てきた役割だ。その時代きっての有力な武人に、すばらしい条件で温かく迎え入れられたのだ。もはや絵筆を見ることすら耐えられない様子、と言われていたレオナルドは、軍人として活躍する機会を与えられた」。
「(1502年)10月7日にはマキャベリが到着した。フィレンツェから使者として、また情報収集役として送られてきたのである。マキャベリはチェーザレの諜報担当に読まれることを承知のうえで、毎日フィレンツェに報告を送った。そのなかではレオナルドのことを『チェーザレの秘密を知るもう一人の人物』あるいは『傾聴すべき知識を持った友人』としか書いていない。それがどんな状況であったか想像してみよう。まるで歴史ファンタジー映画のように、1502年から03年にかけての冬の3カ月、『ローマ法王の血と権力に飢えた息子、狡猾で独特な道徳観を持った外交官兼物書き、そして技術者を自認する傑出した画家』という、ルネサンス期を代表する英傑3人が要塞に囲まれたちっぽけな街にこもっていたのだ」。
「『不和や戦闘などごめんだ。これほど野蛮な狂気の沙汰はない』。レオナルドはあるとき、ノートにこう書いている。それにもかかわらず、8カ月にわたってチェーザレ・ボルジアに仕え、その軍と行動をともにした。ノートに殺戮を非難する警句を綴り、道徳心から菜食主義者になったような人物が、なぜその時代きっての残虐な殺人者のもとで働くことを選んだのか。ここにはレオナルドのプラグマティズムが表れていると言える。メディチ家、スフォルツァ家、ボルジア家などが権力闘争を繰り広げるイタリアにおいて、レオナルドは誰をパトロンとすべきか、いつ乗り換えるべきかを巧みに判断することができた。ただ、それだけではない。俗事に頓着しないようでいて、レオナルドは見直に惹かれるところがあったようだ」。画家にはもう飽き飽きしていたレオナルドは、軍事技術者になるという長年の夢を漸く実現できるチャンスを逃したくなかったのである。
第5は、レオナルドの23歳年下のライバル、ミケランジェロ・ブオナロッティとの相剋がリアルに描かれていること。
「(戦争画『アンギアーリの戦い』の)作品を完成させようとし、しかも壁から剥がれ落ちないようにしようともがいていた1505年夏、レオナルドは物理的にも比喩的な意味でも、背後に若きライバルの存在を感じていたに違いない。同じ部屋の向かいの壁では、フィレンツェの芸術界の期待の星、ミケランジェロ・ブオナロッティが絵を描く準備にとりかかっていた」。
「ヴァザーリによれば、ミケランジェロはレオナルドを『心底軽蔑していた』」。
「『自然な魅力、優雅さ、洗練、親しみやすい物腰、美しいものを愛する心を持ち、そしてなりより無宗教であったレオナルドを、ミケランジェロが嫉妬し、嫌悪するのは当然であった』と作家のセルジュ・ブランリは書いている」。
「(めったに他の画家を批判することのなかったレオナルドだが)『人の裸体を優雅さのかけらもない材木のように描いている。まるで人間ではなくクルミの大袋、人体の筋肉ではなく束になった大根でも見ているような気がしてくる』(と、ミケランジェロの絵を貶している)」。
著者による両者の対比は、このようにまとめることができるだろう。
●宗教心が篤いミケランジェロ、信仰心が薄いレオナルド
●禁欲的なミケランジェロ、人生を楽しもうと享楽的なレオナルド
●気難しいミケランジェロ、社交的なレオナルド
●彫刻が得意なミケランジェロ、絵画が得意なレオナルド
●作品を完成させることに努めたミケランジェロ、完璧さを求めるあまり未完が多いレオナルド
第6は、レオナルドの解剖学への情熱が、医学上の重要な発見をもたらしたこと。
「100歳の老人の死因を探るなかで、レオナルドはある重要な科学的発見をしている。脂肪斑が付着することで動脈の壁が厚くなり、硬くなるという動脈硬化の起こるプロセスを記録したのだ。・・・著名な医学史家で心臓学者のケネス・キールは、レオナルドの分析は『加齢による動脈硬化発生のメカニズムを初めて説明したもの』と指摘する」。
「レオナルドは血液循環の中心は肝臓ではなく、心臓であることをいち早く見抜いていた。・・・レオナルドの心臓の研究のなかで、というより解剖学研究のなかでも最大の業績と言えるのが、大動脈弁の仕組みを解明したことだ。・・・解剖学者がレオナルドの主張が正しかったと気づくまでに、450年もかかった」。
第7は、「モナ・リザ」のモデルは誰かという問題に決着がつけられていること。
「(リザ・デル・ジョコンドは)1479年にゲラルディーニ一族の傍系の娘として生まれた。・・・15歳で、絹取引で財を成したものの家柄としてはさほど良くないジョコンド家に嫁いだ。・・・落ちぶれた地主貴族と有力な商家との結婚は、互いにとってうまみがあった。リザの夫となったフランチェスコ・デル・ジョコンドはその8カ月前に前妻を亡くしたばかりで、2歳の息子がいた。・・・政略結婚であったにもかかわらず、フランチェスコはリザを心から愛していたようだ。リザの家族を経済的に支援しており、1503年までに2人のあいだには息子が2人生まれている。・・・(フランチェスコが)24歳になろうとしていた妻の肖像画をレオナルドに依頼したのはこの頃だ」。
「とはいえ、これは単なる絹商人の妻の肖像画でもなければ、もちろん顧客の注文に応えるための絵でもない。レオナルドは制作を始めた数年後には(あるいは初めから)、フランチェスコ・デル・ジョコンドのためではなく、自らのため、永遠に残すための普遍的作品としてこれを描いていた。フランチェスコに納めることもなければ、銀行の記録を見るかぎり対価を受け取ることもなかった。着手してから16年後に亡くなるまで、フィレンツェ、ミラノ、ローマ、そしてフランスへと、ずっと持ち歩いていた。その間、完璧を目指して油絵の具の薄い層を重ねながら修正を続け、人間と自然に対する深い理解を反映させていった。新しい洞察、新しい理解、新しいひらめきを得るたびに、ポプラ画板の上にやわらかに筆を重ねるのだ。レオナルドが人生の旅路を重ねて深みを増していくなかで、『モナリザ』も深みを増していった」。
巻末の「レオナルドに学ぶ」では、20項目が挙げられている。
●飽くなき好奇心を持つ。
●学ぶこと自体を目的とする。
●子供のように不思議に思う気持ちを保つ。
●観察する。
●細部から始める。
●見えないものを見る。
●熱に浮かされる。
●脱線する。
●事実を重んじる。
●先延ばしする。
●「完璧は善の敵」で結構(=完璧になるまで手放さない)。
●視覚的に考える。
●タコツボ化を避ける。
●届かないものに手を伸ばす。
●空想を楽しむ。
●パトロンのためだけでなく、自らのために創作する。
●他者と協力する。
●リストを作る。
●紙にメモを取る。
●謎のまま受け入れる。
アイザックソンという達意の評伝作家によって、私たちの眼前にレオナルドが生き生きと甦ってきたのは、嬉しい限りだ。