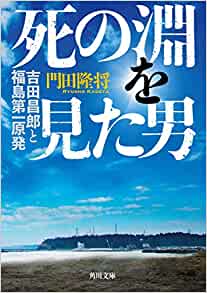福島第一原発の死の淵で、命を賭けて闘った男たちの壮絶な記録・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2188)】
我が家の庭の餌台には、連日、常連のシジュウカラ(写真1~3)2羽、スズメ(写真4~6)2羽が交互にやって来ます。アオダモ(写真7、8)、カジイチゴ(写真9)、ボタン(写真10)が咲いています。繁ったスギナに囲まれたツクシ(スギナの胞子茎。写真11)を見つけました。
閑話休題、心友Kから薦められた『死の淵を見た男――吉田昌郎と福島第一原発』(門田隆将著、角川文庫)を手にしました。
福島第一原発事故を巡る、緻密な取材に基づくドキュメンタリーだが、未曾有の重大事態に直面した人間たちがどう考え、どう行動したかが、生々しく伝わってきます。
原発にとって一番避けねばならない事態は、「全電源喪失」と「冷却不能」であるが、福島第一原発事故では、突如として、しかも手探り状態で、この2つに対処せねばならないという極限の状態に追い込まれたのです。
「暗闇の中で原子炉建屋に突入していった男たちには、家族がいる。自分が死ねば、家族が路頭に迷い、将来がどうなるかもわからない。しかし、彼らは意を決して突入していった。・・・命の危険をかえりみず、放射能に汚染された真っ只中に突っ込んでいった。・・・今回の不幸な原発事故は、はからずも現代の日本人も、かつての日本人と同様の使命感と責任感を持ち、命を賭けてでも、毅然と物事に対処していくことを教えてくれた。その意味では、この作品で描かせてもらったのは、原発事故の『悲劇の実態』と共に、最悪の事態に放り込まれた時に日本人が発揮する土壇場の『底力と信念』だったかもしれない。なぜ彼らは、ここまで踏ん張れたのだろう。同時代を生きるひとりの人間として、私は取材のあいだ中、そのことを考えつづけた。その答えが、本作品で読者の皆さんに少しでも伝われば、これに過ぐる喜びはない」。著者のこの狙いは、見事に成功しています。その証拠に、読みながら、私は何度も涙を拭わねばなりませんでした。
「2011年3月11日午後2時46分。ゴゴゴゴゴゴゴゴゴ・・・異様な音と共に、突然、大地が揺れ始めた。(地震だっ)。(福島第一原発所長の)吉田(昌郎、56歳)は、すぐに書類をおいて立ち上がった」。それは、突然、やってきたのです。
「『あっ』。その時、3号機の補機操作員の指導を担当している伊賀正光(35歳)は信じられないものを見た。自分の方に黒っぽい土色の濁流が向かっていた。それは、猛り狂った竜が、すべてを呑み込むような、おそろしい光景だった。大津波である」。
原子炉建屋への必死の突入が試みられます。「『これをやらなければ、格納容器は守れない』。大友(喜久夫、55歳)は、そう考えていた。プロフェッショナルである彼ら(大友と、大井川努、47歳)には、格納容器を守る、すなわち『原子炉を守る』ことしか頭にない。無論、格納容器を守れなければ、自分や家族の命だけでなく、日本そのものがだめになる。・・・バルブはやっと開度25パーセントに達した。・・・あとは、一刻も早くこの場から離脱しなければならない。放射能の汚染を少なくするためには、この場にいる時間をできるだけ短くすることだ。そして、バルブを開けたことを一刻も早く中操(中央制御室)に伝えなければならない。だが、通信手段はない。自分たちが帰って、伝えるしか方法はない。セルフ・エアのボンベがもつのはせいぜい20分である。行って帰ってくるまでの目標時間は『15分』だ。・・・しかし、バルブを開けた二人は、ここで、もうひとつ、大きな仕事をおこなっている。・・・空気ボンベのエアがなくならないうちに中操に辿り着かなければならない二人は、帰りに圧力の数値を確認し、それが中操で正しく表示されるかを見ようと思ったのである。・・・二重扉の中は、死の世界である。そこから出ることは、生の世界に戻ることを意味していた」。
「第二陣は、遠藤英由(51歳)と紺野和夫(52歳)の二人だ。・・・しかし、第一陣と第二陣が開けるバルブの位置には、あきらかな差があった。大友たちが開けたバルブは、格納容器のコンクリート壁の外側にあった。放射能はその壁によって遮蔽され、逓減されている。これに対して、第二陣が開けようとしたバルブは、コンクリート壁のないサプレッション・チェンバー(圧力抑制室)の上にある。すなわちコンクリートによる放射能遮蔽のない場所である。それが線量にどれほどの差をもたらすのか、誰にもわからなかった。『行ってみなければわからない』のである。・・・行くしかない――二人は、さらに進んだ。・・・遠藤は必死だった。異常な高さの線量が、二人を襲っている。しかし、『行く』しかなかった。・・・二人が中操に戻ってきた時、『大丈夫か!』という声がかけられた。それほど二人は疲労困憊だった。『ダメだった・・・』。装備を脱ぎながら、遠藤がそう言った。そして、こうつけ加えた。『線量が高くて、無理でした・・・メータが振り切れた』。それは、絞り出すような声だった。メータが振り切れた。恐れていた事態だった。もはや、現場に立ち入れないほどの線量が出ている。遠藤のひと言はその冷徹な事実を伝えていた。・・・線量の『数字』との闘いでもあった過酷なベント作業は、恐怖との闘いでもあり、同時に技術者としての知識と理論が集約された総合戦となっていた」。ベントとは、一言で言えばガス抜きを意味し、放射能が低い空気を逃がすことです。
「その瞬間、伊沢(郁夫。52歳)たちの身体は、凄まじい衝撃音と共に浮き上がった」。一号機が爆発したのです。
「吉田は、現場のトップとして、次々と新たな手立てを打たなければならなかった。6基の原子炉を抱える福島第一原発の所長として、それぞれを制御している責任者である。だが、本店とテレビ会議でやりあっている途中、あるいは、現場で部下たちに指示を与えているさなかに、官邸からの電話が入ってきたのである。しかも、それが、『官邸がもう、グジグジ言ってんだよ!』というレベルのお粗末な話である。なんで『素人』の理不尽な要求が直接、現場の最前線で闘っている自分のところに飛んでくるのか。吉田は、そのことが腹立たしくてならなかった。直後に本店から、吉田に海水注入中止命令が下った。官邸の意向が本店に伝えられたに違いない。しかし、吉田は、直前に先まわりしてその『対策』を打っていた。『本店から海水注入の中止の命令が来るかもしれない。その時は、本店に(テレビ会議で)聞こえるように海水注入の中止命令を俺が出す、しかし、それを聞き入れる必要はないからな。おまえたちは、そのまま海水注入をつづけろ。いいな』。テレビ会議の途中、吉田は、わざわざマイクに入らないようにして担当者にそう言い含めていたのである。海水注入しか方法がないことがなぜわからないのか、と吉田は思った」、この時の官邸の主こそ、首相・菅直人だったのです。
「地震発生以来、一睡もせずに復旧への対策を練り、現場にそれを実行させている吉田所長は、自らの足を引っ張るさまざまな『相手』と闘わなければならなかったのである」。
そして、吉田の姿を見て、復旧に全力を尽くす社員たちもいよいよ最期が近づいていることを知ります。「この時、吉田は、頭を垂れながら、あることを考えていた。『私はあの時、自分と一緒に<死んでくれる>人間の顔を思い浮かべていたんです』。吉田は、その場面をこう回想した。・・・それは、『日本』を守るために闘う男のぎりぎりの姿だった」。
「本書は、吉田昌郎という男のもと、最後まであきらめることなく、使命感と郷土愛に貫かれて壮絶な闘いを展開した人たちの物語である」。
吉田は、事故発生から2年4か月後の2013年7月9日に58歳で病没したが、事故がその死を早めたことは間違いない――合掌。