59年間に亘り実施されてきたギンギツネの家畜化実験の全貌が明らかに・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3255)】
林道を威風堂々とやって来るキジの雄(写真1、2)と鉢合わせしました。ヒヨドリ(写真3)、ツグミ(写真4)、イカルチドリ(写真5)、コチドリ(写真6、7)をカメラに収めました。オオカンザクラ(写真8~11)が咲いています。クルメツツジ(キリシマツツジ。写真12、13)が紅葉しています。因みに、本日の歩数は14,588でした。













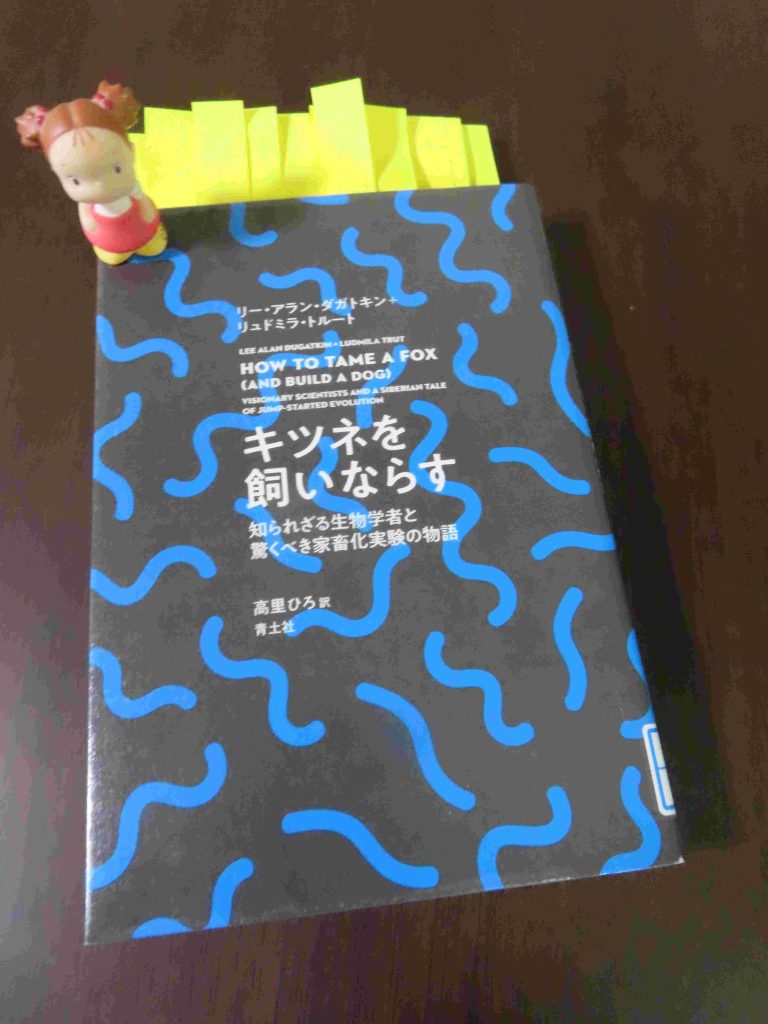
閑話休題、『キツネを飼いならす――知られざる生物学者と驚くべき家畜化実験の物語』(リー・アラン・ダガトキン、リュドミラ・トルート著、高里ひろ訳、青土社)には、感動した! 何にそんなに感動したのかって?
ソ連時代の極寒の地シベリアで開始され、その後、59年間に亘り営々と実施されてきたギンギツネの家畜化実験の全貌が描かれており、その記録を取り続けてきた生物学者リュドミラ・トルートと、リュドミラにまるで飼い犬のように忠誠心を示すキツネたちとの心の交流に胸が熱くなったのです。
卓越した生物学者ドミトリ・ベリャーエフの指導のもと、リュドミラは人間との接触を求めるキツネたちを慎重に選択して同居したのだが、もちろん、人間に敵愾心丸出しのキツネたちも存在します。しかし、この敵愾心丸出しのキツネたちも重要な研究対象です。これらの敵愾心丸出しキツネと忠誠心を示すキツネのDNAを含めた比較は重要な意味を持つからです。
ベリャーエフは、「オオカミのイヌへの家畜化を、オオカミの代わりに遺伝的に近い種であるギンギツネで再現しようと考えた。キツネをイヌのような動物に変えることができれば、家畜化はどのように起きたのかという古い謎を解くことができるかもしれない。さらには人類の進化について重要な洞察を得られるかもしれない」と考えて、大胆な実験に着手したのです。
「リュドミラは(選択した雌ギツネの)プシンカが1歳になり、交尾して、妊娠してから、彼女を家で飼うことを決めた。そうすることで、リュドミラはプシンカが彼女との同居にどのように順応するかだけでなく、人がいる環境で生まれた子ギツネたちの社会化は飼育場で生まれたほかの子ギツネと異なるのかどうかも観察することができるからだ。1975年3月28日、出産予定日の10日前に、プシンカは新居に移された」。「動物行動学史上前例のない研究が始まろうとしていた」。
「リュドミラが長期にわたるプシンカとの暮らしで発見したように、この愛らしい小柄なキツネは完全にリュドミラとの同居に慣れただけでなく、もっとも忠実なイヌに負けぬほど忠実になった」。
驚くべきことに、「(プシンカの子孫の)キツネたちの一部は今や、イヌにとてもよく似てきたので、オオカミがイヌになるときに骨格が変化したように、キツネたちの骨格も変化しているはずだとリュドミラは確信していた。とくに、従順なキツネの鼻づらはより短く、丸く変化し、友好的な行動と似つかわし友好的な顔つきになった」のです。
生物や進化に関心を抱く者にとっては堪えられない力作です。
