ニーチェは、ハイデガーは、死をどう考えたのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3585)】
【読書の森 2025年1月28日号】
情熱的読書人間のないしょ話(3585)
イソヒヨドリの雌(写真1~4)、バン(写真5、6)、ヒドリガモの雄と雌(写真7、8)、飛翔するダイサギ(写真9)をカメラに収めました。シクラメン(写真10)が咲いています。











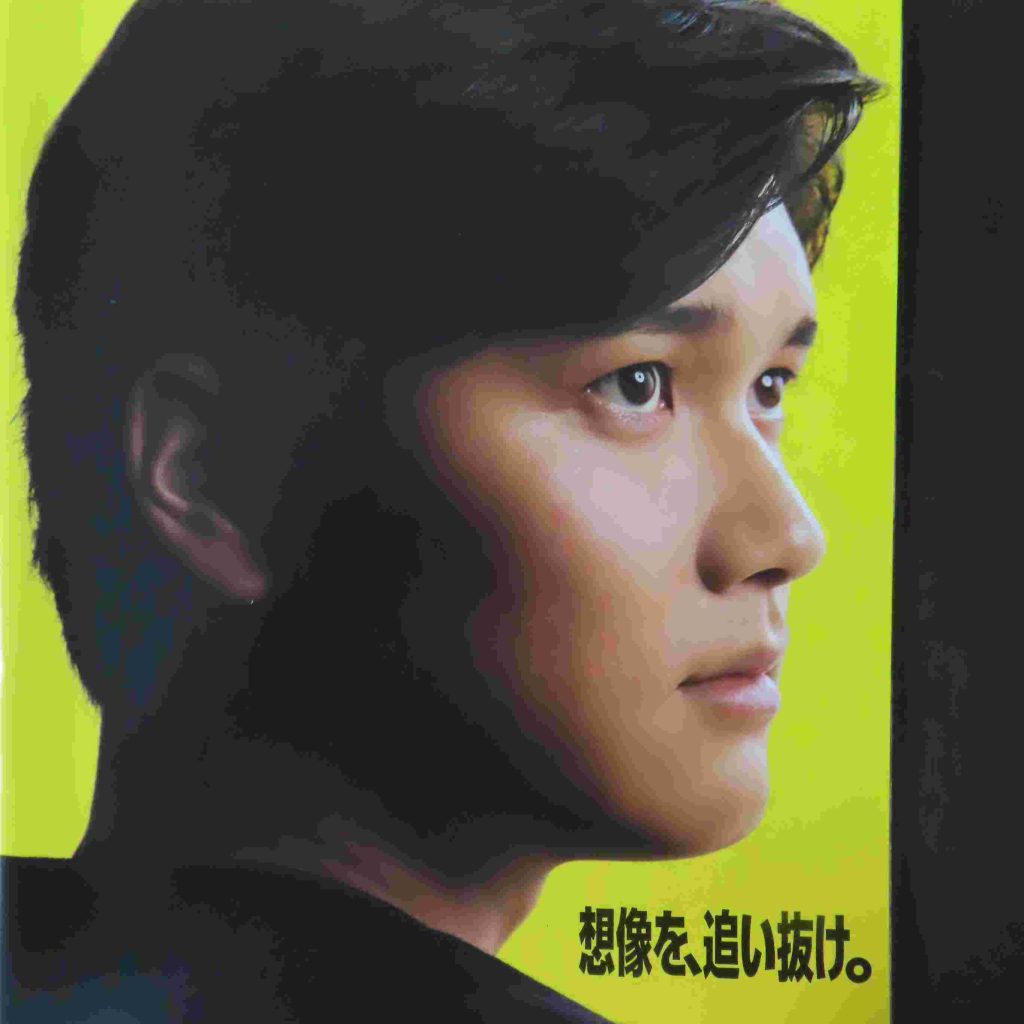
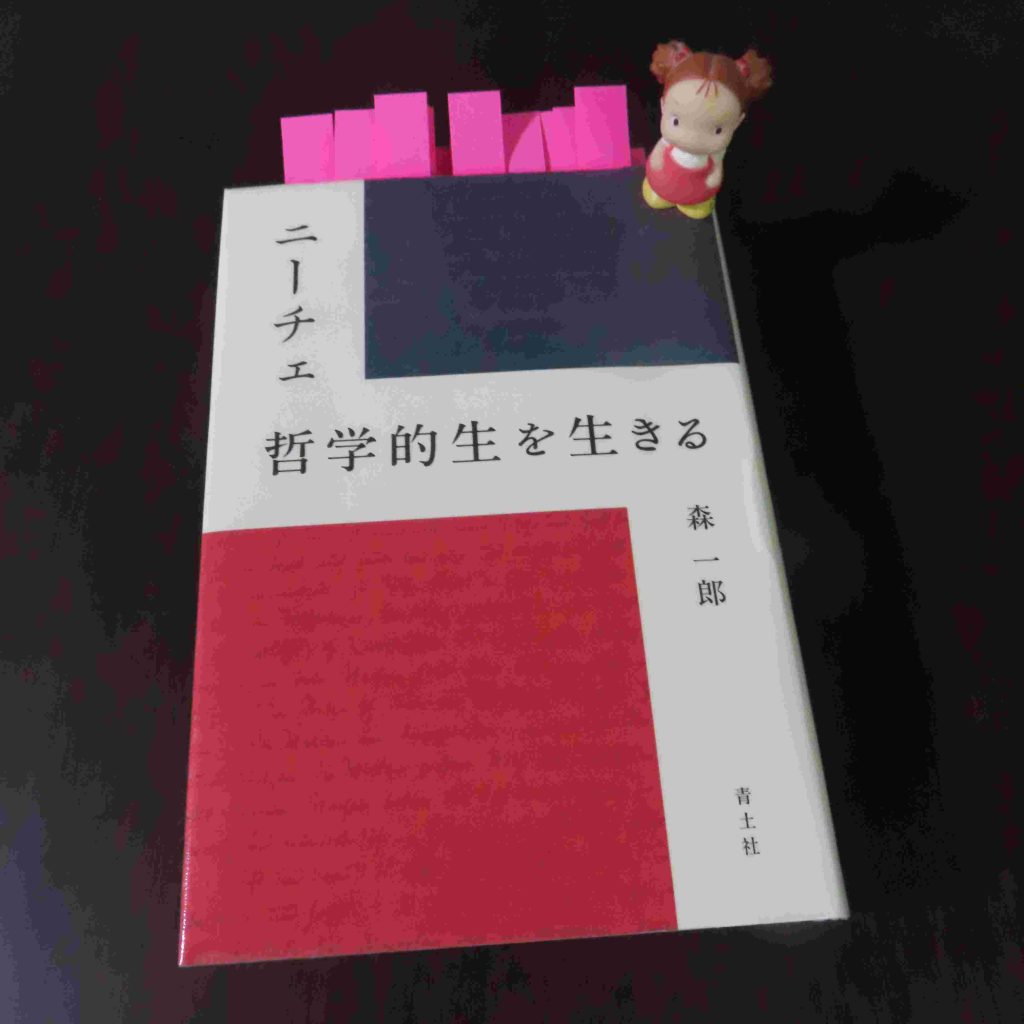
閑話休題、私が哲学関係の書籍を渉猟するのは、哲学者たちが死をどう考えたのかを知りたい一心からです。
『ニーチェ 哲学的生を生きる』(森一郎著、青土社)のおかげで、フリードリヒ・ニーチェとマルティン・ハイデガーの死に対する考え方を確認することができました。
●ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』
「自由な死」の章では、みずからの死を従容として受け入れることのできる度量が、「ゆっくりした死」のみを欲する狭量と対比されている。死は喜ばしい訪問客であるかのごときである。不意に訪れるこの遠来の客を歓待することができるよう、日頃から準備怠りなく充実した生を生きることが何よりも望ましいとされる。この接待の用意――つまり「死の稽古」――が首尾よくなされたあかつきにこそ、「ふさわしい時に死ぬ」という満願が成就するのだ。だから、順風満帆の生のさなかに「勝利に満ちて」、死が「祝祭」となるような死の迎え方こそが「最善」である。
●ハイデガー『存在と時間』
ハイデガーは、ニーチェの『ツァラトゥストラはこう言った』の「自由な死」の章を意識して、死の分析を手がけ、「自分自身の死に向かって先駆しつつ自由となること」を強調している。ハイデガーはニーチェの理想主義的とも言える「情熱」を正面から受け止め、しかも「死への存在」という新たに彫琢された概念を駆使しつつ、伝統的な「人間」の概念に対する仮借なき異議申し立てを遂行することによって、ニーチェのモティーフをみずからの存在論的企投のうちに根付かせた。
