光源氏に犯された藤壺は、光源氏を疎ましく思っていた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3594)】

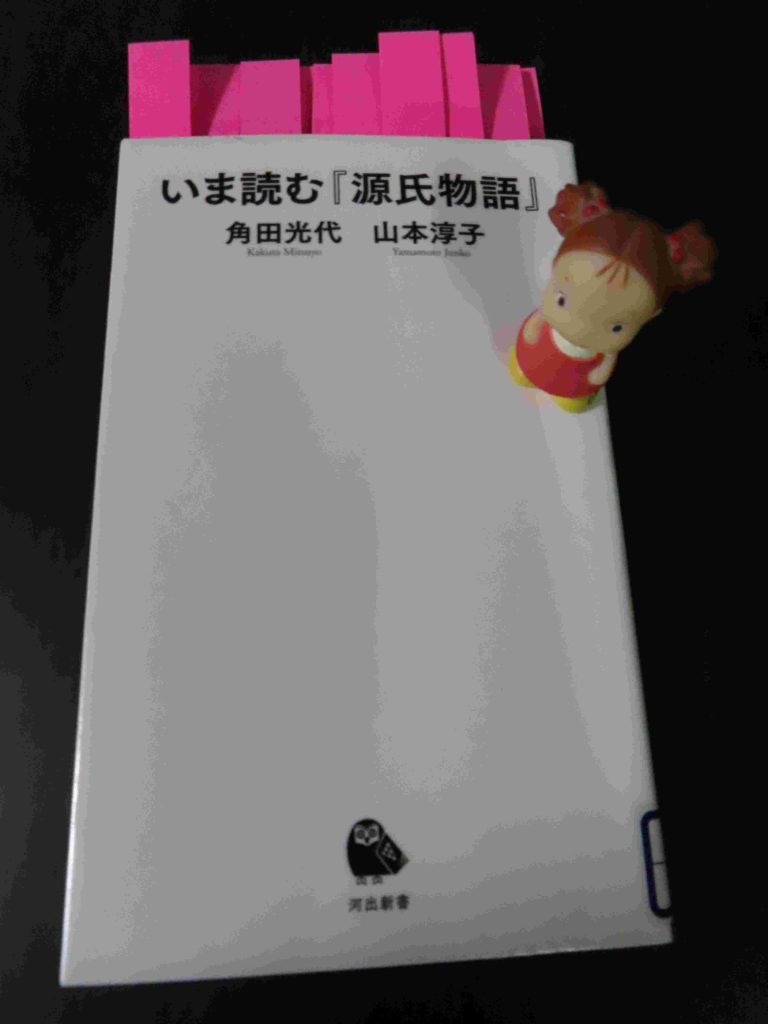
『謹訳 源氏物語』(林望現代語訳、祥伝社文庫、全10巻)を始め、『源氏物語』や紫式部の研究書も読み漁ってきたが、今回、手にした『いま読む<源氏物語>』(角田光代・山本淳子著、河出新書)からも多くのことを学ぶことができました。
●紫式部は、自分の馴染みの場所や中流下級の貴族階級が暮らす世界を舞台にした「帚木」、「空蝉」、「夕顔」の三帖から書き始めた。これを読んだ藤原道長に「長篇を書いて」と依頼され、紙も筆も硯もふんだんにある環境を与えられ、そこで「桐壺」や「若紫」を書き進めていった。
●一条天皇は定子が好きなあまり、定子が亡くなった後、その妹の御匣殿に手を出してしまう。
●清少納言は定子を励ますために「春はあけぼのです!」と美しく楽しい内容の『枕草子』を書き、紫式部は彰子のために感情的になって「『枕草子』なんてダメですよ!」と日記に書いた。
●桐壺帝と桐壺更衣には一条天皇と定子が重ねられているという新説は定説にまではなっていないが、否定しがたい説として議論されている。
●『紫式部集』を読むと、紫式部が夫・藤原宣孝を愛していたことがよく分かる。
●その気はないのに光源氏に犯された藤壺は、光源氏を疎ましく思っていた。藤壺が桐壺帝の一周忌をきっかけに出家したのは、光源氏を拒絶するためだった。
●紫式部は、藤原道長に雇われた時は『源氏物語』を「めでたしめでたし」で終わらせるつもりだったが、「藤裏葉」まで書き終えて「本当に私はこれが書きたかったのだろうか」と思い至り、光源氏が苦しめられる側になったらどうなのかを「若菜」以降で書いていった。
●紫式部は、「匂宮」以降の第三部では、仏教をも否定して、それまで書いてきたことに批判的な眼差しを向けて、「愛は人を幸福にするのか、不幸にするのか」というテーマを深めていった。
●当時の女性は、基本的に横座りか、立て膝で座っていた。
●『源氏物語』に書かれているとおり、女房たちは、光源氏の召人(めしうど。主家の男性と男女関係にある者)になったり、光源氏に女君を紹介したりするキャリアウーマンだったが、一方で、女房はなかなか正妻にしてもらえないという社会構造があった。
●紫式部が『源氏物語』で書こうとしたのは、人の生きにくさ、女性に限らず、人間は皆生きにくいということだったろうと考えている。
