強力な助っ人、生成AIと一緒に読書しよう・・・【MRのための読書論(232)】
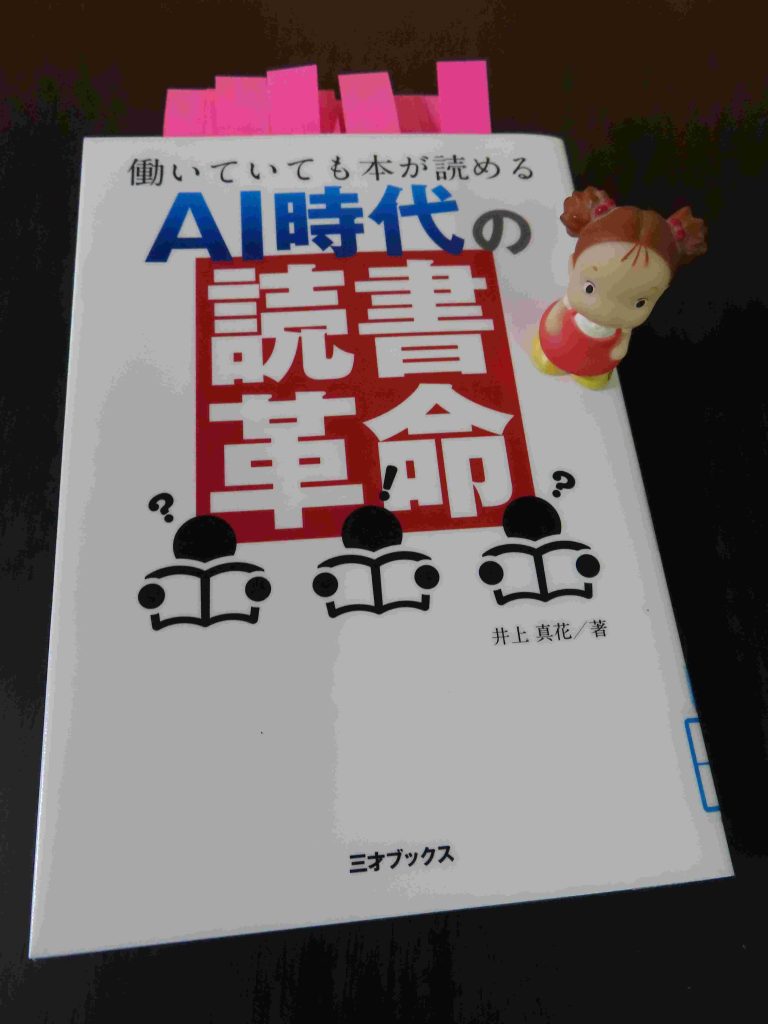
強力な助っ人
今や、AIを無視することは、刀で大砲に立ち向かうようなものである。『AI時代の「読書革命」――働いていても本が読める』(井上真花著、三才ブックス)の著者は、生成AIを活用することで、自分一人では理解できない難解な本が読めるようになると断言している。分からない箇所に出くわしたとき、AIは共に考え、理解へのヒントを提示してくれるので、あなたはより深い思考段階へ進むことができるというのだ。
読書前
分厚い本を読破するのは骨が折れる。そういうときは、本を読む前に、AI要約でその本の全体像を掴むとハードルが下がる。AIを使って要約を作成するには、適切な指示(プロンプト)を与える必要がある。例えば、「○○の要約を500字以内で作成してください。著者の主な主張、本の構造、重要な概念、結論を含めてください」というように。
代表的な生成AI
●ChatGPT(OpenAI)=難解な文学作品、科学書、哲学書など
●Claude(Anthropic)=学術的な本、複雑な文献など
●Gemini(Google)=文章、画像、音声、動画など
●MicrosoftCopilot(旧称:BingChat)(Microsoft)=急速に変化する分野の本、最新動向に関する本など
読書中
AIと対話しながら本の理解を深めることが可能となる。質問に当たっては、▶適切な背景情報を提供する、▶具体的かつ簡潔に表現する、▶問い掛けは一つに絞る――ことに留意する。
読書後
読書後にアウトプットすることで、理解が深化する。思考を整理し発信するには、読書ブログが最適だ。AIを適切に使えば、ブログ作成が容易になる。例えば、「以下の骨子をもとに、1000字程度の読書ブログ記事を作成してください(骨子の内容を貼り付ける)。▶読者を惹き付ける書き出しを考えてください。▶各パートが滑らかに繋がるように意識してください。▶読み易く、親しみ易い文体で書いてください」などと指示する。
AIを使って自分の記事を推敲することもできる。「この記事の文章を推敲してください」、「読者の心に響く表現になるようアドヴァイスしてください」などと依頼すればよい。
さらに、自分の記事をAIに評価してもらうのも面白い。例えば、「この記事の良かった点と改善点を挙げてください」などとAIに問いかけてみよう。
また、AIでブログのトップ画像を作ることも可能である。
戻る | 「MRのための読書論」一覧 | トップページ
