冬期も水を溜めておく「ふゆみずたんぼ」では、田んぼの土を豊かにするイトミミズが激増する・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3863)】
センニチコウ(学名:ゴンフレナ・グロボーサ。写真1)、アツバキミガヨラン(学名:ユッカ・グロリオサ。写真2、3)が咲いています。センニチコウの白く丸いのは、花を包み込んでいる苞です。ハゼラン(写真4)、ヘチマ(写真5、6)が花と実を付けています。ヘチマの花でホソヒラタアブ(写真6)が吸蜜しています。パプリカ(写真7)、ウンシュウミカン(写真8、9)が実を付けています。チュウゴクアミガサハゴロモ(写真10)、ミナミメダカ(写真11、12)をカメラに収めました。










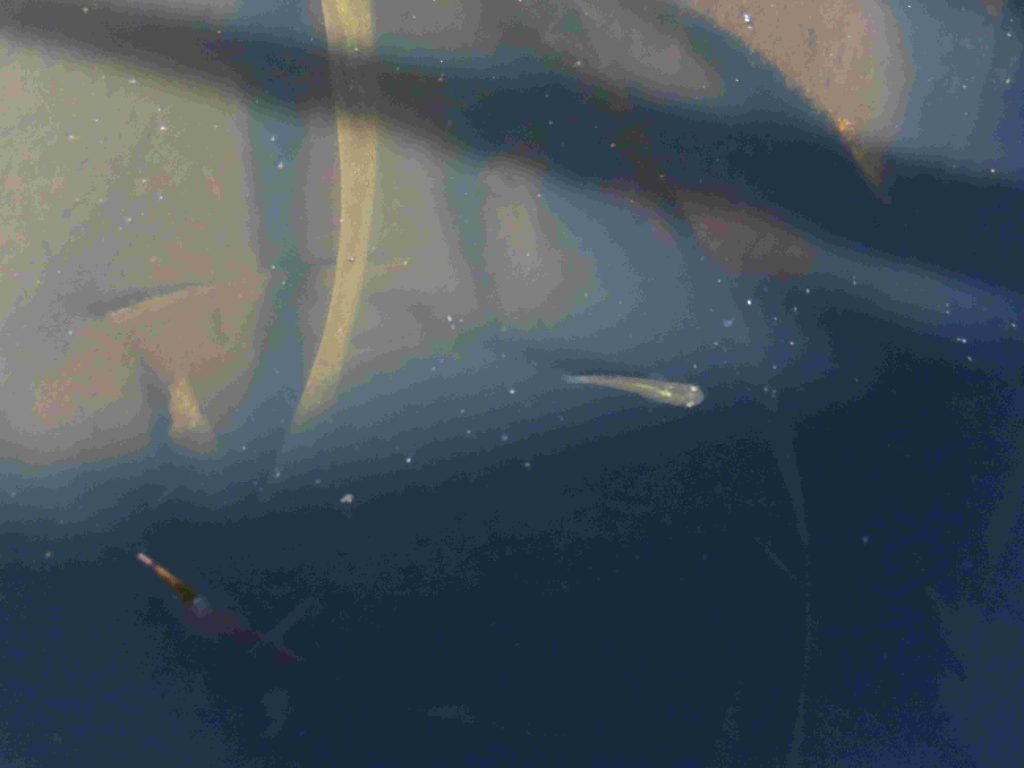

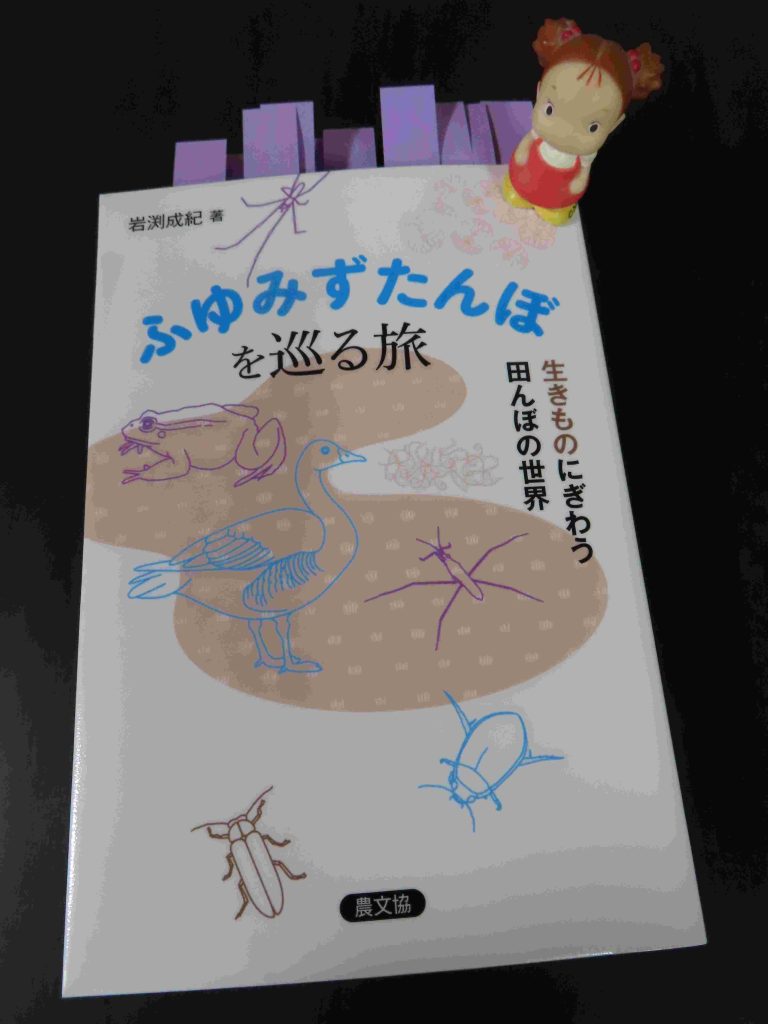
閑話休題、『ふゆみずたんぼを巡る旅――生きものにぎわう田んぼの世界』(岩渕成紀著、農山漁村文化協会)は、著者が日本各地の「ふゆみずたんぼ」(稲の収穫後から冬の間中、水を溜めておく冬期湛水水田)を訪れた記録です。
「『ふゆみずたんぼ』が多様化することで自由に拡散し、今もなお、発展し続けている。この特性が生物多様性向上、地力の向上、抑草効果などさまざまな効果へとつながる」。
●冬期に水を溜める目的は、急峻な棚田の崩壊を防ぎ、地力を培い、雑草を抑制し、春の田植え前の水不足を補うためだ。
●「ふゆみずたんぼ」では、冬の間に田んぼの土が熟成し、「トロトロ層」と呼ばれる粒子の細かいクリーム状の土の層ができる。さらに生物多様性の向上に想像以上の効果を与える。「ふゆみずたんぼ」には、おびただしい数のイトミミズが棲息している。春の田植えまでに「トロトロ層」が3cm以上できることで抑草効果が生まれる。「トロトロ層」さえできれば無施肥の稲作さえ可能である。
●最近の研究から、「トロトロ層」は田んぼの土を作っているイトミミズ類と、それと共生している細菌叢(マイクロバイオータ)などの田んぼの小さな生き物たちの総合体だということが分かってきた。イトミミズ類は一見小さくて、細く、頼りない生き物だが、彼らが作り出す土の世界は、田んぼに大きな影響を与える。
●鳥類のウイルス感染の予防にも「ふゆみずたんぼ」は効果を発揮する。湖沼に集中する水鳥の生活場所を、「ふゆみずたんぼ」を通して田んぼに分散させることで、鳥インフルエンザなどの爆発的流行(パンデミック)を防ぐことができる。
●冬でも水があることによる生物多様性向上の利点は大きい。山から流れ込むミネラル豊富な水や、落ち葉によってもたらされる肥料成分は計り知れない。湿った土は冬でも生物が十分棲息できる。山から流れ出た栄養分を自立型栄養供給システムで分解し、栄養塩類を補う。農地に棲息する生物の相互作用がより複雑化し、生物網が発展することで、病害虫や雑草の被害を減らす。すなわち、生物多様性向上効果が、農薬と肥料を使わなくとも育つ仕組みに繋がっているのだ。
●岩澤信夫の「耕さない農法」(不耕起稲作栽培)は、初期抑草の問題を抱えており、1990年代には、已むを得ず田植え前に除草剤を使っていた時期もあった。その後、「冬期湛水」を技術として採り入れ、春の初期雑草の抑草に成功した。これによって「不耕起+冬期湛水」と呼ばれる新たな農法が生まれた。農薬に頼らない「自然農法」の流れとしての不耕起稲作栽培が確立したのだ。
「『ふゆみずたんぼ』を発展させる篤志を持った百姓たちの物語は今も刻々と続き、つながっている」。
私事だが、「ふゆみずたんぼ」のおかげで、多数のハクチョウ類、カモ類を観察・撮影することができています。
