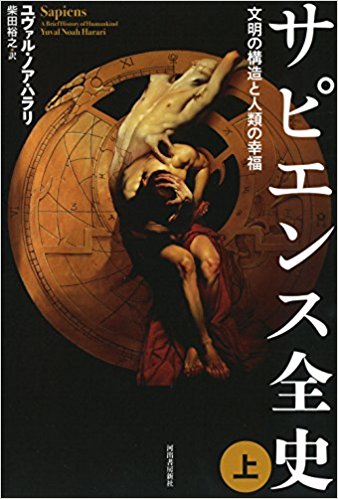妄想という名の想像力がホモ・サピエンスを進化させた・・・【情熱の本箱(166)】
妄想という名の想像力がホモ・サピエンスを進化させた、そして、そう遠くない将来、ホモ・サピエンスはホモ・サピエンスを超えた生命体に取って代わられるという、信じ難いというか、驚くべきというか、ユニーク極まる仮説が我々の眼前に出現した。
『サピエンス全史――文明の構造と人類の幸福』(ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳、河出書房新社、上・下巻)のユニーク性は、3つにまとめることができる。
驚くべき点の第1は、ホモ・サピエンスが他の人類に対し優位性を発揮できたのは、想像力のおかげだという主張。「多数の見知らぬ者どうしが協力し、柔軟に物事に対処する能力をサピエンス(著者は他の人類種と区別するために、現生人類であるホモ・サピエンスを『サピエンス』と呼んでいる)だけが身につけたからだ。・・・このサピエンスならではの能力を可能にしたのが、想像力だ。サピエンスだけが、約7万年前の『認知革命(新しい思考と意思疎通の方法の登場)』を経て、虚構、すなわち架空の事物について語れるようになった。客観的な現実の世界だけでなく、主観的な世界、それも大勢の人が共有する『共同主観的』な想像の世界にも暮らせるようになった。伝説や神話、神々、宗教を生み出し、それを共有する者なら誰もが柔軟に協働する能力を獲得した。虚構を作り変えればすぐに行動パターンや社会構造も変えられるので、サピエンスは遺伝子や進化の束縛を脱し、変化を加速させ、他の生物を凌げたのだ」。伝説や神話に止まらず、企業や法制度、国家や国民、さらには人権や平等や自由までもが虚構だという点に、この仮説の過激さが表れている。
認知革命は、ホモ・サピエンスに、具体的にはどういう果実をもたらしたのか。「それまでも、『気をつけろ! ライオンだ!』と言える動物や人類種は多くいた。だがホモ・サピエンスは認知革命のおかげで、『ライオンはわが部族の守護霊だ』と言う能力を獲得した。虚構、すなわち架空の事物について語るこの能力こそが、サピエンスの言語の特徴として異彩を放っている」。
「虚構のおかげで、私たちはたんに物事を想像するだけではなく、集団でそうできるようになった。聖書の天地創造の物語や、近代国家の国民主義の神話のような、共通の神話を私たちは紡ぎ出すことができる。そのような神話は、大勢で柔軟に協力するという空前の能力をサピエンスに与える。・・・サピエンスは、無数の赤の他人と著しく柔軟な形で協力できる。だからこそサピエンスが世界を支配」することができたというのである。
「ホモ・サピエンスはどうやってこの(意思疎通が可能な組織の規模の上限は150人という)重大な限界を乗り越え、何万もの住民から成る都市や、何億もの民を支配する帝国を最終的に築いたのだろう? その秘密はおそらく、虚構の登場にある。厖大な数の見知らぬ人どうしも、共通の神話を信じることによって、首尾良く協力できるのだ」。
「一対一で喧嘩をしたら、ネアンデルタール人はおそらくサピエンスを打ち負かしただろう。だが、何百人という規模の争いになったら、ネアンデルタール人にはまったく勝ち目がなかったはずだ。彼らはライオンの居場所についての情報は共有できたが、部族の精霊についての物語を語ったり、改訂したりすることは、おそらくできなかった。彼らは虚構を創作する能力を持たなかったので、大人数が効果的に協力できず、急速に変化していく問題に社会的行動を適応させることもできなかった」。個人のレヴェルを超えて、本来の150人というコミュニケーションの限界を超えた集団内で想像力を共有すること、すなわち、コミュニケーションの水平面での拡大がホモ・サピエンスに勝利をもたらしたのである。
「サピエンスは認知革命以降、自らの振る舞いを素早く変えられるようになり、遺伝子や環境の変化をまったく必要とせずに、新しい行動を後の世代へと伝えていった」。さらに、次世代へ想像力を受け渡すこと、すなわち、コミュニケーションの垂直面での継続もホモ・サピエンスが優位に立つことに貢献したのである。
驚くべき点の第2は、認知革命に続く農業革命と科学革命が、さらにホモ・サピエンスの進化を推し進めたという主張。「サピエンスの歴史は、約1万年前に始まった『農業革命』で新たな局面を迎える。農耕によって単位面積当たりに暮らせる人の数が爆発的に増加し、かつて狩猟採集をしながら小集団で暮らしていたサピエンスは定住し、統合への道を歩み始める。やがてその動きを速める原動力となったのが、貨幣と帝国と宗教(イデオロギー)という3つの普遍的秩序だった」。特に、これまで考案されたもののうちで最も普遍的、最も効率的な相互信頼の制度は貨幣だと強調している。
「やがてサピエンスは、人類の運命だけではなく、おそらく地上のあらゆる生命の運命をも変えることになる革命を起こした。約500年前に始まった『科学革命』だ。サピエンスが空前の力を獲得し始めるきっかけが、自らの無知を認めることだったというのだから面白い。それまでは、知るべきことはすべて神や賢者によって知られているという考え方が主流で、ほとんどの文化は進歩というものを信じていなかった。一方、科学は自らの無知を前提に、貪欲に知識を求めていった。知識の追求には費用がかかる。したがって、科学がどの道を進むかは、イデオロギーと政治と経済の力に影響される。そのうちでも、とくに注意を向けるべきなのが、帝国主義と資本主義で、科学と帝国と資本の間のフィードバック・ループが、過去500年にわたって歴史を動かす最大のエンジンだった」。この科学と帝国と資本の間の相互依存関係の分析は、有無を言わせぬ説得力がある。
過去の地球に数多く登場した人類の中で、ホモ・サピエンスだけが繁栄できたのはなぜか。認知革命、農業革命、科学革命という3つの革命の賜物だという著者の思考プロセスは、この謎を論理的かつ明快に解き明かしている。
著者は、ホモ・サピエンスの歴史はプラス面だけではないと指摘する。多くの動植物種を絶滅に追い込んだ、そして、家畜化された動物の幸福を奪っているというのだ。さらに、ホモ・サピエンスという生物種としては大成功だとしても、その個々人の幸福が増したとは決して言えないというのである。幸福度という尺度を歴史の考察に持ち込んだ点、しかも、その対象を人類だけでなく、他の生物にまで拡大している点が、類書との違いを際立たせる本書の特徴となっている。文明は人間を幸福にしたのか、と我々に問いかけているのだ。
驚くべき点の第3は、ホモ・サピエンスの未来は、このようになるという予測。「核の大惨事、あるいは生態学的な大惨事といった番狂わせがなければ、テクノロジーがこのまま発展を続け、ホモ・サピエンスは異なる体形だけでなく非常に異なる認知的世界や情緒的世界も持った、まったく異質の存在に取って代わられるだろう」。管見の限り、SF作品ならともかく、歴史書でありながら、これほどのページ数を割いて、大胆に未来を描出している例を他に知らない。
著者の言葉を借用させてもらうと、我々に「第二次認知革命」を迫る著作と言えるだろう。これほど知的好奇心を激しく掻き立てられたのは、本当に久しぶりのことである。