平安時代の貧しくなってしまった妻の離婚話に慄然としました・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3200)】
アトリの雌(写真1~6)、カワラヒワ(写真7)、シメ(写真8、9)、ツグミ(写真10、11)をカメラに収めました。












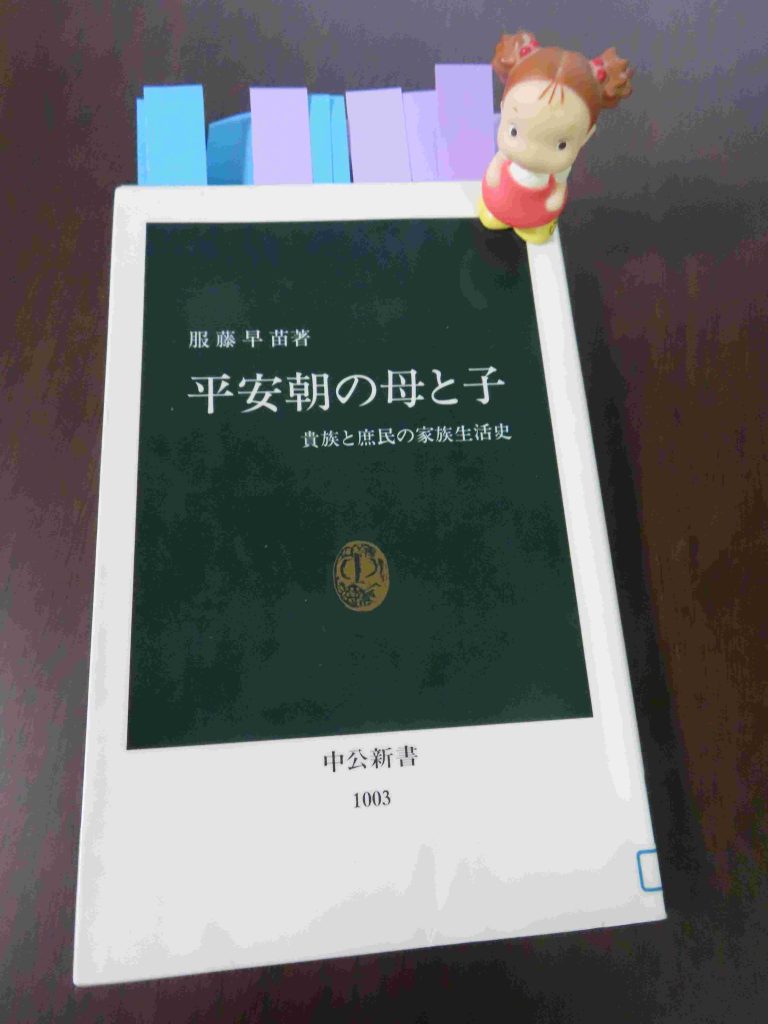
閑話休題、『平安朝の母と子――貴族と庶民の家族生活史』(服藤早苗著、中公新書)で、個人的に、とりわけ興味深いのは、●妻たちの嘆き、●貧しい妻の離婚、●平安時代の婚姻形態――の3つです。
●妻たちの嘆き
「(藤原)道長の正妻倫子も、多くの妾たちのうち、紫式部には、強い嫉妬を覚えていた、と萩谷朴氏は述べている。その理由として、紫式部の身分が低いこと、45歳の自分にたいし35歳ぐらいの式部の年齢がさほど自分と差がないこと、作家としての式部の教養に太刀打ちできなかったこと、などをあげておられる。『栄華物語』などにも、貴族女性が、嫉妬心を相手の男性にぶつけている場面が、結構多い。古代の不安定な対偶婚を脱し、常に同居し生活を共有したいと願っていた女性たちを迎えたのは、上層貴族においては、このような男性にのみ自由な性関係の社会であった。そういう意味では、なかなか所帯が持てないけれど、持てた時は、派手な夫婦喧嘩をしながらも、一緒に働き、一緒に物を造りだし、豊作の喜びを分かち合える、庶民層の女性たちのほうが、人間的にみると健全で幸福だったはずである」。貴族層だけでなく庶民層にまで目が行き届いているのが、本書の特徴の一つになっています。
●貧しい妻の離婚
「王朝時代は、『婿取り』婚、すなわち妻方居住から開始される婚姻であったから、結婚当初は妻の両親が生活の世話をした。ところが妻の両親が死亡すると、財産がなくなり生活に事欠くようになる。『今昔物語』で、女性の方から申し出る離婚話は、こんな時にしかたなく妻の方から申し出る離婚である。中務太輔に娘が一人いた。兵衛佐を婿にとっていたが、打ち続き両親をなくしたので財産がなくなり妻は、夫に離婚を申し出る。親がいた時は、あなたが宮仕えをするための衣服の調達などできましたが、今はできません。いくらなんでも見苦しいので、どうぞお気の済むようになさって下さい。裕福な妻を見つけて下さい、と申し出る。夫は去り難かったけれども、妻が強く勧めるので『男遂に去りにけり』。結局男は他に金持ち妻を儲け、出世して国守になったが、旧妻は郡司の下女になり、前夫の夜伽に出される。かつての妻だと知った国守は、そのことを問いただす。わかっていても黙っていてくれればいいのに聞いてしまった。風情を知らない旧夫の前で、女は恥じてその場で死んでしまった。夫に去られた妻は、結局身を売るがごとく郡司の下女になり、客への性的サービスを強要されるのである。逆に夫は、裕福な女性を見つけ、婿入りし、妻の両親の援助のおかげで、国守にも出世できる」。何とも遣るせない話に慄然としました。
●平安時代の婚姻形態
「平安時代の婚姻形態は『婿取り婚』であったこと、離婚・再婚が頻繁に行われたこと、女性の性も今よりは自由であった」。
