同一種でありながら、負け組のサクラマスが勝ち組のヤマメの2倍以上の大きさになれるのはなぜか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3740)】
【読書の森 2025年6月21日号】
情熱的読書人間のないしょ話(3740)
ツミの雌(写真1~3)、チョウゲンボウの雄(写真4~7)、雌(写真8~10)、幼鳥(写真11~13)、幼鳥に近づいてきたトビを警戒して旋回するチョウゲンボウの雌(写真14)をカメラに収めました。














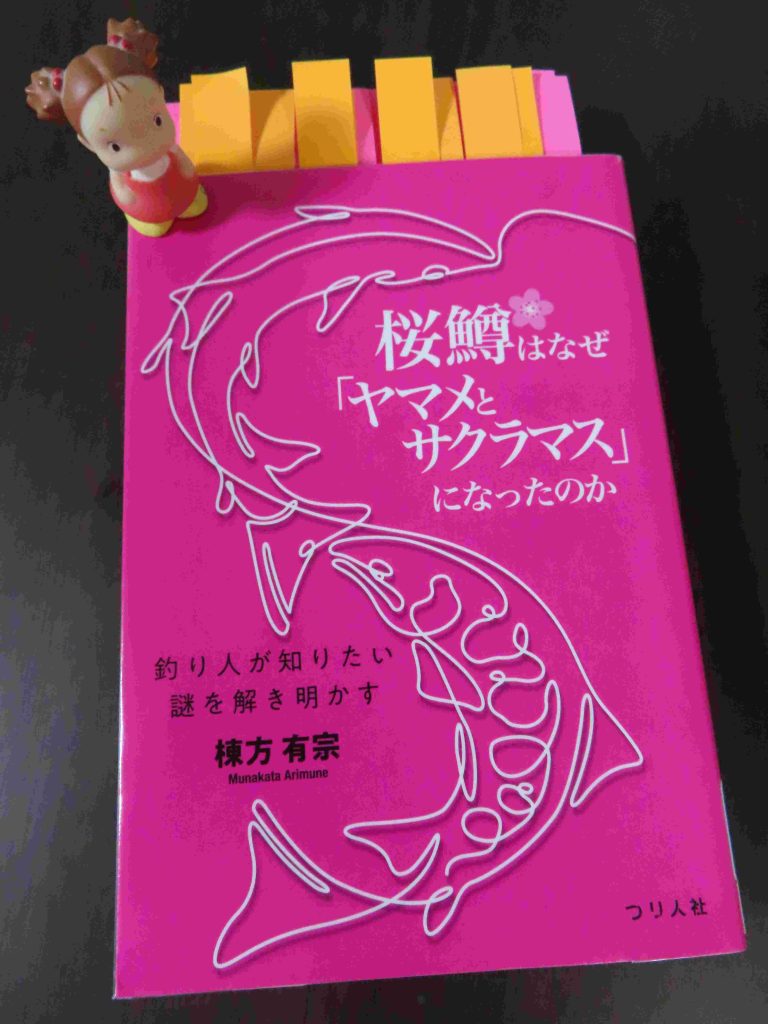
閑話休題、同一種でありながら、川で育つヤマメは小さいのに、川から追い出され海で育つサクラマスはなぜ体が大きいのか、予て疑問に思ってきたが、今回、手にした『桜鱒はなぜ「ヤマメとサクラマス」になったのか――釣り人が知りたい謎を解き明かす』(棟方有宗著、つり人社)が、明快な解答を与えてくれました。
●川→海→川と回遊するサクラマスと、海に降りずに川に残留するヤマメは同一種である。なお、栃木県中禅寺湖に生息するホンマスは亜種ではなく、人によって作り出されたサクラマスの地域個体群である。
●川で生まれ、餌を巡る縄張り争いで優位となったサクラマスの稚魚は河川残留型(ヤマメ)となり、そのまま産卵場付近での生活を続ける。一方。争いに敗れて劣位となった稚魚は銀化変態を起こし、川から海へと降海回遊を発現する(サクラマス)。
●海は餌が豊富なので、降海型のサクラマスは河川残留型の2倍以上まで体を大きくすることができる。
●海は川より餌が豊富だが、その半面、外敵(捕食者)に捕食されるリスクが川より高いことから、過酷な環境だと言える。
サクラマス群(ビワマス<この河川残留型はアメゴ>、サツキマス<この河川残留型はアマゴ>、サクラマス<この河川残留型はヤマメ>、サラマオマス)がどのようにして川から海への回遊行動を進化させてきたのかについても、明快に解説されています。
サクラマスの生息環境を安定させる試みについても言及されています。
どの解説もエヴィデンスに基づいているため、説得力十分です。
