豊臣秀吉の実弟・豊臣秀長とは、どのような人物だったのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3814)】
綿毛のようなものがノコノコ歩き出したではありませんか。アオバハゴロモの幼虫たちです。







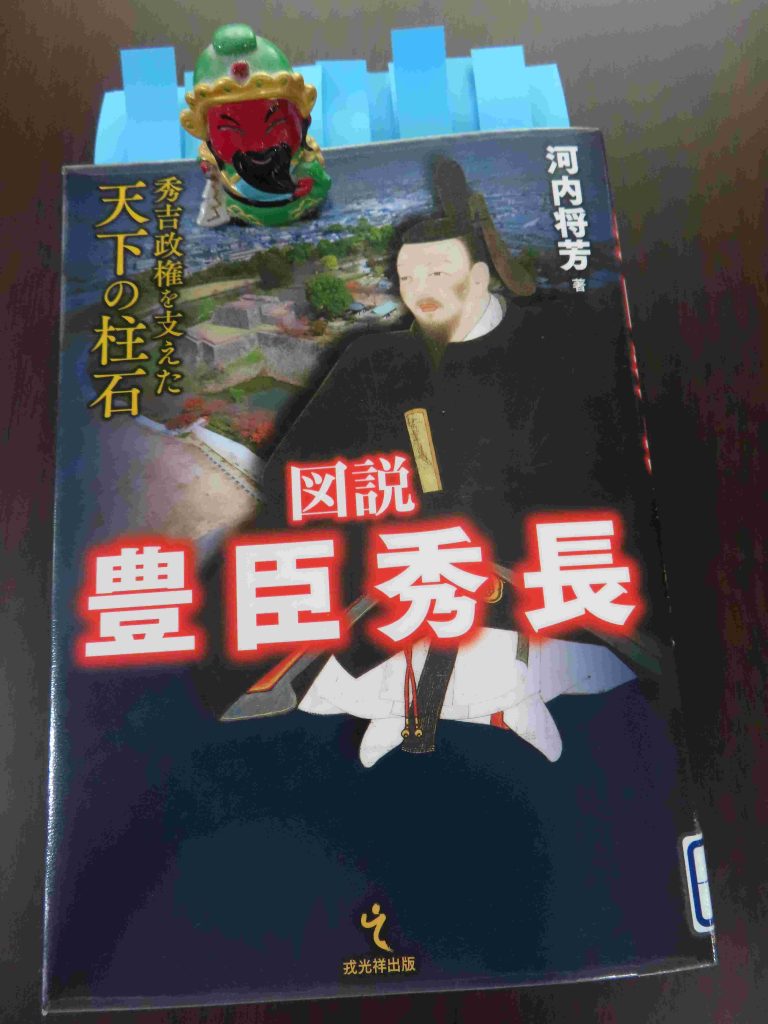
閑話休題、『図説 豊臣秀長――秀吉政権を支えた天下の柱石』(河内将芳著、戎光祥出版)は、驚くほど史料に忠実な実証的な一冊です。豊臣秀長について、これほど実証的な著作は、管見の限り初めてです。
これまで抱いてきた秀長のイメージとは異なる姿も浮かび上がってきました。
●1541年、秀長誕生。秀長の母は、兄・豊臣秀吉と同じ大政所であるが、父も同じかは史料では分からない。
●1577年、秀長は、太田垣氏の城であった竹田城を居城に但馬支配を進めた。竹田城に入ると、秀長は石垣の改修等を行った。現在の竹田城は雲海に浮かぶ天空の城として知られている。
●1584年、小牧・長久手合戦の戦場で秀長と名乗り始めた(それまでは長秀)。
●1585年、秀長は大和を拝領し、支配拠点として郡山城を整備した。やがて、紀伊全体が秀長の支配下に入るが、時には武力にものを言わせて支配を貫徹する武人としての側面も備えていた。大和、紀伊、和泉3カ国を領する大大名となったわけである。
●1585年、参議に任官し公卿に昇進、豊臣秀長となった。
●1586年、秀長は大友宗麟から援軍の要請を受けた。その時、宗麟に「自分はこのような人間なので、なにとぞご安心ください。秀吉家中では、内向きのことについては利休が、また表向きのことについては秀長がうけたまわっています」と語ったことが知られている。
●1587年、秀長は大納言に任官された。豊臣政権の重鎮、「大和大納言」の誕生である。
●1589年、秀吉の息子・鶴松誕生により、秀吉と秀長との間に隙間風が吹き始める。
●1589年以降、秀長の病が重くなる。
●1591年、秀長、50歳にて死去。豊臣政権の落日が始まる。
個人的に一番驚いたのは、秀吉や秀長が「奈良借(ならかし)」という、奈良の町人たちに対する強制的な高利貸しで財を成していたという指摘です。秀長死去時、「限りなき財宝」が蓄えられていたことが史料に記されています。
豊臣秀吉、豊臣秀長は、「とよとみひでよし」、「とよとみひでなが」と表記されることが多いが、「源平藤橘」同様、「とよとみのひでよし」、「とよとみのひでなが」と表記すべきと、私は考えています。
