楽しみは人生の下り坂にあり・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3825)】
タマスダレが咲いています。



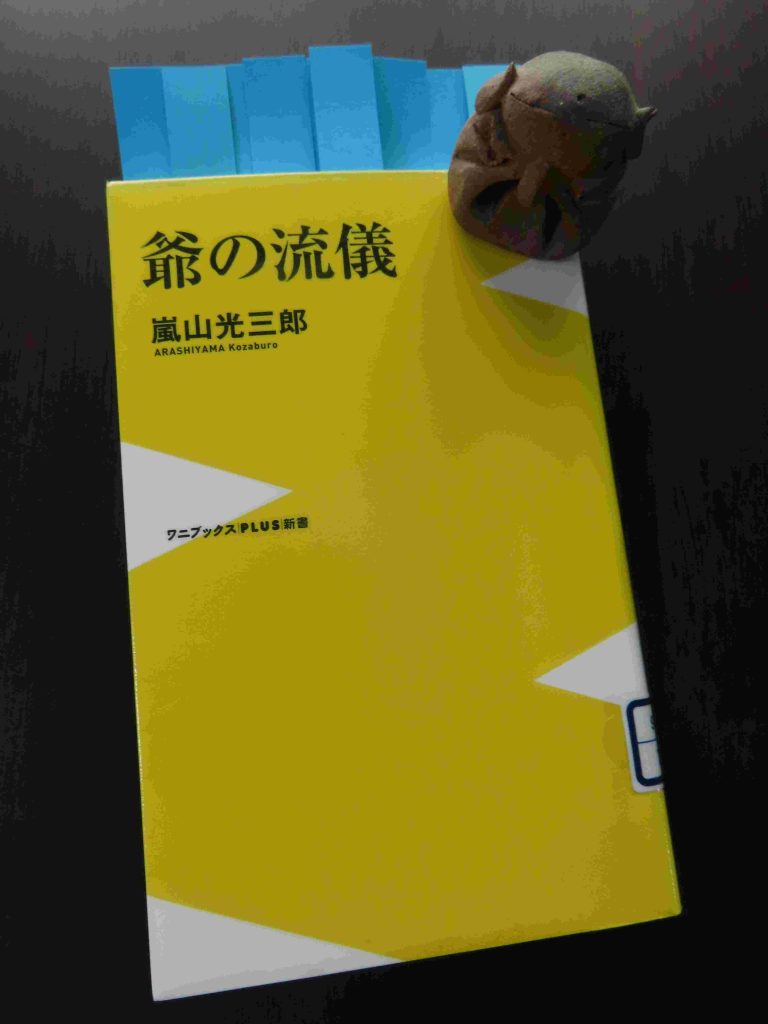
閑話休題、私は嵐山光三郎の著作や生き方が好きで、めぼしいものはほとんど読んできたが、『爺の流儀』(嵐山光三郎著、ワニブックス[PLUS]新書)も嵐山らしさが横溢しています。
●窮地を脱すると頭がリニューアルされ、暗闇にひそむ魔物を飼いならして、いっそう不埒な海を泳ぐ覚悟ができた。こうなれば、自分なりの流儀で生きていくしかないのだと気がついたのです。
●老いの流儀十カ条
①老人の獣道をゆく(もともとの路線)
②ゲーム感覚の人生(行きあたりばったり)
③消耗品としての体(ケガしないように)
④弁解せず(面倒だ)
⑤放浪の夢(廃墟願望)
⑥議論せず(時間の無駄)
⑦時の流れに身をゆだねて(チャランポラン)
⑧いらだって生きる(悟らない)
⑨孤立を恐れず(自分本位の意地)
⑩スキのある服装(ヨレヨレ)
●しのぐとは困難な状況と闘って、それをのりこえる意志。耐え忍び、我慢することである。雨露をしのぐ。飢えをしのぐ。貧乏をしのぐ。不運をしのぐ。
●人生で連勝しているときが一番危ない。連勝したぶんのツケがまわってくる。そんなに極端でなくても、幸運のあとには不運がくる。八十歳をすぎれば、幸運と不運はチャラになる(ようにできている)。
●強い人は、トータルで平均的に勝つ。全勝できないが全敗もしない。人に見えている部分は氷山の一角で、氷山の下が課題になってくる。政財界のスキャンダルで失敗する人は、水面下に潜む化け物が暴かれる。生き残る人はえたいが知れない魔物を飼いならす術を持っていて、魔物が反乱しないように手なずける。それが辛抱である。ふだんから致命的な不運にならないように、平凡な負け星がつづいているあたりがいい。油断してダラダラ過ごしている人は運とは縁がない。幸運は呼びこむものではなく、流れを見さだめて、運気と合体してつかむ。運が悪いときはしのぐしかない。勝ちでも負けでもない「しのぐ時間」が重要である。
●八十歳を過ぎたら、のんべんだらりと一日を過ごして、冗談言って生きるのが老人の特権ですが、体力の低下、衰弱を妖術として使い、進歩という幻想から身をひきつつ、シルバー任侠道を生きましょう。
●だれもが自分の死を体験することはできない。死は意識もろとも肉体が終焉することだから、死んでしまえば、自分の死を知ることができない。死はいっさいを無にし、せっかくの体験すら消滅してしまう。
●老人のライセンスだ。人をはかるモノサシが有りや無しやと問われれば重要なことは「面白さ」である。偉い、立派、品格、有名・・・なども無視できぬが、「面白さ」が一番大切だ。
●いま、町にあふれるジジイ指南書は、そのほとんどが上昇志向である。なんらかの形で上昇し、難しい坂を登りきろうという発想で下降志向のものがない。下り坂がこんなに楽しいのになぜなのだろうか、と考えた。人間は、年をとると、「まだまだこれから」だとか「第二の人生」だとか、「若いモンには負けない」という気になりだし、こういった発想そのものが老化現象であるのに、それに気がつかない。年をとったら、ヨロヨロと下り坂を楽しめばいい。落ちめの快感は、成り上りの快感に勝る。
嵐山先輩が言うように、私の発想そのものが老化現象なのかなあ。
