『<種の起源>を読んだふりができる本』を読んだふりができる書評・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3884)】
早朝、2階のヴェランダに洗濯物を干しにいった撮影助手(女房)が駆け降りてきて、肩を怒らせているカメムシがいるわよ。おかげで、ミナミトゲヘリカメムシ(写真1)を撮影することができました。バン(写真2)、バンの若鳥たち(写真3、4)、カイツブリ(写真5、6)、ダイサギとヒドリガモとカルガモ(写真7、8)、ヒドリガモの雄と雌(写真9、一番左が雄)をカメラに収めました。キク(写真10)が咲き始めています。ナワシログミ(写真11)が咲いています。トキワサンザシ(写真12)が実を付けています。因みに、本日の歩数は9,704でした。












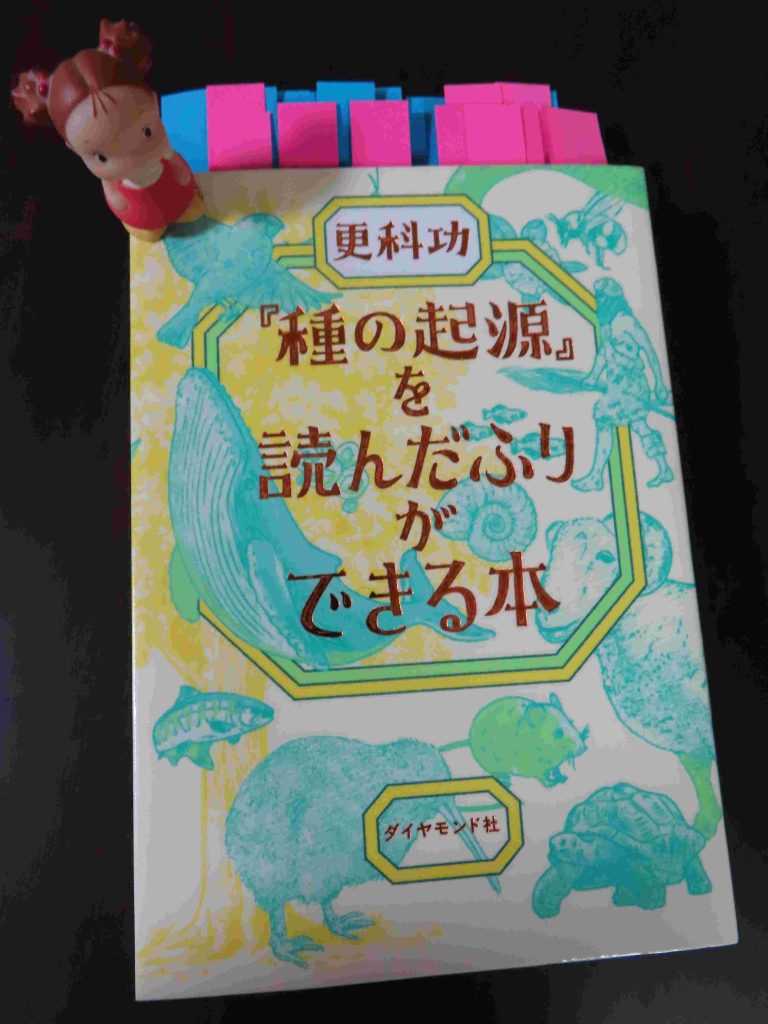
閑話休題、『<種の起源>を読んだふりができる本』(更科功著、ダイヤモンド社)では、信頼できる進化論の専門家・更科功が、読み通すことが難しいとされるチャールズ・ダーウィンの『種の起源』のポイントについて、現在の進化論の知見と比較しながら、分かり易く解説してくれています。
本書には、思いもかけない意外なことがたくさん記されています。
●『種の起源』でダーウィンが言いたかったのは、自然淘汰によって種分化を起こしながら生物の多様性を生み出していく進化、すなわち、生物は、自然淘汰によって進化し、ただ一種の共通祖先から分岐することによって、現在のような多様で豊かな生物の世界を作り上げてきた――ということである。
●ダーウィンが生きた19世紀のイギリスでは、多くの人々が「神がすべての生物を創った」(個別創造説)と考えていた。『種の起源』は個別創造説をノックアウトするために書かれた。
●若いころのダーウィンは敬虔なキリスト教の信者であったが、晩年にはキリスト教への信仰を捨ててしまった。『種の起源』は、その中間の時期に書かれた書物である。従って、『種の起源』は神学書の体裁を採用している。
●厖大な証拠を挙げて。自然淘汰と進化を切っても切れないほどに結び付け、広範で精緻な観察によって自然淘汰の力の凄まじさを認識した人は、明らかにダーウィンが初めてだった。ダーウィンとほぼ同時に、進化の仕組みとして自然淘汰を発見したアルフレッド・ラッセル・ウォレスにしても、この2点においてはダーウィンの足元にも及ばない。自然淘汰や進化に対する洞察の広さと精密さに関しては、はるかにダーウィンに及ばないことをウォレス自身も認めていたからこそ、ウォレスは生涯にわたってダーウィンを尊敬し続けたのだろう。
●ダーウィンの自然淘汰説とウォレスの自然淘汰説は少し違っている。ダーウィンの説は「個体間の闘争によって種が進化する」というものだが、ウォレスの説は「種間あるいは変種間の闘争によって種が進化する」というものである。
●ダーウィンは、進化を進歩とは見なしていなかった。
●『種の起源』は進化論の方向性を決定づけた画期的な素晴らしい本であるが、現在の進化学に照らせば、間違っているところもたくさんある。
●ダーウィンが間違っている最大の原因は、ダーウィンがグレゴール・ヨハン・メンデルが解明した遺伝の法則を知らなかったこと、変異が生じる原因が突然変異であることを知らなかったことにある。
●ダーウィンが考えた獲得形質の遺伝は、現在ではほぼ否定されている。ただし、生活条件の直接作用が、ごくまれに遺伝することは確認されている。これはDNAの塩基配列以外の変化(たとえばDNAのメチル化)によって遺伝するもので、エピジェネティクスと呼ばれている。
●ダーウィンは『種の起源』の中で、性淘汰を自然淘汰の一部だと言ったり、性淘汰を自然淘汰とは別のものとして区別したりするのでわかりにくい。ただし、厳密に自然淘汰と性淘汰を区別することはできないので、性淘汰は自然淘汰の一部と考えた方がよいだろう、
●現在では、進化の仕組みには、自然淘汰の他に遺伝的浮動もあることが知られている。遺伝的浮動というのは、偶然の作用によって進化の道筋が変わることである。そのおもな原因は、親が持っている2つの対立遺伝子のうちのどちらが子に伝わるかが、偶然によることだ。現在の進化学では、進化の仕組みは4つとされている。自然淘汰と遺伝的浮動と遺伝子交流(交雑はここに入る)と突然変異(変異の生じやすさや変異の蓄積はここに入る)だ。
【追記】この書評では、どうも、よく分からんという人は、『<種の起源>を読んだふりができる本』を読んでください。
