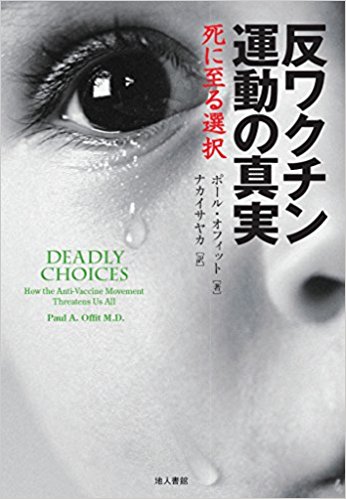反ワクチン運動が子供たちにもたらしたのは、予防可能な病による苦しみと死だ・・・【薬剤師のための読書論(28)】
『反ワクチン運動の真実――死に至る選択』(ポール・オフィット著、ナカイサヤカ訳、地人書館)では、米国と英国における反ワクチン運動の過去と現在が生々しく剔抉されている。
「今も戦争が続いている――静かな、命に関わる戦争が。戦線の一方には親たち。彼らや彼女たちは毎週のようにワクチンが危険だという話で空爆されている。・・・さらに親たちはワクチンが慢性病の原因なのだとも聞かされている。しかもそう告げるのは誰もが信頼を寄せる人々だ。・・・だが何より自分と同じような子育て中の親が『予防注射をするまでは全く元気だったのに、あっというまに具合が悪くなってしまった』と語る言葉にはつい耳を傾けてしまう。ワクチンを避ける親が出てくるのも無理はない。・・・戦線のもう一方には医師たちがいる。ワクチンを打っていない子どもたちでいっぱいの待合室が恐ろしい場所に変わってきていることを憂いた結果、毅然とした態度を取る医者が増えている」。
「対立の真ん中で動きが取れなくなっているのは子どもたちだ。免疫がないまま取り残された子どもたちを苦しめているのは祖父母の時代の病。最近の麻疹、おたふく風邪、百日咳、細菌性髄膜炎の流行では何百人もがそういうワクチンで予防できる病気にかかり、中には死亡した子どももいた。親が病気よりもワクチンを恐れたため死んでしまったのだ」。
「混乱の最中、別のグループも現れた。ワクチンを打たない子どもたちが自分たちの子どもを危険に曝していることに怒っている親たちだ。この中にはワクチンを打つことができない子どもの親もいる。小児がんの抗がん剤治療で免疫が低下した子どもや臓器移植のために免疫抑制剤を使っている子ども、喘息の治療にステロイドを使っている子どもたちは特に病気に弱い。こうした子どもたちは周囲の人々がワクチンで免疫を持っているのが頼りだ。そうでなければ病気が流行したときに真っ先に苦しむのはこの子たちなのだ」。
米国は、現在、岐路に立っているという。「過去20年、予防接種免除を認める州が増加するにつれ、集団免疫はがたがたになってしまった。解決は難しくなってきている。各州は今後も親にワクチン免除を認めるべきか? あるいは思い切って免除の権利を抹消すべきか?」。ワクチンへの恐怖、その恐怖に基づいた選択、その選択の結果がもたらしていること、そして、それに対する抗議の声が、本書のテーマとなっている。
日本語版への前書きで、著者が重要なことを語っている。「2013年、日本の厚生労働省は思春期の少女に対するヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの積極的な定期接種勧奨を差し控えました。推奨の差し控えは、HPVワクチンが慢性的な痛みと慢性疲労症候群、POTS(起立性頻脈症候群)という身体を起こしたときに起こる心拍数の増加と血圧の低下を特徴とする心身の不調を引き起こすのではないかという恐怖に基づいています。日本のメディアはこうした心身の不調に苦しむ子どもたちについて、ワクチンとの関係が因果ではなく偶然である可能性には触れずに報道しました。HPVワクチンはHPV感染症を防ぐために作られています。思春期に起こりがちな他のことを防ぐようには作られていないのです」。
「HPVワクチンは認可後に100万人以上を対象にして公式に調査が行われています。認可前には3万人を対象に7年間に亘って調査研究されました。その結果では、主張されているような病気は起こっていません」。
「HPVは子宮頸がん、頭部、頸部、肛門、性器のがんの共通する唯一の原因です。ワクチンはこうしたがんの85%を防ぎます。毎年約1万人の日本の女性が子宮頸がんにかかり、約3000人が子宮頸がんで死亡しています。HPVワクチンは現在接種可能ですが、厚生労働省の推奨差し控えで、利用は限定されたものとなっています。現在ワクチンを打っているのは思春期の少女たちの1%以下。日本の厚生労働省がHPVワクチンは慢性病の原因とは考えられないとする研究の存在を知らしめることを怠ったために、何千人という少女たちを予防可能な病気で苦しみ死亡する運命に導きました」。日本の厚生労働省の不決断と不作為が厳しく弾劾されているのだ。