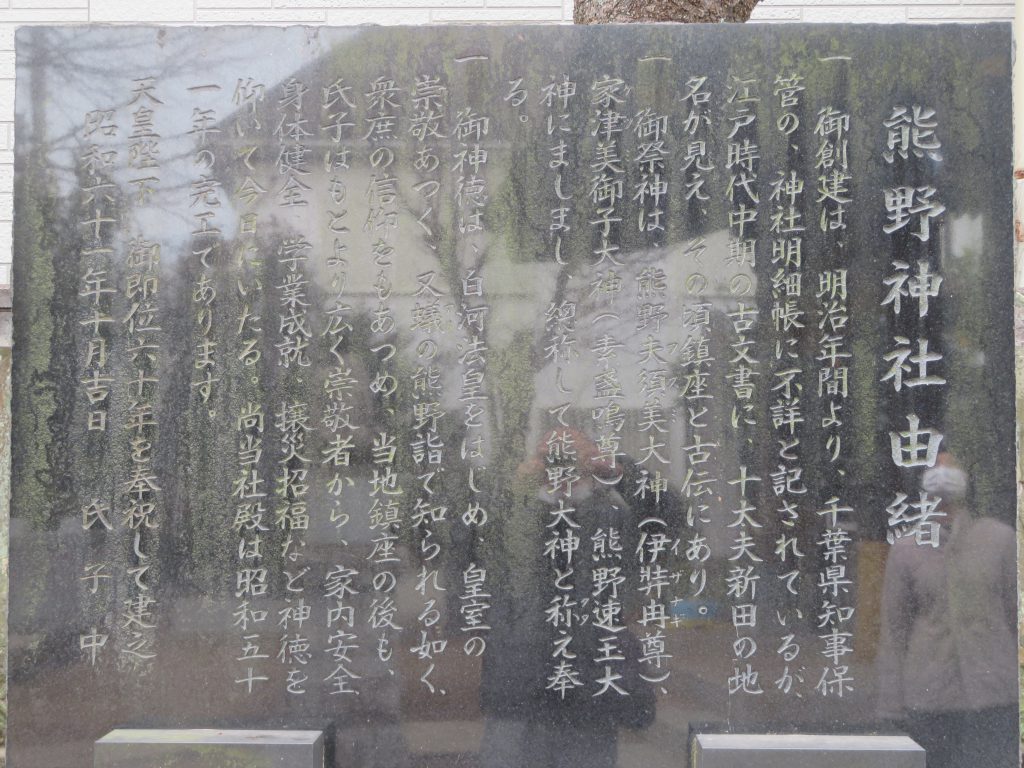今から500年も前に、キーワードで検索可能な図書館という夢に挑んだ、コロンブスの息子・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2093)】
あちこちで、ロウバイ(写真1~3)、園芸種のソシンロウバイ(写真4~12)の蝋細工のような花が芳香を漂わせています。
閑話休題、偉大な航海者、クリストファー・コロンブスの名は知っていたが、その息子、エルナンド・コロンのことは、『コロンブスの図書館』(エドワード・ウィルソン=リー著、五十嵐加奈子訳、柏書房)を読むまで知りませんでした。
本書は、クリストファー・コロンブスの愛人の子で、次男のエルナンド・コロンの評伝です。クリストファー・コロンブスは本来、クリストバル・コロンと表記されるべきだが、本書では、敢えて、日本人に馴染深いクリストファー・コロンブスが採用されています。
エルナンドの生涯で特記されるべきことが、3つあります。
第1は、エルナンドが13歳の時、父の第4回航海に同行して、貴重な経験をしたこと。
「いやになるほどゆっくりと海岸沿いを航行するあいだに父子を襲った熱病によって、エルナンドはよりいっそう父親を身近に感じるようになった。コロンブスはのちに、まだ13歳の息子が苦しむのを見て胸が痛み、ぐったりした姿に気持ちが落ち込んだと書いている。だが、甲板にしつらえたベッドに横たわって息子の姿を見ているうちに、その気持ちはやがて、わが子を誇らしく思う果てしない親心へと変わっていった。エルナンドは病気にもかかわらず一所懸命に働き、それが他の男たちを元気づけ、さらに父が楽になるようにとつねに気を配っていた。お前はまるでその道80年の船乗りのようだと、コロンブスは息子に向かって言った。これは、コロンブスがいままで自分だけにそなわっていると思っていた航海者としてのある種直感的な才能を息子にも認めたということで、父親ゆずりのその資質を、エルナンドは自己像のいちばん重要なものとして生涯大切にしたのだった」。
第2は、崇拝する父の伝記『コロンブス提督記』を著したこと。後代の私たちがコロンブスについて、いろいろ知ることができるのは、この著作に拠るところが大きいのです。
「『コロンブス提督伝』のなかで彼はくり返し、コロンブスがほかの人々にはできなかったことを成し遂げたのは、並外れた修練と忍耐力、自制心のたまものであることを示唆している。それゆえにコロンブスは、大洋で数々の兆候に出会っても、水夫たちのように陸地が近いと早とちりなどせずゆったりと構え、西へ行けば必ず陸地があると確信するに至った3つの論理に意識を集中させることができたのである。その3つとは、根拠、古代の著述家たちの権威、そして大西洋を渡った他の船乗りたちの報告である。エルナンドは、父のこの思慮分別の証拠は彼が欠かすことなくつけつづけた航海日誌にあると考えた。その綿密な日誌は、時間をかけた丹念な計測と記録、観察の集積が新世界発見へつながったことを示している。エルナンドは伝奇のなかで対立役――コロンブスとは対照的なやり口のライバル――まで登場させている」。
第3は、誰も考えたことのないような個人図書館構築を目指したこと。エルナンドが構想した図書館は、幅広く世界中の書物を集めて収蔵するというレヴェルを超えて、キーワードで検索可能な図書館という現代のIT時代の先駆けともいうべき先進的なものであったこと。
「40年前、父が新世界を発見し、謀反と忘恩に打ち勝って生きのび、身の証を立てた――そのころの感覚が、襲いかかるさまざまな中傷や風説によって脆くも崩れ去り、彼の父親が神話と伝説の世界から苦労して掘り起こして日の目を見せた土地が、ゆっくりとまた元の霧のなかへ姿を消そうとしていた。古代史や、迷路のごとく入り組んだ法体系から、古代貨幣の使用や歴史を知るための銘刻にいたるまで、エルナンドが一生涯を費やして学んできたものすべてが、いまや彼に背を向けつつあった。大切に思ってきたものがすべて消滅したいま、エルナンドは残された唯一の武器(彼の図書館と、そこに所蔵された、コロンブスが彼に残した記録文書)に目を向けた。指のあいだからすりぬけていきそうな父を、しっかりとその手にとどめるために――」。
「言語やテーマ、宗教に縛られない図書館というエルナンドの発想は、ヨーロッパにおける知識の概念を根本から変えるものである」。
「本棚は、必要に迫られて考案されたものだ。従来のコレクションならばせいぜい数百ないし数千冊の蔵書で、テーブルに積み上げるか収納箱に入れておいても、記憶力のいい司書ならば難なく見つけ出せただろう。だが、エルナンドの図書館ほどの規模になると、いくらすぐれていても人間の記憶力ではとうてい追いつかず、また、部屋という部屋が本であふれかえってしまっただろう。その点、新型の本棚は場所をとらず、本の重みを後ろの壁にゆだねることができた。棚は整然と並び、付されたナンバーを左から右へ一連のテクストのように読み取ることができ、さらには、本を立てて収納するので、水平に積み上げるのとは違って一冊ずつ取り出しやすく、下の本を取るさいに上の本が崩れそうになることもなかっただろう」。
「エルナンドがいかにすごいものをつくりあげたのか、それを真に実感するのは難しい。当時の、あるいはそれに続く時代の図書館の多くは、創設者の蔵書保管箱に毛が生えたようなものだった。そんな時代にあって、エルナンドは世界中の情報をグアダルキビル川のほとりに集約させるシステムを構築し、そうして集めた本を有効利用するための索引や要約を作成し、さらにそれを世に配布し、広大な印刷物の王国にアクセスできるネットワークを創造したのである。じつにすばらしい仕組みだ。だがエルナンドは、目録からタイトルを見つけ出し『題材別目録』でキーワードを見つけるこの方法では、探している本が具体的にわかっている人にしか役立たないと気づいた。それまで知らなかった新たな知識との出会いの場として図書館を利用する場合はまた別で、ブラウジング、つまり自由閲覧が必要となる。とくに目的もなく自由に見て回る、じつはそこにこそ、読者にとって最大の醍醐味がある。読者の心は、これは読まないわけにはいかないというカテゴリーや情報を教えてくれる一方で、眼中にないものは完全に遠ざけてくれるのだ」。
「エルナンドが遺した財産の主たる相続人は人間ではなく、彼の驚くべき創造物――図書館だった。この世で築いた財産を一群の『本』に遺すなど、ヨーロッパの歴史が始まって以来のことであり、その行為そのものが当惑を招いたに違いないが、それをさらに理解不能にしていたのが問題の図書館の『形態』だった。エルナンドの蔵書の多くは、当時の大型図書館に大切に所蔵されていた手稿本、すなわち神学や哲学、法学などの大冊、その価値に見合う豪華な装丁がほどこされた貴重な書籍ではなく。むしろ地位も名声もない著者による本や小冊子、さらに酒場の壁を飾るような、一枚の紙きれに印刷された物語詩など、当時の人々には紙くずにしか見えない代物だった。偉大なる探検家の息子が遺したものは、はたから見ればなんの役にも立たないごみ同然だったのである。しかしエルナンドにとっては、あらゆるものを蒐集し、それまで誰も思いつかなかった『ユニバーサル』な図書館をつくりあげたいという夢へ近づけてくれるかけがえのないものだった。いつ始まりいつ終わったのかもわからない種々雑多なコレクションには。書物に加え、いくつもの収納箱に入った版画(史上最大のコレクションだった)のほか、一カ所に集められたものとしては最多となる楽譜も含まれていた。また、外の庭園には世界中から集めた植物が植えられていたと伝えられるが、当時はまだ、そうした庭を呼ぶ『植物園』という言葉は存在しなかった」。
「だがなんといっても、彼が抱いた最大の野望である、全世界の知識を集めた宝庫――キーワードによる検索が可能で、概要を通じてさまざまな情報に触れ、異なる基準に沿った並べ替え、そして世界中に広がる拠点からのアクセスが可能なそれはまさしく、ほぼ500年後に登場するワールド・ワイド・ウェブ、サーチエンジン、データベースといった、インターネットの世界を予感させるものだった。エルナンドの努力は並大抵のものではなく、彼が描いたプランは驚異的だが、じつは彼が目指したプロジェクトは、デジタル化や、テクストを読み取って他の言語に書き換える機械の能力、コンピュータのブール論理で動く検索界の巨人グーグルはグーグル・ブックス・プロジェクトにおいて、エルナンドの死後500年のあいだ滞っていた作業の大半を、わすか数年で完成させた(だがしかし、この革新的プロジェクトもまた、たちまち著作権をめぐる法的な問題にはまり込み、いま現在もなかば非公開事項となっている)」。
自分なりの、知の脳内図書館構築に取り組んでいる私にとって、何とも刺激的な一冊です。