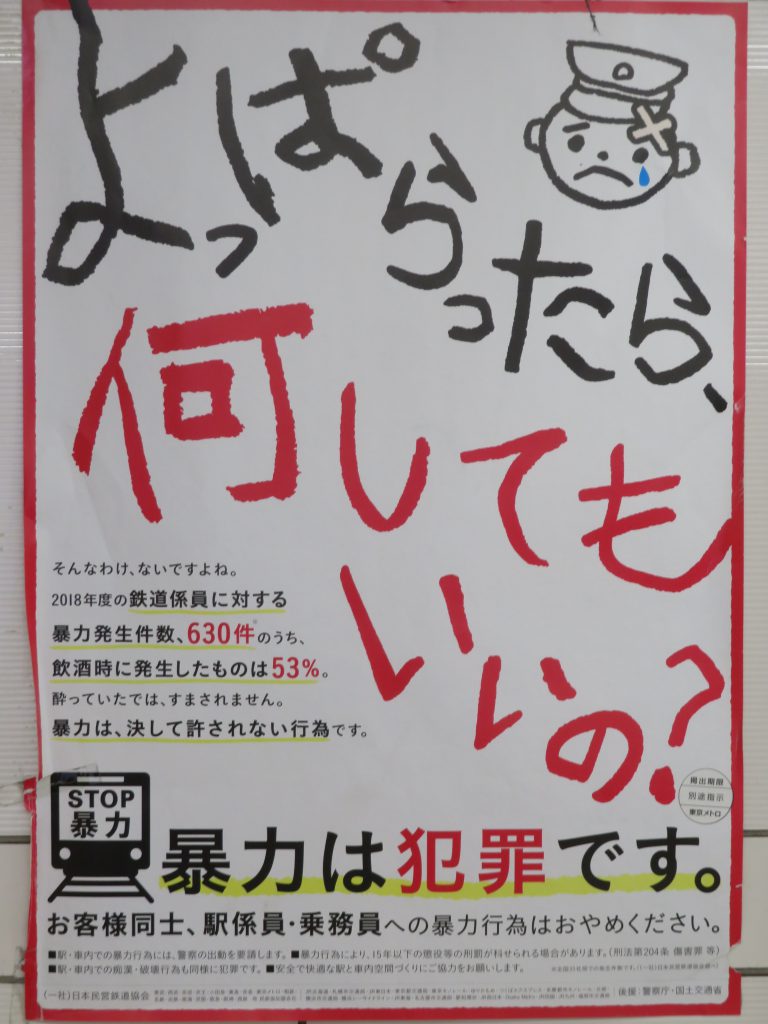ルネ・デカルトは、身分違いの内縁相手とその娘に、どのように接したのだろうか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2432)】
パソコンがあなたの恋人なのねと、女房から、しょっちゅう嫌みを言われています(涙)。
閑話休題、『死にたいのに死ねないので本を読む――絶望するあなたのための読書案内』(吉田隼人著、草思社)の中で、著者が、「デカルトが関係をもった女中ヘレナとその娘フランシーヌについてもう少しアカデミックなアプローチを望まれる向きには」『デカルトと女性たち』(シャルル・アダン著、石井忠厚訳、未来社)を薦めているので、早速、本書を手にしました。
ルネ・デカルトの往復書簡や同時代人の数多の証言に基づいた実証的な著作なので、強い説得力があります。
「彼(デカルト)の交ったのはエリザベト王女やクリスティナ女王のような雲上人ばかりではないのであって、近親の者たち、パリの上流市民の女性たち、オランダの貴族階級の婦人たち、才芸に秀で品位も並々ならぬ貴婦人でもあった一人の女流学者、こういった人々はむろんのこと、目立たぬ身分の、もう少しはっきり言って、卑しい階層の女たちもいたのであって、彼女たちの一人とは、少なくとも、ある時期、彼は密接な関係をもって結ばれたほどなのである」。
「デカルトはデフェンテルに1632年6月から1633年12月まで住んでいた。弟子の一人、レネリの近所に。この弟子がこの小都市の大学でデビューしたので気がかりだったのである。そして恐らくこの頃、彼はヘレナを識り、女中に雇ったのであろう。彼女は彼に付いてアムステルダムにも来たのだろうか。彼はそこに1633年12月には戻っていたのであるが、少なくとも1634年10月15日、日曜日、そこで例の子供(フランシーヌ)は母親の胎内に宿ったのである。・・・母親はお産のためにデフェンテルに戻った。そして当時ユトレヒトにいたデカルトは、1635年5月、彼女に会いに行ったらしい。2年の歳月が流れる。それから、1637年夏、ハルレムに近いサントポルトというかなり鄙びた所に下宿する。そこに(そこから出された日付入りの手紙によって確かめると)1937年後半、1638年と39年の2年、そして少くとも1640年4月まで、すなわち2年半以上も住むことになる。彼は自分の傍に子供と母親を呼び寄せようと考える。母親が彼に手紙でそうしてくれと頼んで来たのである。彼からの、1537年8月30日付の一通の手紙がこの問題について興味ある情報を与えてくれる。彼の下宿先の女主人は、気の良い女だったらしいが、彼に子供(彼はこの子を『姪』と呼んでいる)を引き取ってよい、『いつでもあなたのお好きなときに。お金のことなど簡単に話がつく、世話をする子供が一人くらい多かろうと少かろうと大したことではないから』と言ってくれたのである。ヘレナについては、彼女はデフェンテルで女中奉公をしていたようであるが、彼女にも暇がとれ次第女中として来てもらうことになろう。9月30日の聖ヴィクトリア祭の頃がよいが、その前でも、彼女の方で代りの者が見つけられるようならさしつかえはない。それゆえ、デカルトは彼の幼い娘と、この子の2歳、3歳、4歳半の時期(1637年10月から1640年4月まで)すなわちこの子がまさに愛らしさを発揮し出す年齢の時期に共に暮したわけである。そして彼は目の前にあるあらゆる事柄について哲学することを愛していたから、彼女についても色々と書き留めていったにちがいない。このメモ類がフランシーヌ伝を書く際に彼の役に立ったものと思われる。この伝記が単なる年表の如きものではなかったとしての話であるが。いずれにせよこれは余り長いものであったはずはない。バイエの言う所によれば、これはある本の見返しに書き込まれてあったそうだから。この本は若干の者によって読まれた可能性がある。それゆえ哲学者(デカルト)はバイエが『彼の生涯の屈辱的な状況』と呼ぶ所のものを秘密にしていたわけではない。デカルトの書簡が、身近に子供とその子の母親を置いて共に暮したこの2、3年間ほど喜びに息づいていたことはないということを指摘しておこう」。
「ところで、1640年4月、彼はライデンに戻るが、この時には二人を伴ってはいない。彼女たちを連れて行きにくい事情があった。この都市には数多の知己がいたからである。ここはもはやサントポルトのような田舎ではなかった。おまけに、彼の情事の知れわたっていない土地でもなかった。・・・当時、恐らくはデカルトは子供をフランスに送り、親族のデュ・トロンシェ夫人に託して、フランス流に躾けてもらおうと心に決めていたようである。・・・しかし1640年9月7日、子供はアーメルスフォルトで死んでしまう。母親が多分そこへこの子を伴って行っていたのであろう。デカルトはずっとライデンにいたが、不意にここを発っている。・・・彼はこの15日間をアーメルスフォルトで過したのであり、そしてこの不意の出立は母親から緊急の報らせがあったためであると考えてよいのではないか(もっとも子供は『全身紫斑におおわれる』病に冒されてから、わずか3日後に死んだのではあるが)」。
「哲学者は幼いフランシーヌの死は自分に生涯最大の悲しみをもたらしたと告白した。・・・(われわれが注目すべきは)彼が幼いフランシーヌに対して、この子の短かい生涯の間、そしてその死後までも抱き続けた愛情ではなかろうか。これこそ彼の名誉となるものではなかろうか」。
私の尊敬するデカルトが、身分違いの内縁相手とその娘に対し冷淡ではなかったこと、そして、人間的魅力を備えた人物であったことが分かり、ホッとしました。