本書のおかげで、ヒグマについて、いろいろ学ぶことができた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3742)】
茨城の筑波山の麓の「葛城の森」の植物観察会に参加しました。小幡和男講師、永谷真一講師の説明を受けながら、ムラサキシキブの花(写真1)、クリの雄花と、雌花から成長した実の赤ちゃん(写真2)、実(写真3)、アカマツ林(写真4)、アカマツの雄花と、雌花から成長した実の赤ちゃん(写真5)、実(写真6)、エノキの実(写真7)、コナラの実(写真8)、クヌギの実(写真9)、シラカシの実(写真10)、ヤマウルシの実(写真11)、ヌルデとヤマウルシの葉(写真12、左がヌルデ)、ヒメコウゾの実(写真13)、ウメガサソウの実(写真14)、キヅタ(写真15)、ツタ(写真16)、ツタの吸盤(写真17)を観察しました。


















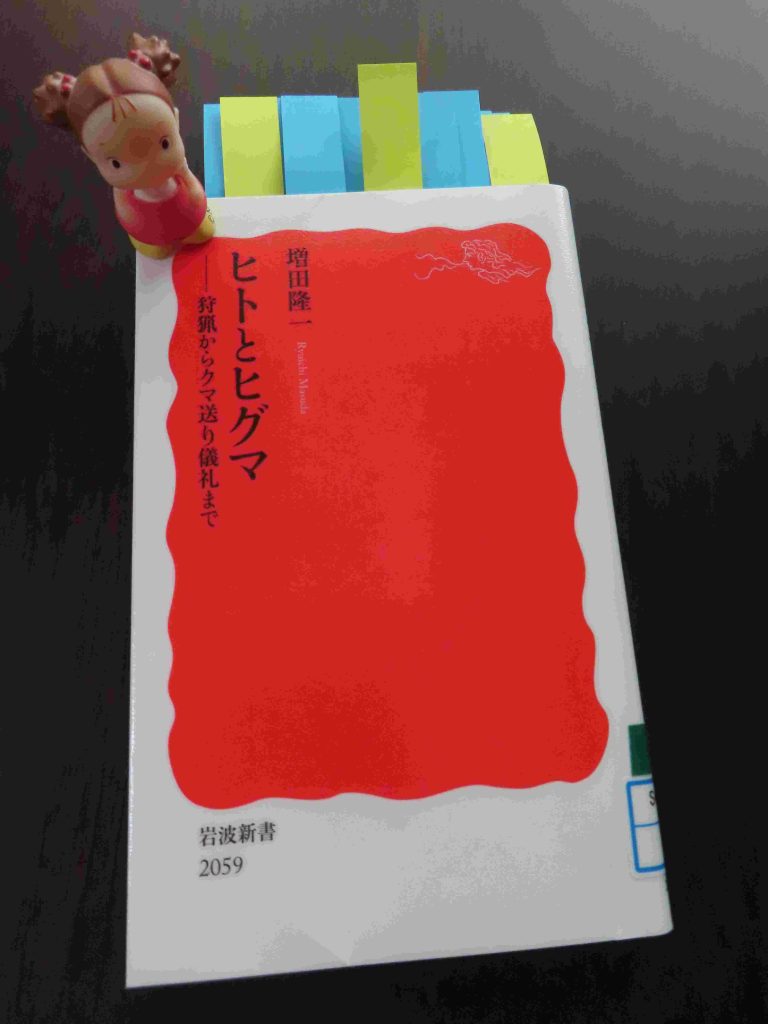
閑話休題、『ヒトとヒグマ――狩猟からクマ送り儀礼まで』(増田隆一著、岩波新書)のおかげで、ヒグマについて、いろいろ学ぶことができました。
●ヒグマの起源地
最も古い化石が発見されたユーラシア大陸の内陸部である可能性が高い。
●ホラアナグマ
約25000年前に説滅した大型のホラアナグマとヒグマは、約160万年前に分岐したと推定されている。
●ホッキョクグマ
染色体DNAの分析から、約60万年前にホッキョクグマとヒグマが分岐したと考えられている。
●北海道ヒグマ
ミトコンドリアDNAの分析から、ユーラシア大陸から3つの系統が北海道にやってきたと考えられている。最初にやってきたのは道南系統、次にやってきたのは道東系統、最後にやってきたのは道北ー道央系統である。すなわち、三重構造となっている。
●ネアンデルタール人
ホラアナグマにもヒグマにも出会っていたことは間違いないであろう。
●ホモ・サピエンス
ネアンデルタール人、ホラアナグマ、ヒグマと出会っていたと考えられる。ホモ・サピエンスが、ヒグマという動物を対象として、狩猟からクマ送り儀礼を発展させたことは注目に値する。
●アルプスのアイスマン
約5300年前に生きていたアイスマンの帽子はヒグマの皮で作製されていた。
●未確認動物「イエティ」
体毛、毛皮、骨などのミトコンドリアDNA分析の結果、「イエティ」の正体は、チベットヒグマ、ヒマラヤヒグマ、アジアクロクマ(ツキノワグマ)であることが明らかにされている。
本書の後半では、ヒトとヒグマの関係、とりわけクマ送り儀礼について詳細に考察されています。
