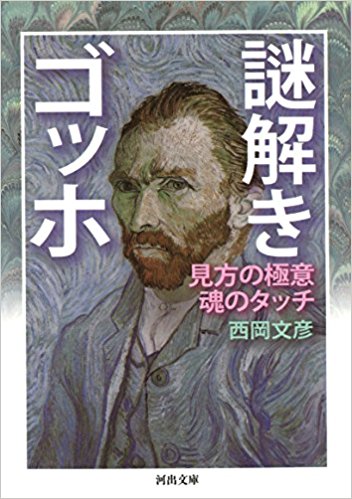ゴッホは日本に憧れ、浮世絵のような絵を描こうとした・・・【情熱の本箱(216)】
フィンセント・ファン・ゴッホは多くの謎を残したまま、37歳の時、ピストルで自らの命を絶ってしまった。その謎――●ゴッホは、なぜ売れなかったのか、●ゴッホは、なぜ画家になったのか、●ゴッホは、なぜひまわりを描いたのか、●ゴッホは、なぜアルルを日本と思ったのか、●ゴッホは、なぜ浮世絵に熱中したのか、●ゴッホは、なぜ急いで描こうとしたのか、●ゴッホは、なぜ究極の黄色を求めたのか、●ゴッホは、なぜ大量の白を必要としたのか、●日本人が購入したゴッホの「アルルの寝室」が、なぜオルセー美術館にあるのか、●ゴッホは、なぜ耳を切ったのか、●ゴッホは、なぜ麦畑を描いたのか、●ゴッホは、なぜ愛されるのか――に果敢に挑戦し、説得力ある回答を提示しているのが、『謎解きゴッホ――見方の極意 魂のタッチ』(西岡文彦著、河出文庫)である。
いずれの謎解きも興味深いが、私が最も引き込まれた謎は、「ゴッホは、なぜアルルを日本と思ったのか」と「ゴッホは、なぜ浮世絵に熱中したのか」である。
「ゴッホがゴッホになったといわれる南仏アルルを、ゴッホ自身は『南仏の日本』と思い込んでいた。・・・温暖な地中海性気候には瀬戸内海を思わせる部分もなくはないが、澄み切った大気と明るい陽光に恵まれたこの街を、南仏の日本と見なすことには無理がある。・・・なぜゴッホは、自分の絵を浮世絵のような作品と見なし、アルルを南仏の日本だと思い込んでしまったのだろう。ゴッホが画家として実現しようとしていたことを知るためには、この2つの疑問を避けて通ることはできない」。
「浮世絵には、伝統的なヨーロッパ絵画が禁じている手法が、ほとんどすべて動員されていた。浮世絵の造形の特徴は、くっきりとした輪郭線、平らに塗られた色面、あざやかな原色の対比にある。いずれも、木版画の持つ技術的な限界から必然的に導き出された特徴であったが、こうした造形手法はすべて、ルネッサンス以来の伝統的絵画ではタブーとされていたものばかりだったのである」。
「画家としての兄の飛躍のために、印象派の画家達を紹介し、当時のパリを席巻していた日本美術の魅力を教えたのもテオであった。この印象派の光の洗礼と、浮世絵の色彩の洗礼によって、陰鬱なほど暗かったゴッホの画面は一変し、スーラ風の点描と骨太の描線とが混在する独自の画風を模索し始めることになる」。
「アルルからの手紙は、初めて日本人の物の見方、色の感じ方が理解できたと書いている。『フランスの日本人』である印象派は、『フランスの日本』である南仏へ来るべきだとも書いている。絵画の未来は日本にあると確信したゴッホは、南仏の日本に新進画家の共同体を建設するという夢を描くことになる。ゴーギャンをイエスに見立てた十二人の画家と画商使徒としてのテオによって構成されるこの『日本的』共同体の夢想のなかで、ゴッホは、彼を破門した神に再会する宗教者としての道を模索していたのであろう。(日本の)僧侶としての自画像は、日本の浮世絵に倣って、影を描かぬ平坦な色面で描かれている。ヨーロッパ絵画には、異例の表現である。が、その浮世絵の色面が、木版画という技法の制約から陰影を省いていることは、ゴッホにはわからなかった。影を描かない画面は、光に満ちた文字通りの『日出ずる国』で描かれたがゆえの、色彩の輝きと誤解していたからである。ゴッホが、陽光の輝く南仏を日本と誤解してしまったのはそのためである。この誤解が、ゴッホをして南仏へと駆り立てることになったのである」。
「実際には、日本の変化に富んだ四季は、湿潤な大気感と複雑な陰翳をもたらすものであり、浮世絵の平坦な色面は、木の板に版を彫って刷るという木版の技術的な制約から生じた様式でしかない。が、髪の毛の一本まで再現する浮世絵の彫りの技術や、微妙この上もないぼかしを生む刷りの技術に圧倒されたヨーロッパ人は、この精緻な木版技術が陰影を表現できないなどとは想像もつかなかったに違いない。影を『描かない』のではなく、影を『描けない』浮世絵の風景を鵜呑みにしたヨーロッパの人々の多くは、ゴッホと同様に、日本を南仏のような風土の国と思いこんでしまったのである」。
「まだ見ぬ日本という光の国を、ゴッホが芸術のユートピアとして夢想してしまった最大の要因のひとつに、日本の画家達が、共同生活を営み作品を互いに交換しながら画業に励んでいるという、彼の思い込みがあった。・・・浮世絵は、絵師が下絵を描き、彫師が彫った版木を用いて、刷師が紙に刷ることによって完成する。専門職によるこの分業が、分業ではなく共同と解釈されれば、その工程は、なにやら共同作業の色合いを帯びて映っても不思議はない。ゴッホが、日本では画家が共同生活の中で制作していると思い込んでしまった背景には、その種の誤解があった可能性が大きいように思われる」。
「おそらく、その夢想はゴッホの胸を焦がすような憧れを喚起したに違いない。その夢想の中には、彼が望むすべての夢が含まれており、彼が失ったすべての夢が息づいていたからである」。
「彼らしい思い込みから、浮世絵こそが自分の理想とする美術品のあり方を具現したものと誤解してしまったゴッホは、日本の画家の生活様式から日本の気候風土まで現実とかけ離れたものを夢想していたに違いないのである。アルルを南仏の日本と思い込み、自分の絵を浮世絵のような作品と思い込むことになってしまったのは、そのためであったに違いないのである」。
生前には作品がたった1点しか売れなかった無名の画家・ゴッホが、今日、これほど世界中で愛されるようになったのには、弟・テオ、弟の妻・ヨハンナ、彼らの息子・フィンセントの努力の積み重ねがあったことを知り、胸が熱くなった。ゴッホの作品には、ゴッホだけでなく、「命を賭して兄ゴッホの名を世に知らしめようとしたテオの魂、亡き夫テオの遺した思いを遂げることに生涯を賭したヨハンナの魂、さらには、そのヨハンナが、命を賭して産み落としたもうひとりのフィンセント(=フィンセントという名はゴッホに因んで命名された)の魂」も籠もっているのだ。
知的好奇心を激しく刺激する一冊である。