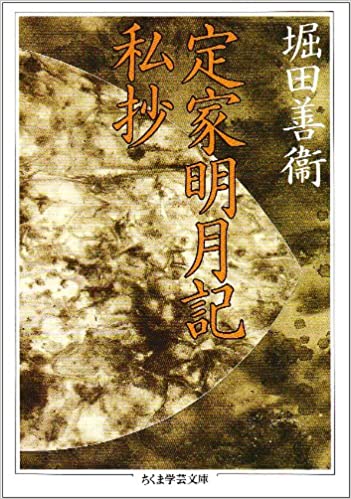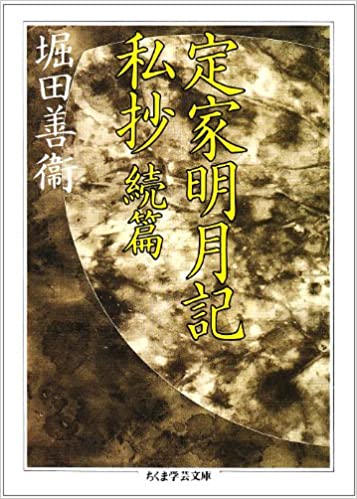『明月記』から読み解く、定家の西行との関わり、後鳥羽院との微妙な関係、そして、実朝の真実・・・【情熱の本箱(351)】
『定家明月記私抄』(堀田善衞著、ちくま学芸文庫)と『定家明月記私抄 続篇』(堀田善衞著、ちくま学芸文庫)では、若い時に『明月記』に出会って以来、数十年をかけて読み継いできた堀田善衞と、藤原定家が一体化している。これだけ長い付き合いとあっては、当然のことだろう。
「『明月記』の面白さは、(藤原兼実の)玉葉などとともに歴史的、時代的といった形容句のともなうものとしてもさることながら、やはり定家という人その人に即いての面白さであり、ときとしてはその癇癖の高さがかえって当方の哄笑をさそったりもし、その哄笑の間に、苦虫を噛みつぶしたような定家氏の表情までが見えて来たりもするのである。またその職業歌人としての矜持、二流貴族としての苦渋、歌壇操作のやり切れなさ、あるいは今日のことばで言っての生活難をかこつところなどは、同じ文筆業をいとなむ者として同情を禁じえないところもあり、私としては同業の先輩の日常の記として読んでいたこともあった」。
「すでに長の歳月にわたって彼の日記によってこの歌人と付き合って来て、この人の大概の言いぐさや癖、物事、事件に対する反応の仕方、あるいは考え方の屈折などについては、一通りは承知しているつもりではあるけれども、その日記の、どの部分をひらいてみても、やはり驚かされるところがある」。
私にとって、とりわけ興味深いのは、若き定家の西行との関わり、定家と後鳥羽院との微妙な関係、源実朝の真実――の3つである。
●西行――。
定家は、歌の道に専念することに決したのは、と問われて、若い時に西行に会ったことを挙げている。「父(藤原)俊成などにやかましく言われたことなどはそっちのけで、西行である。・・・西行の歌風と宮廷歌人としての俊成、定家などのそれとは劃然として別のものである。しかもなお、西行なのである。余程印象が深かったものとしなければならない。文治二年、西行六十九歳、定家は二十五歳、この年に定家は『文治二年、円位上人(西行)、之ヲ勧進ス』として二見浦百首なるものを詠んでいるのであるが、このときに勧進――すなわちすすめられて百首歌を伊勢神宮の神に手向けた者は、定家、家隆、寂蓮、隆信、祐盛、公衡等のほか、伊勢在住の蓮位以下の四法師と度合某なる人などであるが、いずれも京、伊勢の錚々たるメンバーであり、西行という人物の、いわば動員力を如実に物語っているものである」。
「(西行は)生涯経済的な心配のない豪族の出であったが、徳大寺家の家人であり、平清盛とは同年でともに鳥羽院の北面に仕えていたことがあり、彼の遁世後といえども、権力の中枢に立った人々との交渉は絶えたことがなかった。鳥羽法皇、崇徳上皇、入道信西、平清盛、源頼朝、藤原秀衡等、数えて行けば百人を越え、出家などというよりも、『政僧』ということばを使いたくなるほどの部分を色濃くもっているのである。・・・この人物の巨大さ、あるいは巨怪さが知られるであろうと思う。・・・放胆にして鋭利、おどろくべき人物であろう。・・・かかる異様な大人物が、彼の側からして若き定家に接触を求めて来てくれたのである。それは歌の家に生れた者の仕合せの一つであった。印象の浅かろう筈がないのである。父俊成や、周辺の競い合わねばならぬ立場にある歌人たちなどとは比較にならぬ強烈なものが、『久しくあひ伴ひて聞きならひ侍りし』際に存したであろうことも想像に難くないのである」。
若い定家が西行から大きな刺激を受けたという話は、浅学にして知らなかったが、西行という人物が、単に優れた歌詠みではなかったという指摘には、もっと驚かされた。
●後鳥羽院――。
後鳥羽院は桁外れの大遊戯人間であった。「この年(建仁元年)は、後鳥羽院は水無瀬離宮での遊女やら白拍子やらを総揚げしての遊興とともに、憑かれたようにして和歌に熱中しはじめ、その出来映えもまた定家をして『金玉ノ声、今度凡ソ言語道断ナリ。今ニ於テハ、上下更ニ以テ及ビ奉ルベキ人無シ。毎首不可思議。感涙禁ジ難キ者ナリ』と感歎させるほどのものであった。この院は実際に主催者としても実践者としても、競馬、相撲、蹴鞠、闘鶏、囲碁、双六、それから何軒もの別邸と庭園の建造等々、何をさせても、いわばルネサンス人的な幅をもっていて、京都宮廷などというせせこましいところに閉じ込めておくのが惜しいくらいのものであった。後には承久の乱という戦争までを発起する。しかも後鳥羽院御口伝などの歌論書にも見られるように、他の歌人の歌の鑑賞についても批評家として充分に自立しえていたと言っていい」。
「後鳥羽院その人もまた遊戯人間(ホモ・ルーデンス)の典型的存在である。承久の乱などという戦争行為も、『真面目な』かつ真剣な権力闘争としては、その準備において、また指揮作戦についても欠けるところの方が多い。帝王的大らかさなどと屡々称される評価や形容の仕方は不正確というものであろう。・・・(定家の)出世昇官への望みはますます強烈になって来るのであるけれども、ここに困ったことなのは、大遊戯人間にとっては、和歌もまた諸芸能のうちの一つにすぎないことである。蹴鞠、管弦、連句、勝負笠懸、賭弓、双六などの遊芸、遊宴の道に長けた者は、ただの武士でも白拍子、遊女でもたやすく昇殿を許されるのが実情であり・・・和歌所の復活は、新古今集編纂のため、及び宮廷遊戯あるいは『御遊儀』の一つの制度化であり、それ以上のものではなかった。出世昇官とは次元の異る問題であり、後者は政治的実力の範疇に属する」。
「後鳥羽院もまた執念深い男である。後に(流された)隠岐の島での、今日『後鳥羽院御口伝』として伝えられている歌論書に『定家は左右なき物なり』、すなわち定家はもうどう仕様もない頑固者だ、と前置きをしてこの時の歌を引き、『傍若無人、理も過ぎたりき。他人の詞を聞くに及ばず』とまで言い出す素地をつくるのである」。
歌という特技を通じて宮廷で出世したい定家と、歌は数ある趣味の一つに過ぎない後鳥羽院では、しょせん相容れぬのは已むを得ないだろう。
●実朝――。
定家の実朝観は辛辣である。「(実朝は)成長するに従って現実が見えなくなって行く青年、と見える・・・幕府の長として、鎌倉将軍として、実際に実朝が何をしていたかを調べてみると、そこに実に異様な形姿が浮び上って来る。政治上の実験が、執権北条義時に握られていたことは、これは言うまでもない。・・・(実朝の)日常のほとんどは、神事と仏事、それも仏教、密教と陰陽道の習合した、何とも怪異な祭事や仏会についやされているのである。百日泰山府君祭、天地災変祭、天曹地府祭、七座泰山府君祭、三万六千神祭、百怪祭、鬼気祭等々・・・。実朝は、幕府の長であるよりも、その幕府における祭祀の長であり、時には祭祀用の象徴でしかなかった。しかもそうした象徴にとって最重要、かつ最優先の任務である、嗣子を生ませることが、未だに出来ていないのである。不毛の祭祀長である」。
「実朝は、幻想のなかに生きている。そうしてこの幻想のピークに来るものが、大船建造による。渡宋幻想である」。
「『箱根路をわれ越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄る見ゆ』。平安鎌倉期の和歌には、和する歌としての和歌の特質にもとづいて、いわゆる絶唱といった言い方に相当するものは、まず見当らない。けれどもこの一首は、やはり絶唱というに価するであろう。現実を失ってしまった者の眼に、箱根路、伊豆の海、沖の小島はまさに現実そのものでありながら、この風景はすでに現実から離陸してしまっていて、実朝の心象としての風景と化し、渺茫として風の音ばかりが耳に鳴っている。風景の自己分身(ドッペルゲンガー)である。この歌の周辺に、和すべき者も、また和すべき歌も何もない。ありえない。孤独な実朝がいるだけである。絶唱たる所以である」。
ここまで実朝に厳しい評価は、管見の限り、初めである。