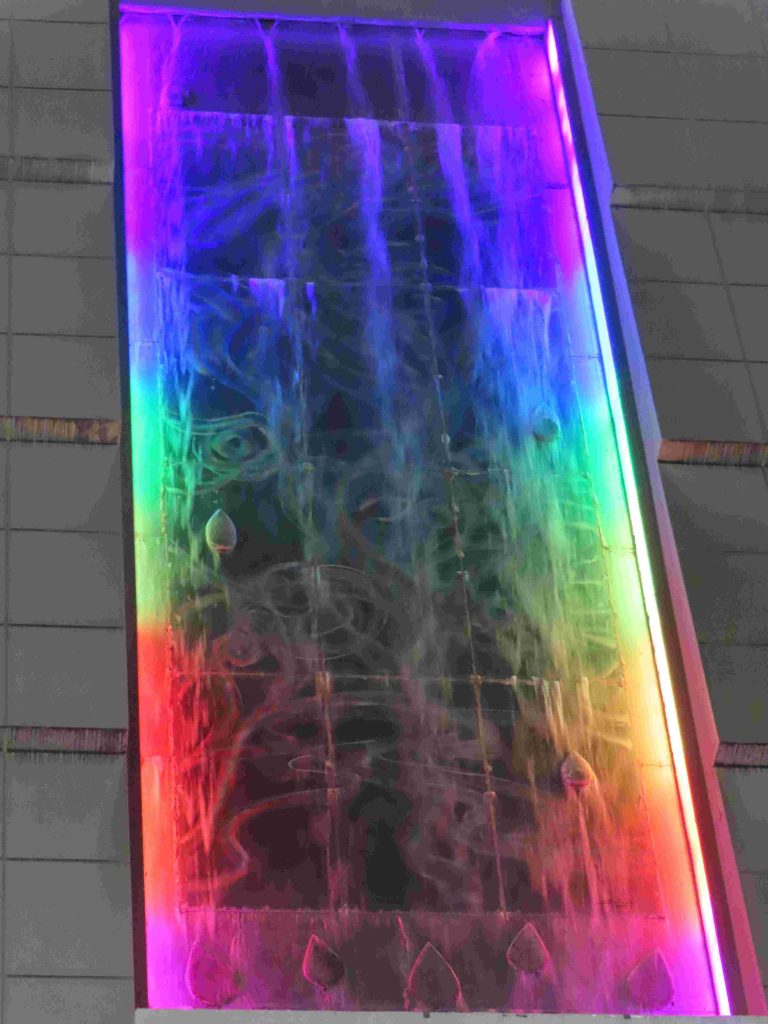斎藤美奈子に唆されて、読みたくなった本が9冊・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2977)】
アガパンサス(写真1、2)が咲き始めています。アスチルベ(写真3)、アルストロメリア(写真4)が咲いています。ブドウ(写真5)が実を付けています。ニホンカナヘビ(写真6)をカメラに収めました。
閑話休題、厚さが5.1cmある『本の本――書評集1994~2007』(斎藤美奈子著、筑摩書房)は、斎藤美奈子の切れ味抜群の書評がてんこ盛りです。
『打ちのめされるようなすごい本』(米原万里著)の書評を、斎藤は「書評とはひっきょうサービス業であることを米原万里はよく知っていた。そして一日七冊とは、こうやって読むことなのだと改めて教えられるのである」と結んでいます。米原と斎藤の書評に対する考え方に大賛成!
斎藤美奈子に唆されて、読みたくなった本が9冊――。
●容貌差別への挑戦状――『説教師カニバットと百人の危ない美女』(笙野頼子著)
「果敢にも『自覚的なブス』を語り手に迎え、女の容貌問題への正面突破を試みた、おそらく本邦初の長編小説である。この本気さ。しつこさ。正義の味方が悪をくじく活劇のようにおもしろい。しかし同時に、これは恐ろしい小説でもある。読む人の意識も、この活劇はまともに直撃してくるからだ」。
●お勉強よサヨウナラ、新解釈よこんにちは――『文学がもっと面白くなる』(金井景子・金子明雄・紅野謙介・小森陽一・島村輝著)
「読み切りの文章とアンソロジーで構成された本書は、学校教育的な文学観を打ち壊そうとする野心にあふれ、どうして悪くないのである。学校では自然主義文学の嚆矢と習ったはずの田山花袋『蒲団』に<(近代文学史上の重要度)×(思わず笑ってしまう指数)=(教室で笑われる指数)の最も高い作品>、つまり『笑える小説』のラベルを張って巻頭に持ってきている、といえば方針がおぼろげに見えてくるだろう」。
●中世と現代をつなぐ、爽快な「平家」論――『男は美人の嘘が好き――ひかりと影の平家物語』(大塚ひかり著)
「『平家物語』っていわれてもなあ、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり(だっけ?)しか知らないからなあ、と頭をかく古典音痴の人でも大丈夫。というか古典嫌いの人こそ本書の最良の読者である。なにしろ著者は頭からビシッとかましてくれるのだ。<『平家物語』にはブスがいない>」。
●浪花節とナショナリズム――『<声>の国民国家・日本』(兵藤裕己著)
「そう、『旅ゆけば、駿河の国に茶の香り・・・』という、あの浪花節だっ。いまでは伝統芸能の一種として命脈を保っているにすぎない浪花節も、明治末期から昭和前半期までは、Jポップの最前線をいく、まさに国民的な一大人気ジャンルだった。というだけでも『へえへえへえ』だけれども、本書のテーマは、その浪花節(名前に反してそのルーツは上方ではなく近世の江戸にある)が、『国民』意識の形成に多大な影響を与えたという点にある」。
●文学界の金八、批評の現状を憂う――『メルトダウンする文学への九通の手紙』(渡部直己著)
「知命をすぎても、大学教授になっても、その勢いは衰えず、本人の用語を借りれば『通りすがりのビンタ』にも似た痛罵が、今回も容赦なく繰り出される。とはいえ、この『ビンタ』はむしろ渡部直己の過剰な、鬱陶しいほどの、『もういいからほっといて』と相手が逃げ出したくなるほどの愛によるものであって、その伝でゆくと彼の資質は批評家という以上に教育者に近い。渡部直己はさまぁ~ずというより『文学界の金八』なのだ」。
●エロスな本――『ルビーフルーツ』(斎藤綾子著)
「斎藤綾子は現在もっとも刺激的な官能小説を書ける女性作家。女性ファンも多い、この本は性の快楽を貪欲に求める女の子たちを描いた短編集で『なんてエッチなのっ』と身悶えできること請け合い。SMからレズビアンまで、いろんなパターンが出てきてびっくりするかもしれないけれど、セックス・ファンタジーはこのくらい『飛んでる』ほうが盛り上がれます。ちなみに『ルビーフルーツ』とは女性器の名称を彼女流に表現した言葉」。
●血を流す立場からの選択は――『我、自衛隊を愛す故に、憲法9条を守る――防衛省元幹部3人の志』(小池清彦・竹岡勝美・箕輪登著)
「この改憲は自衛隊を認めるためではなく、米国に追従した海外派兵が目的であること。国際貢献の名の下に海外派兵をしなければ非難されるなど嘘で、日本は平和国家として世界の尊敬を得ているし、自衛隊員も専守防衛を誇りに思っていること。国防と名誉の観点からこそ改憲は阻止すべきだと彼らは主張するのである」。
●十八世紀は科学革命と同時に性差の再編期でもあった――『女性を弄ぶ博物学――リンネはなぜ乳房にこだわったのか』(ロンダ・シービンガー著、小川眞里子・財部香枝訳)
「一番のビッグスターとして登場するのは、あのカール・リンネである。いまの分類学の基礎を築いた『近代分類学の父』だけれども、どうもこのリンネおじさんの女性観(?)が、新しく形成された自然観には色濃く影をおとしているもようなのだ。植物の受精をロマンチックな結婚になぞらえたのもリンネ、哺乳類(英語でママル。ラテン語ではママリア。字義通りに訳せば『乳房類』の意味である由)を哺乳類と名づけたのもリンネである。なんだってまたそんな性的なイコンを、彼は分類上の名前に採用したのか」。
●ナチュラリストだったシートンの横顔が浮かび上がるノンフィクション――『シートン動物誌(全十二巻)』(アーネスト・T・シートン著、今泉吉晴監訳)
「これは『(動物)記』ではなくて『誌』。あっちが『オオカミ王ロボ』のようなフィクションとしての動物物語なら、こっちはまったくのノンフィクション。全巻の邦訳が出るのは今回が初めてである。シートンの出世作である『シートン動物記』は、アメリカでも大好評で迎えられたが、同時に大きな論争にも発展したらしい。この本の成功がつぎつぎと追随者を生み、動物の擬人化が問題になったのだという。本署は、そのような論争の後に、シートンが三十年の歳月を費やして書き上げたライフワークともいえる大著である」。