紫式部は宮廷社会で実務に有能な女房だった・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3180)】
カラスウリ(写真1)が実を付けています。ソメイヨシノ(写真2~5)が紅葉しています。






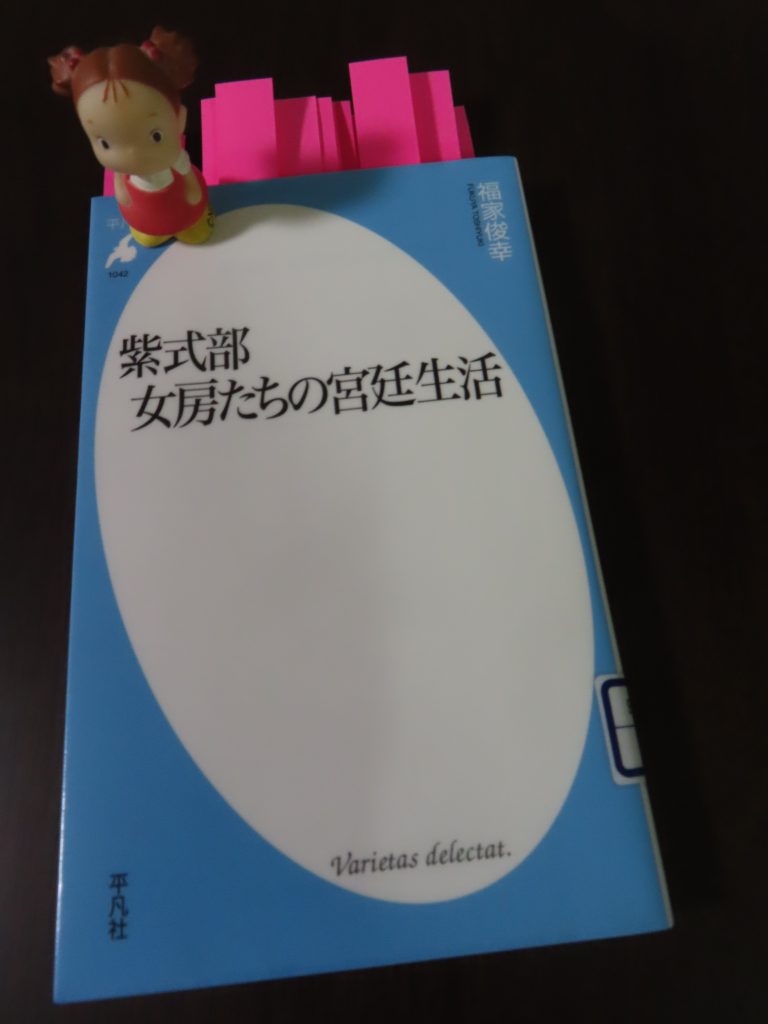
閑話休題、『紫式部 女房たちの宮廷生活』(福家俊幸著、平凡社新書)で、とりわけ興味深いのは、●紫式部は宮廷社会で実務に有能な女房だった、●女房から派生した召人(めしうど)という存在、●紫式部による清少納言の批評――の3つです。
●有能な女房
「紫式部は早くに父(紫式部の夫・藤原宣孝)を喪った娘(賢子)を見事に養育するとともに、その輝かしい人生のレールをも敷いていたのだった。紫式部の人生は『源氏物語』によって切り拓かれた。彰子との信頼関係の根底に『源氏物語』があったことは確かだろう。しかし、そのような物語作者であるだけではなく、紫式部が宮廷社会で実務に有能な女房であり、母であったことも見逃してはならないだろう」。
●召人
「女房の中には、主人筋の男性の愛を受け入れる者もいた。このような女房を平安時代では特に召人といった。・・・紫式部が生きた時代は、この召人が貴人の許に多く仕え、文学作品にも登場している。・・・『源氏物語』にも召人が登場する。・・・召人は召人に過ぎず、妻との間に圧倒的な身分差があった。・・・召人が妻になることはない。あくまでもその関係は主人への奉仕に留まるのである」。
「早朝に、女郎花の花をもって、局まで来る(藤原)道長の振る舞い、愛の分け隔てを嘆く紫式部の様子など、単なる主人と女房の関係を超えているという見方があり、紫式部召人説を強めている。その一方で、ここでの愛情とは、あくまでも主従の愛情だとする見方も当然ながら根強くある」。
「もしも、この(道長との)場面を紫式部が意図的に、後人の編集ではなく『紫式部日記』に記したのだとすれば、そこには道長から求愛されたということを書き留めておきたいという思いがあったのだと考えられる」。
●清少納言評
「紫式部は清少納言と会ったことはなかったと思われ、この(清少納言評の)執筆時点で、清少納言が宮中を退出してから、10年の歳月が流れていたが、なお清少納言の存在を意識せざるを得ない状況にあった(ちなみに、推定になるが。清少納言が紫式部より5~10歳ほど年長)。『そういう浮薄なたちになってしまった人の成れの果てが、どうしてよいことがありましょうか』という最後のことばは清少納言の不幸を祈る、呪詛のようにも響くが、それだけ紫式部は日ごろから清少納言を喉に刺さった魚の小骨のように感じていて、むきにならざるを得なかったのであろう。宮廷社会において、いまだ定子後宮の華やかな記憶が残る中、清少納言の存在の大きさと、さらに自らとの共通性をこの清少納言評は逆説的に伝えているのである」。
「紫式部も現代人と同様に、集団や組織の構成員の一員として、主家に奉仕し、主人の話し相手になったり、儀式に参加したりしながら、物語や日記を書き、和歌を詠む。一方で主家からの厚遇のためか、周りの女房から、やっかみを受け、嫌な思いもする。環境は違うが、人間の営みはそれほど変わっていないのではないかと思わせる」。著者・福家俊幸のこの言葉に大きく頷いてしまいました。
