表裏を使い分けた計略を凝らしながら精一杯の背伸びをして外交交渉に挑んだ戦国大名たち・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3197)】
早朝の東京・新宿の新宿中央公園で、オナガ(写真1~7)の群れに出くわしました。因みに、本日の歩数は11,921でした。














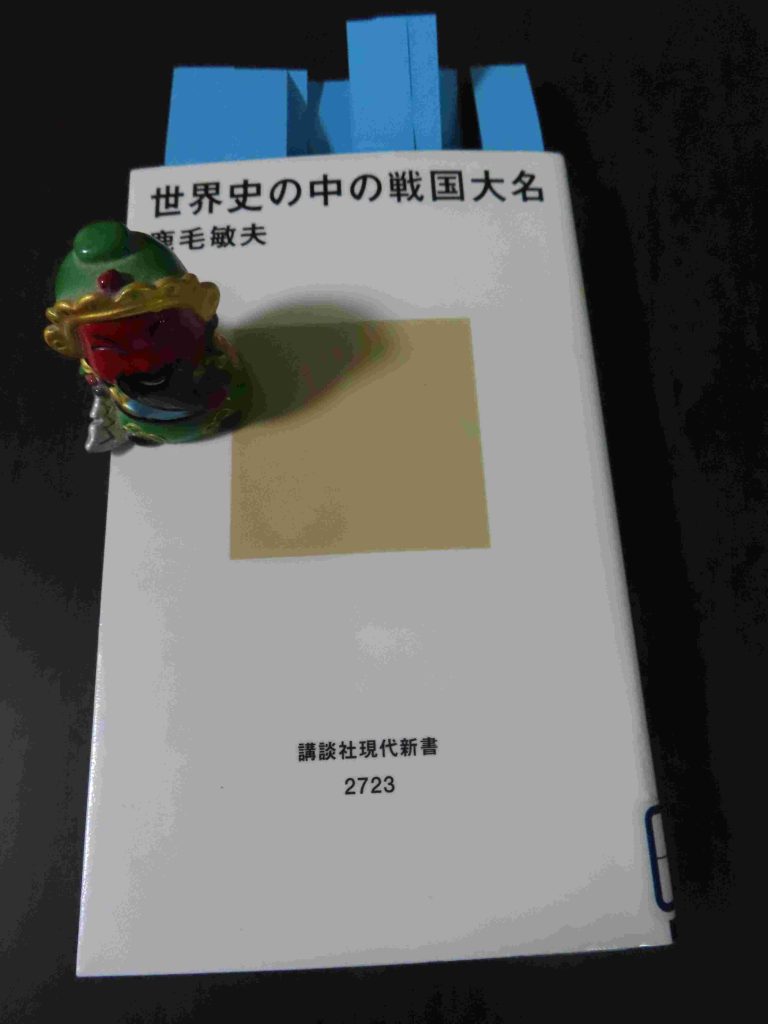
閑話休題、領土拡大に鎬を削っていた戦国大名というイメージを一変させる本が出現しました。『世界史の中の戦国大名』(鹿毛敏夫著、講談社現代新書)がそれです。
「東アジアにおける時代の大きなうねりのなかで、日本では戦国大名が一国史の枠内部の『天下統一』にとどまらず対外的に活動し、また、東アジア交流の活発な都市や港町を拠点とする豪商(貿易商人)が急激に成長した」。
「戦国大名による対外活動は、アジアの広範囲におよんでいた。特に、環東シナ海域の一角に位置する九州の戦国大名にとって、目前に広がる海は決して『陸路』交通の妨げとなる壁ではなく、自領と他領をつなぐ文字通りの『海路』として認識されていた。むしろ、その海の道に、あるいは自前の船を就航させ、あるいは行き交う船をチャーターして、諸外国と交易を行うことによってはじめて、陸上に拠点を置く彼らの大名領国制の基盤が維持されていたとさえも言えるのだ」。
「16世紀半ば以降、戦国大名の対外活動は東南アジアから南アジア、そしてヨーロッパへと、地球を俯瞰する広範囲に拡大していく。大友氏はポルトガルのインド総督への使者をゴアへ派遣し、また、松浦氏はアユタヤ国王へ書簡と武具を贈答した。カンボジア国王との間では、1570年代初頭までに大友氏がその外交関係の締結に成功したが、九州を二分する軍事衝突(豊薩合戦)以降は、軍事的優位に立った島津氏がその通交を遮断し、自らカンボジアとの善隣外交関係を構築しようとした」。
「さらに、1580年代になると、大村純忠や有馬晴信が主導して、ローマ教皇らに向けた書簡を携えた天正遣欧使節を派遣した。そして、17世紀初頭には、島津義久が琉球王国への介入を強めて出兵し、伊達政宗はメキシコ経由でヨーロッパに渡る慶長遣欧使節の派遣を実行した」。
「16世紀日本の戦国大名は、明代の中国からは、江南海域で密貿易を営む倭寇集団の活動に責任を負う存在と見なされ、カンボジア等の東南アジア諸国からは、周辺国との軍事衝突が続くなかで外交的支持と軍事的援助を相互に得る善隣外交パートナーとして認識された。さらに、ヨーロッパのイエズス会においては、東アジアにおけるキリスト教の布教を庇護しうる『国王』として、その宣教活動の成果を証明する絵画等の画像に戦略的に描かれた。こうした戦国大名の実態への評価は、私たちが通常の日本史の文脈でとらえる国内評価とは大きく異なるものであり、歴史を人間集団間の相関性から考察した成果として、世界史上に提示することが可能である」。
「戦国大名は、決して国内の国盗り合戦に終始したのでなく、『領国』の為政者として多様な外交チャンネルの締結を模索しながら、対外的な活動を繰り広げていた」のです。
個人的に、とりわけ強く印象に残ったのは、大内義隆と大友義鎮(宗麟)の二人です。
「この時代の遣明船派遣主体としては、細川氏と大内氏が有名であるが、特に両氏が朝貢の入関手続きの先後を争奪して起こした寧波の乱(1523年)を経て、以後の遣明船経営権は大内氏に認められることになり、その後、天文7(1538)年と同16(1547)年出発の遣明船は、有効勘合を集約した大内義隆による独占派遣となり、大内氏は経済的富強化を誇るとともに、中国地方から北部九州にかけて広大な領国を有する大大名へと成長した。もし、義隆がその後、不慮の死を遂げることがなかったら、『天下統一』は大内氏によって成し遂げられていたかもしれない」。この指摘には、腰が抜けるほど、びっくりしました。
「1550~60年代に、戦国諸大名のなかでいち早くポルトガル国王やローマ教皇との外交関係の締結に成功した大友義鎮(宗麟)の名は、日本国内の『天下統一』競争において島津氏との軍事競争に敗北し、豊臣政権傘下に組み込まれてやがて次代には改易されるという歴史を歩んだにもかかわらず、ヨーロッパにおいては、彼らの布教活動や国家政策を成功裏に導いた東アジアの外交パートナーとして、大きな評価をもって紹介されていった。あたかも、日本国から独立した『BVNGO』国とその国王が存在するかのような数々の地図や記録の存在は、一見、日本国内の実情を知らないヨーロッパ人の誤解と誤認の産物として片付けられがちである。しかしながら、実のところ、この一人の人物に対する東西での歴史的評価のねじれこそは、国内情勢のみを眺めた際に導かれる日本史の史実たるものが、必ずしも世界情勢全体の歴史文脈における史実に合致するわけではないことの証左なのである」。世界史的な視点の必要性を痛感しました。
歴史に関心を抱く者にとっては必読の一冊です。
