脳を操るトキソプラズマがホモ・サピエンスの脳内にも入り込んでいる・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3646)】
埼玉・さいたまの秋ヶ瀬公園での自然観察会に参加しました。不鮮明だがアオゲラ(写真1~3)、巣材をシュロから齧り取ったハシブトガラス(写真4)、獲物を捕らえたトビ(写真5~7)をカメラに収めました。ヤドリギ(写真8~11)の実が好物のヒレンジャクに再会できるのではと期待したが、今年はやって来なかったとのこと。ソメイヨシノ(写真12)が咲いています、シュロ(写真13~18)が群生しています。シュロには雌株(写真15~18)と雄株がある由。因みに、本日の歩数は17,152でした。


















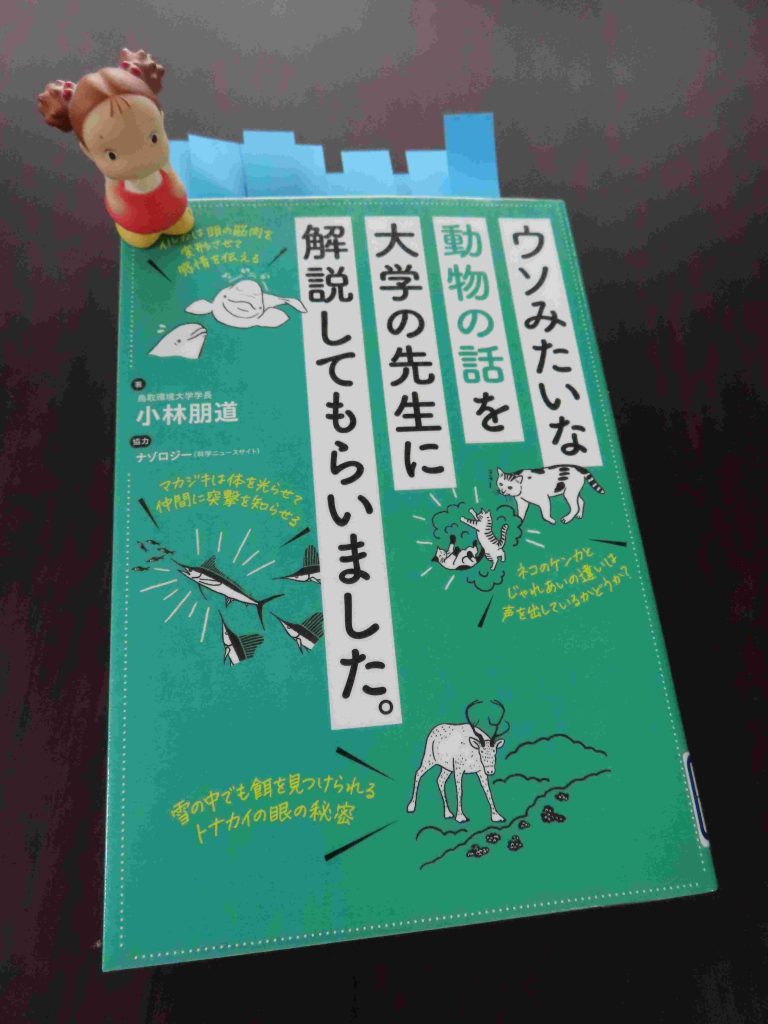
閑話休題、『ウソみたいな動物の話を大学の先生に開設してもらいました。』(小林朋道著、ナゾロジー協力、秀和システム)で、とりわけ興味深いのは、●動物は、お互いの顔が分かっている、●薬草で怪我を治すオランウータン、●脳を操るトキソプラズマがホモ・サピエンスの脳内にも入り込んでいる――の3つです。
●動物は、お互いの顔が分かっている
動物が群れの中の他の個体を識別していることは、さまざまな種で明らかにされています。とりわけ驚かされるのは、アフリカゾウは互いに「名前」(パターン化された一まとまりの音の連鎖)で呼び合っていることです。
●薬草で怪我を治すオランウータン
オランウータンだけでなく、他種のさまざまな動物も、自分以外の種の生物の体の一部を自分の体に塗り付けて、自分の利益に結びつけていることが知られています。例えば、ネコ科の動物はマタタビに体をこすり付けて、蚊を寄せ付けないようにしています。
●脳を操るトキソプラズマがホモ・サピエンスの脳内にも入り込んでいる
トキソプラズマという原虫は、中間宿主の体内、特に脳内にいるとき神経系の状態にさまざまな影響を与えることが研究の結果、分かってきました。脳を操作していると言えるでしょう。よく知られている例だが、ネズミ類の脳内に入り込んだトキソプラズマが、本来ならばその匂いを嗅いだらそこから離れる「ネコの尿」の匂いを逆に好むようにさせるため、そのネズミはネコに食べられてしまいます。ネズミが食べられることによって、トキソプラズマは最終宿主であるネコの体に到達することができるのです。
衝撃的なのは、このトキソプラズマが、3人に1人くらいの割合で、我々ホモ・サピエンスの脳内にも入り込んでいるというのです。正確には、トキソプラズマが「シスト」と呼ばれる休眠中の蛹のような状態になっているそうです。
