松本清張のおかげで、二・二六事件の全体像を俯瞰することができた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3802)】
ハス(写真1~3)、テキサス・セージ(学名:レウコフィルム・フルテスケンス。写真4、5)、ミソハギ(写真6)が咲いています。オシロイバナ(写真7~11)が芳香を漂わせています。パンパス・グラス(和名:シロガネヨシ。写真12、13)の穂が風に揺れています。


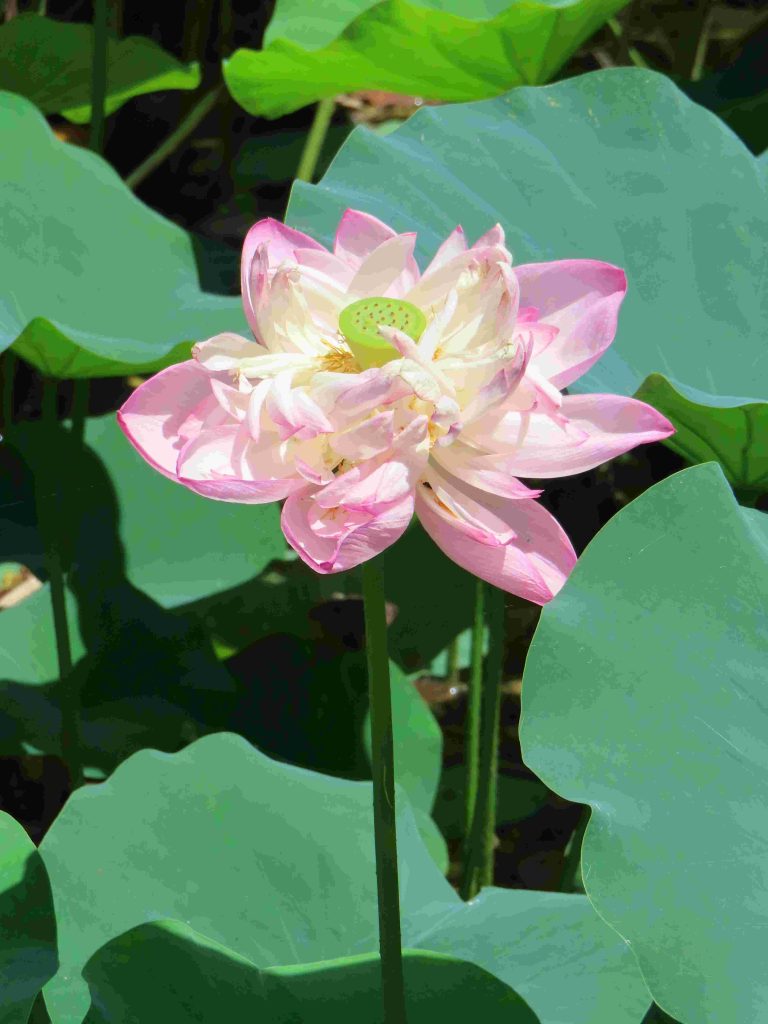











閑話休題、『昭和史発掘(5)~(9)』(松本清張著、文春文庫)の5冊で扱われているのは、二・二六事件です。
●6カ月後の二・二六事件の誘因の一つとなった1935年8月12日の相沢事件――相沢三郎陸軍歩兵中佐が永田鉄山陸軍省軍務局長(少将)を白昼、斬殺――は、なぜ起こったのか。
斬殺直後の相沢の言葉――<永田閣下に天誅を加えてきました>。
●相沢が心酔した真崎甚三郎教育総監(大将)を頂点とする皇道派と、永田が率いる統制派との陸軍内部の勢力争いとは、いかなるものか。
●二・二六事件の中心人物――歩兵第三連隊の安藤輝三陸軍歩兵大尉、歩兵第一連隊の栗原安秀陸軍歩兵中尉、近衛歩兵第三連隊の中橋基明陸軍歩兵中尉、免官となっている磯部浅一(免官前は陸軍主計大尉)と村中孝次(免官前は陸軍歩兵大尉)ら――は、なぜ、1936年2月26日に蹶起したのか。
磯部の「行動記」の一節――<いよ〱発(はじ)まつた。・・・勇躍する、歓喜する、感慨たとへんにものなしだ。・・・余の筆ではこの時の感じはとても表し得ない。とに角云ふに云へぬ程面白い。・・・あの快感は恐らく人生至上のものであらふ>。
斎藤一郎元特務曹長の談話――<兵隊たちは何も知らず、本心から明治神宮参拝と思っていた>。
●拳銃で撃たれた上、軍刀で切り刻まれた高橋是清蔵相。夫人の機転で一命を取り留めた鈴木貫太郎侍従長。女中部屋に潜んで助かった岡田啓介首相――彼らの運命を分けたものは何か。
●皇道派を率いた真崎とは、どういう人物か。
磯部の「行動記」に記載された真崎の言葉――<とう〱やつたか、御前達の心はヨヲッわかつとる、ヨヲッわかつとる>。
事件後、「同志を『裏切った』真崎甚三郎大将に対して磯部は、反感と憎悪を抱いている」。
叛乱青年将校らは銃殺刑になったが、真崎は無罪。
●石原莞爾陸軍参謀本部作戦課長(大佐)は、二・二六事件にどう対応したのか。
「石原は、決行部隊に対して『説得』ではなく、はじめから『鎮圧』の態度だ。この朝、事件を知り逸早く官邸に駆けつけたのは、川島陸相の態度を懸念したからである」。「当時の石原は一大佐ながら全陸軍を背負って立つような風があり・・・」。
●昭和天皇は二・二六事件にどう対応したのか。
「天皇は決行部隊を当初より許さなかった」。
昭和天皇の言葉――<朕ガ股肱ノ老臣ヲ殺戮ス、此ノ如キ兇暴ノ将校等、其精神ニ於テモ何ノ恕スベキモノアリヤト仰セラレ>。<朕自ラ近衛師団ヲ率ヒ、此ガ鎮定ニ当ラント仰セラレ>。
●叛乱青年将校らの蹶起が失敗に終わったのは、なぜか。
●二・二六事件には関与していないのに、叛乱青年将校らに強い感化を与えたとして、『日本改造法案大綱』を著した北一輝と、その弟子・西田税が銃殺刑に処されたのはなぜか。
「北が一方に革新運動を青年将校らにすすめ、一方ではその情報を送って独占資本から金をとっていた行為は、青年将校からは明瞭に察知されなかった」。
「北一輝の思想的生涯は未熟と浮動の一語に尽きる」。
● 昭和天皇の弟・秩父宮は二・二六事件に関係していたのか。
「秩父宮は士官学校の校庭で西田ら同期生と何回か会い、そのつど彼らの革新意見を傾聴している。西田らからそこに誘われるだけの反応を秩父宮は示していたのである」。「秩父宮に歩三の安藤輝三大尉が接近していたことは事実」。「秩父宮は歩三のころ、安藤大尉を偏愛した」。
「皇太后(大正天皇の妻、昭和天皇・秩父宮の母)は秩父宮を溺愛していたという通説がある」。
●二・二六事件後の日本は、いかなる道を歩んだか。
「軍部は、絶えず『二・二六』の再発をちらちらさせて政・財・言論界を脅迫した、かくて軍需産業を中心とする重工業財閥を抱きかかえ、国民をひきずり戦争体制へ大股に歩き出すのである。この変化は、太平洋戦争が現実に突如として勃発するまで、国民の眼には分らない上層部において静かに、確実に、進行していた。天皇の個人的な意志には関係なしに」。
●本筋からは外れるが、松本清張の山下奉文陸軍省軍事調査部長(少将)に対する痛罵が印象に強く残りました。「山下は責任のない場所ではきわめて大胆な放言をする。・・・山下奉文は青年将校に阿っていた小心な男だった。あの巨躯や風丰(ふうぼう)などに世間はごまかされている。外見と中見は別である。・・・出世主義の機会主義者(オポチュニスト)である」。「山下はその巨躯を買いかぶられ、自分でもそれを気どって日ごろ豪放なことを云っていたが、実は狡猾な官僚主義者であった」。
●『昭和史発掘(5)~(9)』を読み終えて感じたことは、その死により未完に終わった清張最後の小説『神々の乱心』との関係です。『神々の乱心』では、『昭和史発掘』で発掘した膨大な資料に基づき、二・二六事件と秩父宮の関係、秩父宮を溺愛した母・貞明皇后と昭和天皇の確執が生々しく描かれているからです。
