劉備、関羽、張飛は商人の用心棒だった、劉備と諸葛亮の人間関係は微妙だった・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3812)】
シルエットだが、オオシオカラトンボの雄(写真1)をカメラに収めました。ヘクソカズラ(写真2)が咲いています。ハナミズキ(写真3)が実を付けています。




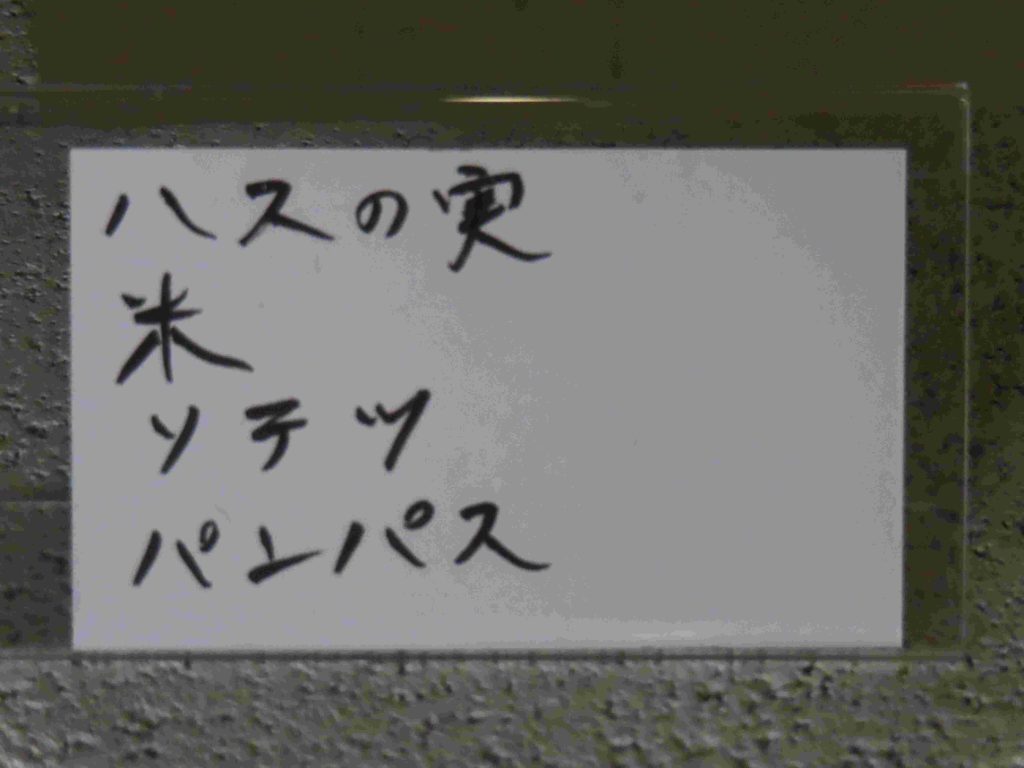
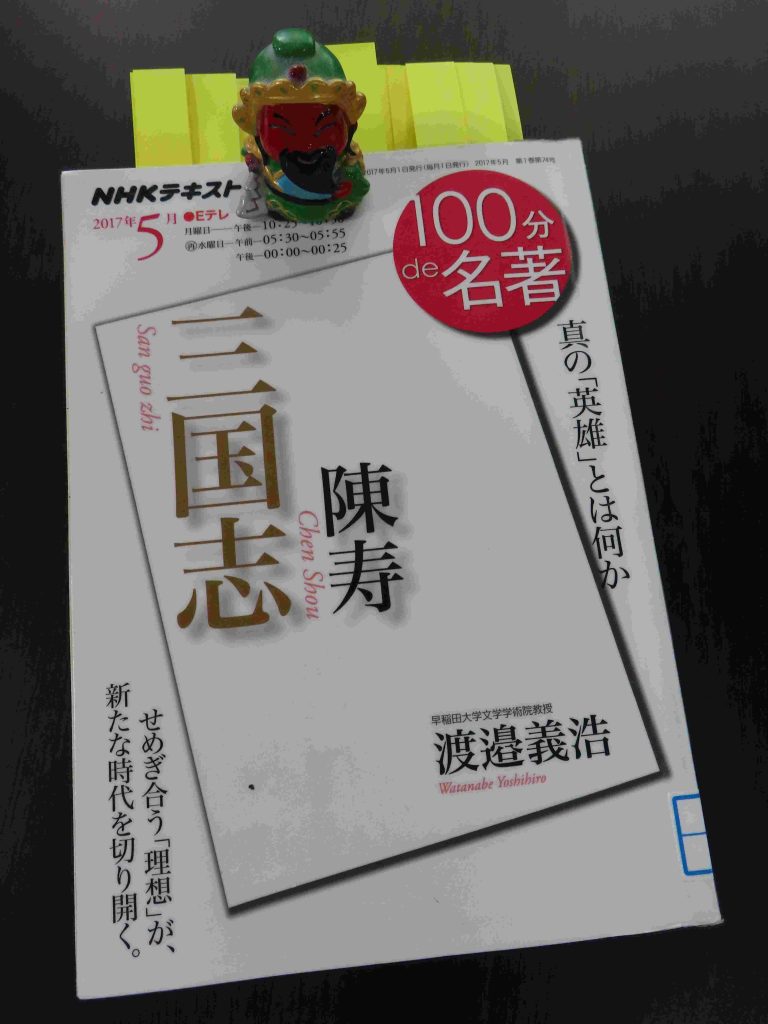
閑話休題、『陳寿 三国志――真の「英雄」とは何か』(渡邉義浩著、NHK出版・NHK 100分de名著)には、驚くことが書かれています。
●正史『三国志』の著者・陳寿は、晋の官僚であった一方で、実は元蜀臣でもあった。263年、蜀は魏によって滅ぼされ、陳寿は亡国の民になり、その後、魏を滅ぼした晋に仕えたのである。それゆえ、陳寿の蜀に対する微妙な心情が『三国志』に反映しているというのだ。
●陳寿は、曹操を「並外れた人物で、時代を超えた英傑」と評している。実際に、曹操の土地制度政策が400年後の隋・唐帝国の基本となっていくわけだから、その視野の広さや規模の大きさは、まさに時代を超越した英雄と言える。
●劉備は、実際には練達した戦闘技術で乱世に台頭した人物であった。曹操は劉備を、「今、天下で英雄と言えるのは君と私だけだな」と高く評価している。挙兵前には、関羽が塩商人の用心棒であったのと同じように、同郷の劉備と張飛は馬商人の用心棒だったのではないか。
●劉備は非常にカリスマ性のある人物だったが、将来性、大局的な戦略、指針が欠けていた。それを補ったのが諸葛亮だった。
●『三国志演義』などでは、劉備が諸葛亮を「受信」していたかのように描かれているが、実際に劉備が「受信」していたのは、非常に有能ながら、諸葛亮とそりの合わない人物(法正)だった。劉備も諸葛亮も互いを必要とし、原則的には協力関係にあった。現代の卑近な事例でいえば、叩き上げの創業者と中途入社で功績の大きなエリートは、互いを認め合っているものの、人事の方針が異なり、時に対立関係が生じたりするようなものだ。劉備の遺言と諸葛亮の出師表に、二人のその微妙な人間関係が滲み出ているというのだ。
●諸葛亮の軍事指揮官としての能力は、もちろん『三国志演義』が描くような天才軍師ではないが、魏に比べ遥かに劣勢という不利な条件の中で、『孫子』に基づいた理性的な用兵により最大限の健闘を果たしたと評価できる。
何度も目から鱗が落ちる思いをさせられた一冊です。
