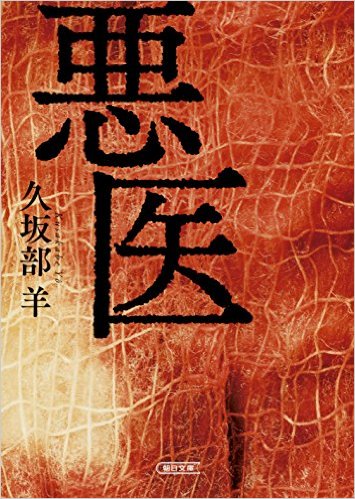死について、末期がんについて、末期医療について考えさせられる小説・・・【薬剤師のための読書論(23)】
『悪医』(久坂部羊著、朝日文庫)は、末期がんを巡る患者と医師の深刻な物語である。
「患者は52歳の男性。2年前に早期の胃がんの手術を受け、11カ月後に再発して、肝臓への転移が見つかった。医師は35歳の外科医。2年前に手術をした早期の胃がん患者が、11カ月後に再発して、肝臓への転移が見つかった」。
「医師が手を替え品を替えて治療しても、がんは徐々に進行し、病勢を増す。そのうち治療の効果より、副作用のほうが強くなる。そうなれば、治療をしないほうが命が延びる。この患者もあれこれ治療を行った後、がんが肝臓から腹膜に転移して、ついに使うべき薬がなくなった」。
「医師は沈痛な面持ちで、患者に告げる。『残念ですが、もうこれ以上、治療の余地はありません』。・・・『もうつらい治療を受けなくてもいいということです。残念ですが、余命はおそらく3カ月くらいでしょう。あとは好きなことをして、時間を有意義に使ってください』」。
「この若造の医者は何を言うのか。余命は3カ月? あとは好きなことをして、時間を有意義に使えだと・・・? つらい治療に歯を食いしばり、吐き気やだるさに耐えてきたのは、どんなに苦しくても、死ぬよりましだと思ったからだ。それなのに、治療法はもうないと言うのか。ふいに胸に激情が込み上げた。『先生は、私に死ねと言うんですか』」。
やり場のない怒りに駆られ、席を蹴って立ち上がった患者・小仲辰郎(印刷工)は、絶望して外来の診察室を飛び出す。
「(三鷹医療センターの医師)森川(良生)が疑問に思うのは、抗がん剤ではがんは治らないという事実を、ほとんどの医師が口にしないことだ。それはあたかも当然すぎて、今さら言う必要もないと思われているかのようだ。医師が目指すのは、がんの縮小や腫瘍マーカーの低下、すなわち延命効果でしかない。がんを治すことなどはじめから考えていないのだ。しかし、大半の患者は、抗がん剤はがんを治すための治療だと思っているだろう。治らないとわかって薬をのむ人はいない。この誤解を放置しているのは、ある種の詐欺ではないか。しかし、医師は反論するだろう。自分たちは『効く』とは言っても、『治る』とは言っていない、患者が勝手に誤解しているだけだと。では、なぜ医師は事実を明かさないのか。それは患者を絶望させたくないからだ。そうやって患者の気持を思いやるふりをしながら、本音では医療の限界を認めたくないという気持もある。がんは治らないと認めることは、敗北宣言であり、自己否定にもつながるのだから」。初期のがんならともかく、末期がんについては、残念ながら、森川の呟きを認めざるを得ないだろう。
「自分は治る。ぜったいに治ってみせる。そして、三鷹医療センターのあの最悪の医者の鼻をあかしてやるのだ。治療法がないなんて、簡単におれを見放したあの野郎に、目にもの見せてやる。だが、もし、あいつの言ったことが正しかったら・・・。おれは死ぬのか。この世から消えるのか。恐ろしい。小仲のこめかみに、冷たい汗が流れ落ちる」。
「末期がん患者の治療には、いったいどこまで悩めばいいのか。末期になっても治療を求める患者はあとを絶たない。そして、だれもが貴重な残り時間を、苦しい治療ですり減らす。それが人間の性(さが)と言えばそうかもしれないが、なんとか、道はないものか」。
治療を諦められない小仲は、なけなしの貯金をはたいて、腫瘍内科医のいる病院や、免疫細胞療法を行うクリニックにかかったりするが、結局、思わしい効果は得られない。そして、辿り着いた郊外のホスピスで最期を迎える。
現役の医師の手になる作品だけに、全てのシーンがリアルに描かれている。死について、末期がんについて、末期医療について、いろいろなことを考えさせられる一冊である。