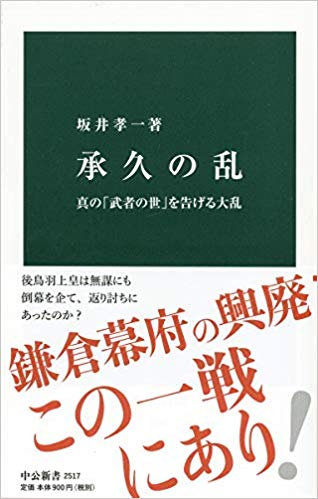源実朝暗殺事件が承久の乱を引き起こした・・・【情熱の本箱(269)】
『承久の乱――真の「武者の世」を告げる大乱』(坂井孝一著、中公新書)によって、私が抱いてきた後鳥羽上皇(院)のイメージ、源実朝のイメージが一変してしまった。そして、実朝暗殺事件が承久の乱を引き起こしたという主張には驚かされた。さらに、実朝暗殺事件の黒幕説をばっさりと切り捨てている。これらの論考が論理的、実証的な手続きを踏んでなされているので、歴史好きには堪らない一冊である。
「後鳥羽の蹴鞠の才能は、音楽の才能同様、後白河の遺伝子によるものだったといえよう。この祖父と孫にはいくつもの共通点が指摘できる。ともに好奇心旺盛で、既成概念にとらわれない自由さと遊び心を持っていた。記憶力も抜群であり、今様にしろ和歌にしろ一度覚えると、二度と忘れなかった。芸術家にしてプロデューサー、おまけにスポーツマンという点も同じである」。
「学問・政治においても後鳥羽は巨人であった。宮廷儀礼の復興を領導したのである」。
「後鳥羽が院政を主宰している時期、間違いなく朝廷は光り輝いていた。しかし、光あるところには必ず影もある。エネルギッシュな帝王が猛スピードで走らせる巨大な機関車に乗り遅れ、あるいは乗車を拒まれ、あるいは自ら乗ることを拒否した人々もいた」。
「鎌倉幕府の将軍でありながら和歌や蹴鞠などの公家文化に耽溺し、『金槐和歌集』を編んだ天才歌人。ただ、それがゆえに荒々しい東国武士の中では孤立した存在。また朝廷と幕府、源氏と北条氏の狭間で苦悩し、若くして甥に殺された悲劇の貴公子。源実朝というと、一般的にはこうしたイメージが強いのではないだろうか」。
「成人後の実朝は将軍親裁を推進し、後鳥羽の朝廷と実朝の幕府は良好な関係にあった。執権北条氏といえども、将軍権力の前には表立った反抗はできなかった。実朝が朝廷と幕府、源氏と北条氏の狭間で苦悩したというのも先入観に基づくイメージである」。
「実朝は、統治者としても次々と政策を打ち出し、成果をあげた」。
「『吾妻鏡』によれば、実朝は建暦元(1211)年の7月から11月にかけて『貞観政要』を学んだという。『貞観政要』とは唐の太宗と群臣の問答録で、後鳥羽も学んだことがある帝王学の教科書である。実朝はこのような地道な努力を積み重ね、擁立された将軍から御家人たちの上に君臨する将軍へと自立し、その権威と権力で御家人たちを従えていたのである」。
「父頼朝や兄頼家と違い、実朝は妾つまり側室を持とうとしなかった。・・・何らかの理由で実朝は自分に子供ができないと考えていたようである。・・・実朝の官位上昇による将軍親裁強化を阻止しようとする執権側、親裁強化のために将軍派閥形成の必要性を直感した将軍側、という構図を読み取ることができる。ただ、唐船建造は失敗に終わり、将軍親裁に汚点を残してしまった。ところが、実朝は起死回生の策を打ち出す。構想は『子孫あへて之を相継ぐべからず』と考える実朝が、以前から温めてきたものと思われる。それは、実朝の後継将軍に親王(後鳥羽の皇子)を請来するという策であった」。
「尊敬する亡父(源)頼朝と同じく王権を意識し、また自分に子供ができないと自覚した実朝にとっても、名付け親であり政治・文化の模範である後鳥羽の皇子を将軍に推戴し後見するという策、つまり王権という公家政権の伝統的権威を新興の武家政権に取り込み、幕府をいわば『東国の王権』として発展させるという策は大きな利益をもたらすものであった。将軍職を親王に譲ってその後見になれば、後鳥羽が譲位して自由を謳歌したように、実朝も前将軍の権威を保ちつつ、将軍が果たすべき公務から解放され、遠隔地に足を延ばすなどの自由を謳歌できる。頼朝が挙兵の10年後に上洛して後白河や九条兼実と会談したように、実朝も上洛して後鳥羽や順徳、御台所の兄坊門忠信ら院近臣たちと対面し、和歌談義に花を咲かせ、朝幕の友好関係を進展させることも夢ではない。いわば、実朝による『幕府内院政』である」。
「(後鳥羽にとっても)今や我が子を将軍に据え、実朝に後見させることによって幕府をコントロール下に置き、実世界でも日本全土に君臨する帝王となる道が開けたのである」。
「(二代将軍源頼家の遺児、実朝の甥・公暁にとっては)親王将軍が推戴され、右大臣実朝が後見するとなれば、自らの将軍への道は閉ざされる。そうなる前に殺すしかない。いつやるか。別当を務める鶴岡八幡宮の境内、自分のテリトリーに実朝がやってくるその時だ。追いつめられた公暁がそう考えたとしても不思議ではない」。
「(実朝暗殺時)命拾いした(北条)義時こそ実朝暗殺の黒幕だったとする説が唱えられるようになった。ただ、後継将軍構想を実朝と一緒に進めてきた義時が、ここにきてすべてをご破算にする行動を取るはずもない。北条義時黒幕説は成り立ち得ない。また、公暁の乳母夫三浦義村を黒幕とみる作家永井路子氏の説もある。公暁の門弟駒若丸は義村の子、義村自身はこの日に限って姿をみせていない。永井氏は、実朝・義時の殺害を公暁に任せ、義村は北条氏の小町邸を襲う『大勝負』に出ようとしたのではないかとする。しかし、これを察知した義時が小町邸に戻ったため、公暁を切り、身を守る選択をしたというのである。魅力的な説ではあるが、『吾妻鏡』の義時に関する記述を論拠にした点に難がある。義時は小町邸に戻っていないのである。また、義村の姿がこの日みえないのは、前年の直衣始の儀で長江明義とトラブルを起こし、右大臣拝賀のメンバーから外されたからだと考える。和田合戦のような北条氏を潰す絶好の機会においてすら義時に味方した義村である。右大臣拝賀の儀で『大勝負』に出るとは考えにくい。三浦義村黒幕説にも無理がある。雪の日の惨劇(=実朝暗殺)は、追いつめられた公暁のほぼ単独の犯行と考えるしかない」。著者のこの説得力ある主張は、私に大きな衝撃を与えた。私は長いこと、永井の義村黒幕説を支持してきたからである。
「一人の若者が犯した凶行は、歴史を動かすほどの重大な結果を生んだ。鎌倉幕府三代将軍、右大臣源実朝、享年28。満年齢にして26歳と5ヵ月半の無惨な死は、それほどまでに人々に衝撃を与えたのであった」。
「建保7(1219)年1月27日の実朝の横死は衝撃であった。当然のごとく、幕府内にはとてつもない悲しみ・怒り・動揺が広がった。・・・(頼朝の未亡人)政子・義時・(大江)広元ら幕府首脳部にとっても、突然の将軍空位は想定外の危機であった。・・・(後鳥羽の)胸中は穏やかではなかったであろう。衝撃・怒り・落胆・悲嘆、様々な思いが渦巻いたのではないか。・・・信頼する実朝を守ることができなかった幕府への怒り、実朝亡き後の幕府への不信感が読みとれる。しかし、幕府も引き下がるわけにはいかなかった」。
承久の乱が勃発し動揺する幕府の御家人たちに向かって、政子が行った名演説が知られている。「鎌倉幕府創設者の未亡人にして二代・三代将軍の生母、従二位という高い位階を持ち、幼き将軍予定者を後見する尼将軍の、聞く者の魂を揺さぶる名演説であった。しかもそこには、(後鳥羽の)北条義時一人に対する追討を、三代にわたる将軍の遺産『鎌倉』。すなわち幕府そのものに対する攻撃にすり替える巧妙さがあった」。
後鳥羽が義時追討を目論んだ承久の乱は、後鳥羽側が大敗を喫する。その敗因は何か。「鎌倉方が驚天動地の想定外の事態の中で、『チーム鎌倉』として結束力・総合力を十二分に発揮したのに対し、あらゆる意味で巨大な存在であった後鳥羽が独断専行する京方は、『後鳥羽ワンマンチーム』としての力しか発揮できず、帝王にありがちな武士に対するリアリティの欠如といった弱点が、そのまま京方の弱点として露呈した」のである。「その結果、杜撰でも楽観的でもなかったはずの後鳥羽の戦略にほころびが生じ、先手を打ったにもかかわらず、逆に劣勢に立たされることになった」と、著者は分析している。
「『吾妻鏡』で注目すべきは、後鳥羽が今回の大乱を『叡慮』からではなく『謀臣』の企みで起きたと主張した、としている点である。帝王の責任回避、家臣への責任転嫁を図ったものである。(院御所で討ち死に覚悟の籠城戦を行いたいと奏上したのに、後鳥羽から)門前払いを受けた三浦胤義らが失望し憤った無責任な姿勢である。しかし、所詮、帝王とはこのようなものである」。
「幕府による戦後処理の中で、人々が衝撃を受けたのはいうまでもなく後鳥羽の隠岐配流であった。人並みはずれたマルチな才能を持った文化の巨人であり、誰もが認める強大な権力と権威によって君臨した帝王が、武家の力によって、都から遠く離れた孤島へと流されたのである。人々の衝撃は現代の我々の想像を絶するものであったろう。ただ、歴史的にみて、より注目すべきは、新たな天皇と院を幕府が決定したことである。院政期、天皇を選定する人事権は治天の君が握っていた。ところが、その治天の君が幕府によって流罪に処されるという前例のない異常事態が起きた。そのため、圧倒的な勝利を収めた幕府の前に、王家・摂関家・公卿たちの合議は全く機能せず、天皇・院の人事権を幕府に握られてしまったのである」。
「古代半ば、10世紀の延喜の聖代に軍事貴族として武士が誕生してから300余年、中世初頭、11世紀末に院政が始まってから135年、『武者の世』が到来したと人々が感じた保元の乱から65年、『真の武者の世』は承久3年に始まったのである。承久の乱とは、それほどまでに『画期的な大事件』であり、大きな意味を持つ歴史の転換点であった」。
本書は新書版だが、内容が充実しているので、今後、長く読み継がれていくことだろう。