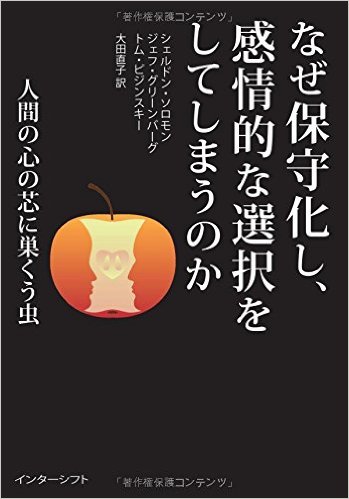死の恐怖にどう対処すべきか――本書を読んで、自分なりの覚悟ができた・・・【情熱的読書人間のないしょ話(183)】
私は、日本語で書かれた書籍であれ、翻訳書であれ、書名には滅多に拘らない人間であるが、本書のタイトルは読者に内容を誤認させるのではないかと危惧している。
『なぜ保守化し、感情的な選択をしてしまうのか――人間の心の芯に巣くう虫』(シェルドン・ソロモン、ジェフ・グリーンバーグ、トム・ピジンスキー著、大田直子訳、インターシフト)は、政治的・社会的な保守化傾向をテーマとしたものではなく、人間として避けることのできない死の恐怖にどう対処すべきかを、「恐怖管理理論」に基づいて論じた著作である。
「いまや恐怖管理理論は心理科学者だけでなく他分野の学者によっても広く研究されており、(アーネスト・)ベッカーの想像をはるかに超えた結果が次々と生み出されている。ウィリアム・ジェイムズが1世紀前に提唱したように、死はまさに人間のありようの芯に巣くう虫であることは、いまやきちんと証明されている。私たち人間は死ぬという自覚は、人生のほぼあらゆる領域で思考、感情、そして行為に、深く広い影響をおよぼす――意識にのぼっていようがいまいが」。
「(私たち人間は)自分は何をしようと遅かれ早かれ死との闘いに負けることを知っている。そう考えるとひどく不安になる。死ぬのが怖いのは、自分の体が腐り、悪臭を放ち、塵になるからかもしれない。愛する人を残して去ることになるからかもしれない。大切なことをやり残すことになるからかもしれない」。
「私たち人間は自分が存在することを知っているからこそ、いつの日か存在しなくなることも知っている。死はいつ来てもおかしくないし、私たちはそれを予測することも止めることもできない。これは明らかにうれしくないニュースだ。たとえ運よく毒虫や噛みつく獣、ナイフや弾丸、飛行機の事故や自動車事故、がん、地震による攻撃をかわせたとしても、永遠には生きられないことを、私たちは理解している」。
「このたえずつきまとう、身のすくむような潜在的恐怖は、人間のありようの『芯に巣くう虫』である。この死に対する恐怖を管理するために、私たちは自己防衛しなくてはならない」。これが、恐怖管理理論の基本的な考え方である。
本書の最重要箇所は、当然のことながら、私たちは死の恐怖にどう対処すべきかを論じた部分である。
著者の結論は、こう記されている。「死を受け入れよう。死すべき運命にあることは恐ろしい反面、だからこそ人は勇気と思いやりと将来世代への気遣いにあふれ、だからこそ人生が崇高なものにもなることを、きちんと理解しよう。意義と価値、社会的つながり、精神性、個人的成果、自然との一体感、そしてつかの間の超越経験を、あなたなりに組み合わせて、変わることのない意義を求めよう。そのための道筋を示しながら、不確実なことや異なる信念を抱く人たちへの寛容さを促す、そんな文化的価値観を推進しよう」。
「あなたは恐怖から行動しているのか、それとも他人によってそうするように操られているのか? かたくなな防衛機制に突き動かされているのか、それとも人生で心から大切にしている目標を追いかけているのか? 他者に対応するとき、死の恐怖を管理しようとする努力がどれくらい彼らの反応に影響しているか、あなた自身の防衛機制が彼らに対する反応に影響しているか、考えているだろうか? このように問いかけ、それに答えることによって、私たちは自分自身の人生の楽しみを広げ、周囲の人々の人生を豊かにし、さらにそれ以上の影響をもたらすことができるだろう」。
正直言って、この優等生的な結論は私にはしっくりこない。
著者は、「論理的根拠をもとに死の不安を取り除こうとするエピクロス派の努力は、今日までみごとに失敗している」と断定しているが、私の心に一番ぴったり合致したのは、エピクロス派の考え方である。
「ルクレティウスを含めたエピクロス派の人たちにとって、この心理的難題を抜け出す方法は単純だ。まず、私たちは自分の抱いている死の恐怖に気づかなくてはならない。次に、死を恐れることは理屈に合わないと認めなくてはならない。エピクロス派の主張によると、結局、悪いことは感じることができる者にのみ起こりうる。死んだ人には感覚がいっさいなく、母胎に宿る前の状態と同じだ。したがって、死んでいることは存在していないのと変わりない。自分が生まれる以前のことを怖がる人はいないのに、なぜ死を思い悩むのか? 私たちの生涯が始まる前の何十億年にわたって支配していたのと、まったく同じ無感覚状態なのだ。ひとたびこのことに気づけば、死の不安はなくなり、私たちは不死を切望しなくなるだろう。エピクロスによれば、これで『人生の死すべき運命がもっと楽しめる』ようになる」。
死の恐怖にどう対処するかは、人によってそれぞれであろうが、私自身は、このエピクロスの考え方に沿って生きよう、そして死を迎えようと、自分なりの覚悟ができた。本書のおかげである。