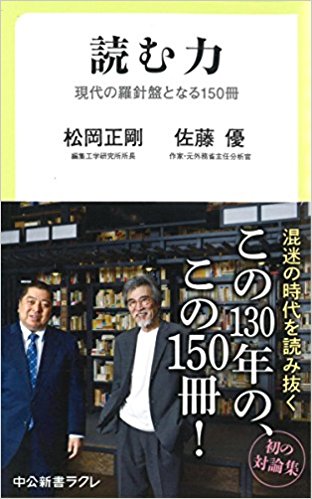松岡正剛と佐藤優の、読書・書評・知のネットワークを巡る血沸き肉躍る対談集・・・【情熱の本箱(233)】
読書の練達の士、松岡正剛と佐藤優の対談集『読む力――現代の羅針盤となる150冊』(松岡正剛・佐藤優著、中公新書ラクレ)を読んで、大きく頷いたことが、3つある。
その第1は、二人の書評に対する姿勢である。
●佐藤=私には書評を書く際に、一つの鉄則があるんですよ。・・・引用のない書評は絶対に書かないことにしているのです。・・・ところが、それをすると、「地の文に直してください」という編集者がときどきいるのです。「佐藤さん、引用が多いです」などと、注文を付ける。しかし、書評で引用するということは、そこでとても重要な判断を下しているわけですよ。言い方を変えると、あえて引用すべき部分を見定めて、それに対して、地の文で自らの論評を加えていくのがフェアで、読者にとっても親切な書評なのではないかと思うのだけれど、それがわからない。地の文のほうがいいのだと思い込んでいるのです。
●松岡=引用とか、あるいは本歌取りとか、転位、デペイズマン(=意外な組み合わせで、受け手を驚かせること)するということは、思想の書き換えに連なる重要な営みにほかなりません。そのときに『本歌』を隠したりすれば、その思想が信用を得るのは難しいでしょうね。
●佐藤=普通の新聞原稿や書評原稿は、その追跡ができないものがあります。この業界に入って感じたのは、逆に、引用のない書評は相当警戒しないといけない、ということです。その手のものには、版元が出すプレスリリースに極めて近いもの、あるいは先行書評に類似しているものが、少なくないわけです。私が必ず引用することにしたのは、そういう胡散臭さと一線を引きたかったのも、大きな理由です。
●松岡=書評をするにしても、私は一介の読み手であり、研究者のような仕事をしたいと思っていないので、例えば丸山眞男や岡潔の著作でもなんでもいいのですが、ある本を褒めようと思ったときに、この本の中に足りないものはいったい何だろう、丸山眞男の中にないものは何だろうと考える。そこから見なければ、新しい丸山眞男も岡潔も見つからない。そんなふうに仕事をしてきたのです。
●佐藤=松岡さんの「千夜千冊」を読んでいる人と、読んでない人では、世界の見え方が変わってくると思います。脱線しますが、あの本は、同じ著者を取り上げないとか、同じジャンルを続けないとか、とても厳しい制約を課しているのがすごい。
●松岡=制約の一つに、ケチをつけないというのもあります。ケチは意外に簡単です。
●佐藤=ケチをつけなくても、伏せること、空白にすることで、わかりますからね。
●松岡=そうなんです。お前はダメだということは簡単なんです。
私も書評を書くに当たっては、最大限、引用することと、貶さないこと――を基本姿勢としている。取り上げた書物の著者が言わんとすることを、引用なしに、書評者が上から目線で小賢しくとりまとめて示すというのは、著者と読者の双方に対する冒涜以外の何物でもないと考えているからだ。栓を開けて放置して気の抜けた炭酸飲料のような書評が、その書物の魅力を台無しにする愚は避けたいからだ。
第2は、互いに対談相手の本質の核心を衝いていることである。
●松岡=実は、僕が最初に佐藤優というのはとんでもない人物だと驚いたのは、大川周明の『米英東亜侵略史』(1942年)を「解読」した、『日米開戦の真実』(2006年)を読んだときだったんですよ。神学とインテリジェンスの専門家だったはずなのに、どうして大川にまで目を向けることができるのかと思った。
●佐藤=松岡正剛氏の頭の中には、独自の樹形図がある。中世神学に「博識に対立する体系知」という格言があるが、1980年代中葉から90年代にかけて、ポストモダンの嵐が(中途半端に)吹き荒れた後、体系知というアプローチに知識人が冷ややかになってしまった。その結果が、現在の閉塞した社会状況を作り出す大きな要因になったと思う。そのような状況で、松岡氏は、編集工学という、知恵と技法が綜合された方法論で、知のネットワークを再構築するという「不可能の可能性」に挑んでいる」。
第3は、世の中に正当に受け容れられているとは言い難い著述家に対する目利きの確かさである。
例えば、副島隆彦、渡部昇一、唐木順三、松本清張、鈴木邦男などに対する透徹した評価が挙げられる。