エピクロス、モンテーニュ、ハイデッガーの「死」に対する考え方は哲学失格だというのか・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3575)】
キンカン(写真1)が実を付けています。ジンチョウゲ(写真2)が蕾を付けています。我が家の庭の常連のメジロ(写真4)、シジュウカラ(写真5~7)、スズメ(写真8)。








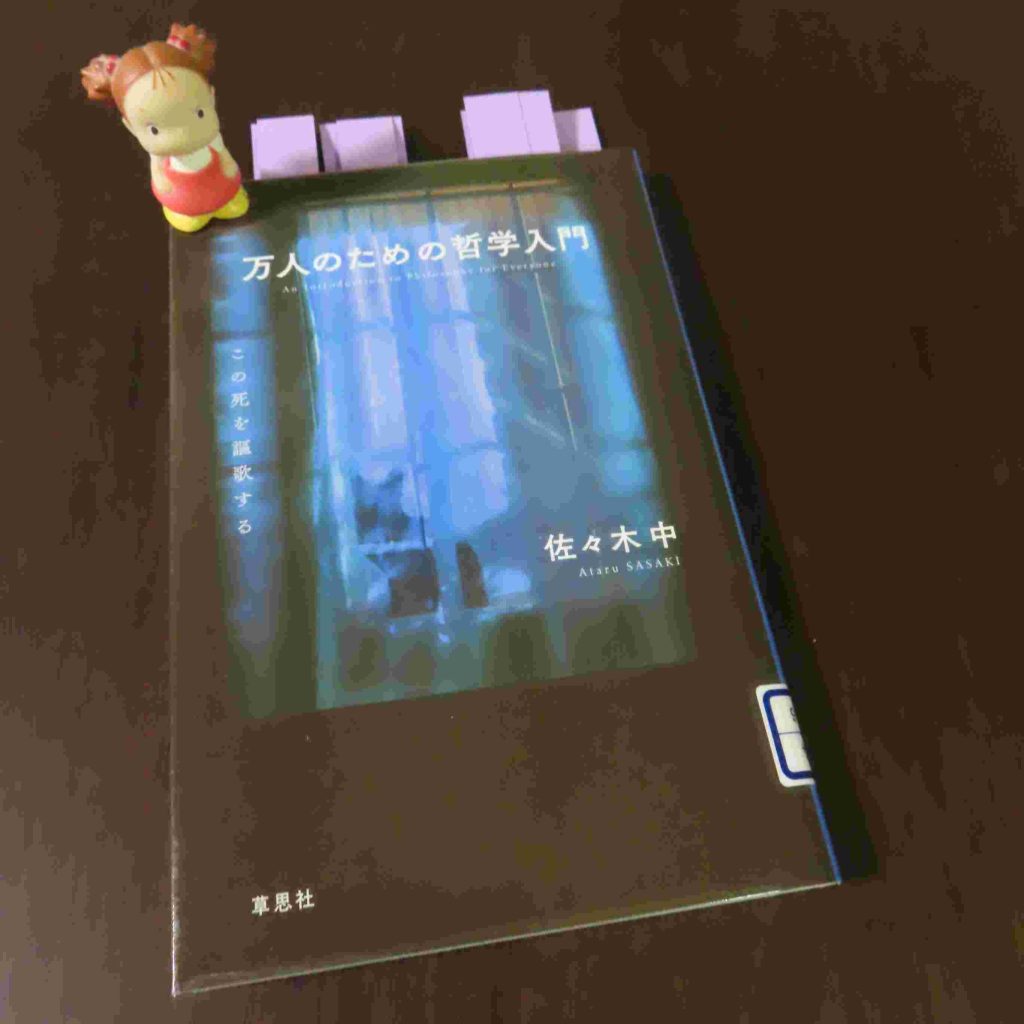
閑話休題、哲学の最重要テーマは「死」だと私は考えています。『万人のための哲学入門――この死を謳歌する』(佐々木中著、草思社)の著者も同じ考えの持ち主のようなので親近感を覚え、本書を手にしました。
●哲学失格
ソクラテスは「哲学は死の練習」、モンテーニュは「哲岳は死を学ぶこと」、エピクロス、スピノザ、ニーチェは「自分の死を経験することはできない、死んだ時には自分はいないのだから、死を恐れる必要はない」と言った。こういう死から目を背ける態度こそ、哲学失格と言わざるを得ない。
●安売り
死ぬことは確実であって、生は限りあるものだからこそ生は価値があり、死の自覚があるからこそ「生き生きと」生を生きることができるのだ、という理屈は、薄められていくらでも安売りされている。
●通り道
死の確実性から有限性の自覚へ、そこから「跳躍」して大いなる大義や偉大なる国家のために死ぬこと、という危険な通り道があり得る。
●忘却
我々は苦労して生きていて、そして無意味に死ぬ。それだけではない、その生き死にを誰も覚えていてはくれない。
●藝術
我々には芸術があり、そこでこの生と死という定めを笑うことを学ぶことができる。この定めを悲劇ではなく喜劇とすることができる。そこから、陽気に、快活に、哄笑しつつ、この定めを生き抜くことができるようになるかもしれない。芸術こそが、「遥か彼方で瞬いてくれる燈火」なのだ。
私は、エピクロスの言葉によって死の恐怖から脱却し、ハイデッガーの言葉によって限りある生を充実させようとしている人間なので、本書の著者とは考え方が異なります。死後に、身近な愛する者以外から忘れ去られようと構わないと考えています。
