自ら新たな「問い」を発しよう、その問いの編集力を鍛えよう・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3587)】
幸運にも、また、ヒクイナ(写真1~5)に出会えました。ヒドリガモの雄と雌(写真6)をカメラに収めました。シロダモ(写真7~9)が実を付けています。









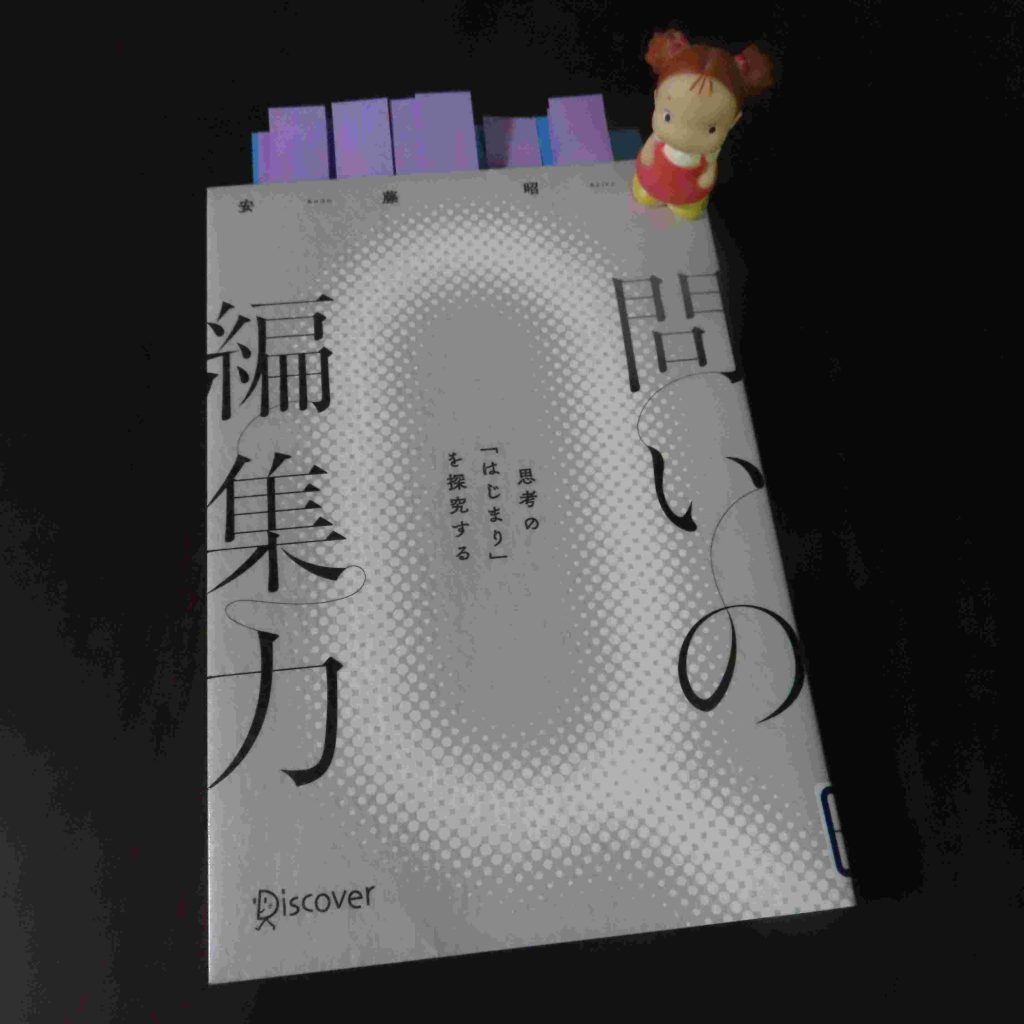
閑話休題、『問いの編集力――思考の「はじまり」を探究する』(安藤昭子著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)の著者が読者に伝えたいことは、私なりに乱暴にまとめると、自ら新たな「問い」を発すること、そして、その問いの編集力を鍛えることが、自らの生を充実させる――ということになるでしょう。
これからの世界において人間に残された創造性は、「問う」ことにあるというのです。
「問う」という行為は、情報を編集することを意味します。
問いの編集力を向上させる具体的な方法が順序立てて提示されているが、私は3つのキーワードに注目しました。
●セレンディピティ
何かに熱心に気持ちを向けていると、思いがけないところから大事な情報が舞い込んでくることがある。こうした偶然を呼び込む力を「セレンディピティ」と呼ぶ。セレンディピティを呼び込むには、「やってくる偶然」をすかさず察知できるだけの豊かな「見方の群れ」が意識の側に満ちている必要がある。
●ネガティヴ・ケイパビリティ
一心不乱の試行錯誤が臨界値に達するタイミングでふいに舞い込んだ偶然は、探究心でふくらんだ風船への針のひと刺しになる。「迎えにいく」準備ができたところで、察知は弾ける。「ああでもないこうでもない」を許容する力、分からなさや答えのなさに耐えるネガティヴ・ケイパビリティが、偶然を味方につけるには必須なのだ。
●アブダクティヴ・ライティング
人の思考や発見は、思うほどに論理的に組み立てられてはいない。「あれ?」と思ったことをきっかけにその違和感の正体を探っていく中で、「そうか、自分はそんなことを感じていたのか」と、漸く自分自身の本心に気がつくことがある。もしくは「そう考えれば、全部説明がつく!」と思えるような、痛快な発見に出会うことがある。これはまさに、アブダクションの道筋だ。この「不確かさを確かさに転じていくアブダクション」のプロセスは、何かを発見したり道理を分かっていく上での「発見の型」として活用することができる。アブダクションのプロセスに沿って文章を組み立てることで、頭の中で考えているだけでは辿り着けない風景に至ることができるのだ。また同時に読み手にとっても、書き手の推論の道筋を追体験することで、臨場感をもって発見に立ち会うことができる。この、ささやかな「驚き」をとっかかりに、まだ見えていない背景を仮説として、ある確かな世界像を描き出していくことを「アブダクティヴ・ライティング」と呼ぶ。
