目から鱗が37回も落ちました・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3830)】
フジバカマとオミナエシ(写真1)、オミナエシ(写真2~4)、クズ(写真5)、ヤマハギ(写真6)、ツリガネニンジン(写真7)が咲いています。カラスウリ(写真8~10)が実を付けています。










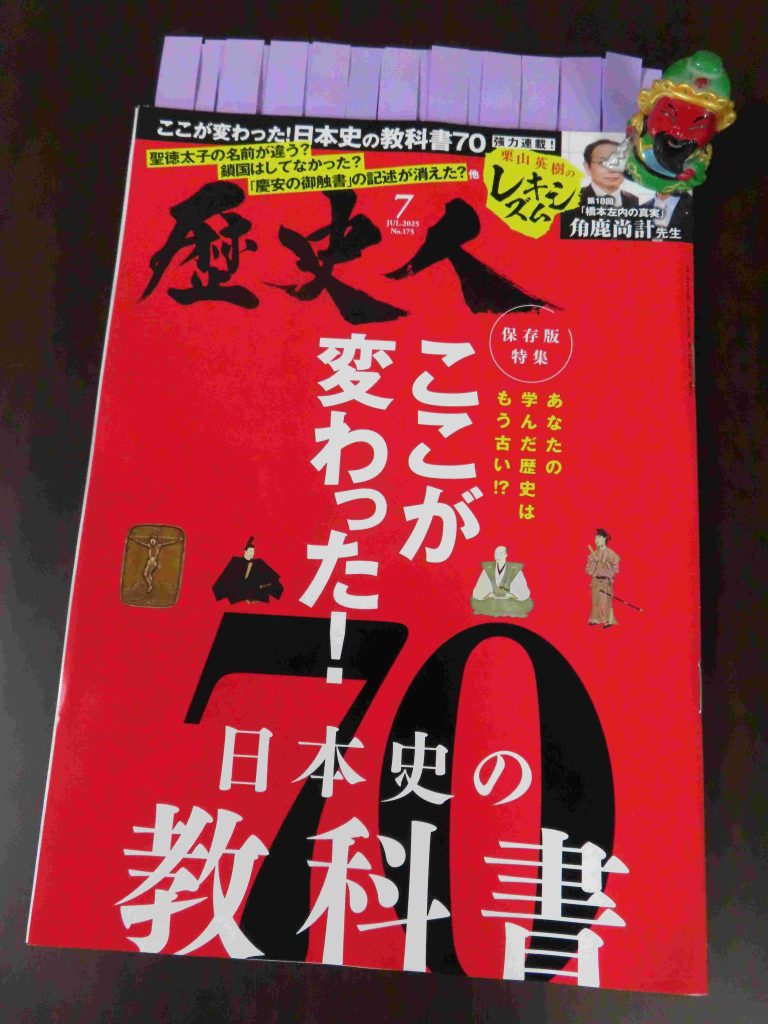
閑話休題、「歴史人 2025年7月号」(ABCアーク)の特集「ここが変わった! 日本史の教科書――あなたの学んだ歴史はもう古い!?」を読んで、目から鱗が37回も落ちました。
【古代】
●【昔の教科書】大和朝廷➡【現在の教科書】「大和政権」「ヤマト政権」「大和王権」「ヤマト王権」などの表記がみられる
●【昔】大和朝廷は朝鮮半島に進出し、まだ小国群のままの状態であった半島南部の弁韓諸国をその勢力下におさめた。これが任那である➡【現在】倭は4世紀には朝鮮半島南部の弁韓地域にあった加耶諸国(加羅)と密接な関係を持ち、鉄資源を確保した
●【昔】名前は「聖徳太子」➡【現在】「聖徳太子」だけでなく「厩戸皇子」という名も併記されるようになった
●【昔】「聖徳太子二王子像」を聖徳太子として掲載➡【現在】「伝聖徳太子像」として扱う
●【昔】「冠位十二階」「憲法十七条」は聖徳太子の業績➡【現在】「冠位十二階」「憲法十七条」は推古朝全体の業績
●【昔】645年、中大兄皇子と中臣鎌足はともに計略を巡らし、蘇我蝦夷・入鹿父子を滅ぼして国政改革に乗り出した。一連の改革を「大化改新」という➡【現在】645年、中大兄皇子と中臣鎌足は蘇我蝦夷・入鹿を滅ぼした。これを「乙巳の変」という
●【昔】反乱鎮圧のために大軍が数度派遣され、征夷大将軍・坂上田村麻呂が東北地方の経略を進めた➡【現在】北上川中流の胆沢地方の蝦夷を制圧しようとしたが、蝦夷の族長・阿弖流為の活躍により政府軍が大敗する事件も起こった
【中世】
●【昔】政治権力の交代を重要視。中世は鎌倉幕府の成立からスタート➡【現在】社会経済の変化を重要視。中世は荘園公領制の変化を画期とする(院政期までさかのぼる)
●【昔】各地で成長した豪族や有力農民が、勢力拡大のために武装して武士になる➡【現在】源氏や平氏などの一族が武芸を職能とし、下向して武士団を形成する
●【昔】『平家物語』にもとづき「源平合戦」と表現➡【現在】幅広い階層を巻き込んだ戦いのため「治承・寿永の内乱」と表現
●【昔】肖像画を、かつては源頼朝像として紹介➡【現在】一時、伝源頼朝像と改められたが、その後、甲斐善光寺所蔵の木造に変更
●【昔】騎馬武者像を、かつては室町幕府を開いた足利尊氏として紹介➡【現在】等持院所蔵の木像に変更
●【昔】「元寇(蒙古襲来)」と表記➡【現在】「モンゴル襲来(蒙古襲来、元寇)」と表記
●【昔】文永の役の元軍は暴風で撤退した➡【現在】文永の役の元軍は戦いによる損害や内部対立もあり撤退
●【昔】後醍醐天皇の挙兵は朱子学の大義名分論を学び政治の刷新を目指した➡【現在】後醍醐天皇は中継ぎの立場だったため、皇位継承を決める幕府を倒そうとした
【戦国時代】
●【昔】戦国時代のはじまりは応仁の乱だった➡【現在】応仁の乱より12年早い享徳の乱が、戦国時代の幕開けとなる
●【昔】掲載した肖像画は、武田信玄、フランシスコ・ザビエルを描いたもの➡【現在】武田信玄は全くの別人。フランシスコ・ザビエルも想像で描かれたもの
●【昔】豊臣秀吉は農民階層の出身であった➡【現在】豊臣秀吉の出自は謎が多いが、足軽クラスの武士階級出身との説が有力
●【昔】「応仁の乱」と呼称➡【現在】「応仁・文明の乱」と呼称
●【昔】北条早雲は伊豆侵攻し足利茶々丸を討ったが、これは下剋上であった➡【現在】北条早雲の伊豆侵攻は幕府による許諾を得たものだった
●【昔】「北条早雲」とのみ呼称➡【現在】「北条早雲」と「伊勢宗瑞」が併記
●【昔】鉄砲はポルトガル人によって日本に伝来した➡【現在】鉄砲は密貿易にたずさわっていた倭寇によりもたらされた
●【昔】漂流したポルトガル船により、種子島に鉄砲が伝来した➡【現在】種子島と同時期、九州など西日本各地にも鉄砲が伝来
●【昔】戦国最強といわれた武田騎馬隊が武田軍の強さの根幹だった➡【現在】武田軍に騎馬隊は存在したが、小規模で戦闘よりも戦場偵察を中心に運用されていた
●【昔】織田信長が考案した鉄砲の三段撃ちで、武田騎馬隊を打ち破った➡【現在】長篠合戦で鉄砲は使用されたが、三段撃ちはなかった
●【昔】斎藤道三は一代で美濃を奪い、戦国大名となった➡【現在】斎藤道三は父と共に二代を通して美濃を奪った
●【昔】比叡山は織田信長により徹底した焼き討ちにあった➡【現在】織田信長の比叡山焼き討ちは一部で、かなりの部分が焼き討ちを免れた
【江戸時代】
●【昔】石田三成が関ヶ原の戦いの西軍盟主として記載される➡【現在】毛利輝元が関ヶ原の戦いの西軍盟主として記載される
●【昔】「鎖国」と明記される➡【現在】「いわゆる鎖国」「のちに鎖国と呼ばれる」などと曖昧に
●【昔】「島原の乱」と表記➡【現在】「島原・天草一揆」と表記している教科書もある
●【昔】生類憐みの令は極端な動物愛護政策であり人々を重い罰則で苦しめた➡【現在】生命や自然を尊重する道徳を民たちに定着させた
●【昔】徳川綱吉は母親・側近の傀儡将軍となり幕府の財政も悪化させた➡【現在】徳川綱吉は文治政治への転換で徳川の平和な時代を築き、後世にも影響を与えた名君
●【昔】江戸幕府の直轄地を「天領」と呼んでいる➡【現在】「幕府直轄領」「幕府領」などと記載されるようになっている
●【昔】田沼意次は賄賂を横行させ幕府の統制力をおとろえさせる悪政を行った➡【現在】田沼意次は幕府財政を再建するため、株仲間の公認・貨幣制度の統一・新田開発などを実施した
●【昔】幕末の幕府外交は砲艦外交に屈した弱腰外交だった➡【現在】幕末の幕府外交は弱腰ではなく、冷静かつ論理的に対応していた
●【昔】日米修好通商条約は不平等だった➡【現在】日米修好通商条約は必ずしも不平等ではなく、関税率は日本に有利だった
●【昔】坂本龍馬らの仲介で、薩摩藩は長州藩と軍事同盟の密約を結んだ➡【現在】坂本龍馬の名前が教科書の削除候補に入る
