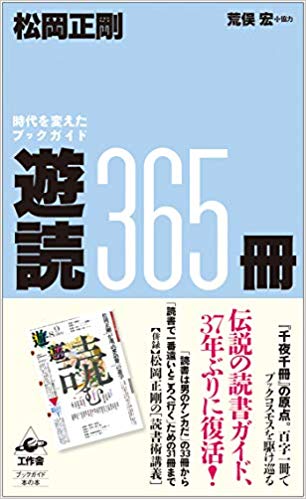読書の達人・松岡正剛は、若き日にどんな本を読み、どう評していたのか・・・【情熱の本箱(256)】
私のような松岡正剛ファンにとって、若き日の松岡がどのような本を読み、どのような本を取り上げ、どのような書評をしているのか――は、非常に気になるところである。この意味で、1981年時点の松岡の書評を俯瞰できる『遊読365冊――時代を変えたブックガイド』(松岡正剛著、荒俣宏協力、工作舎)は、私の好奇心を十分に満足させてくれた。
当時の松岡は、「書物は隙間だらけ、気配によってどうにでも動きまわる『想像上の庭に棲む動物』のように思っていたほうがいい。気温変化だってある」と記している。
「読書はイマジネーションにはじまる」の章に収められている『ねじ式』(つげ義春)は、このように評されている。「1960年代のピークを飾った劇画だ。日本的シュルレアリスムの極北を示す記念碑でもある。『ガロ』に掲載された。・・・あわせて西東三鬼句集なんぞを読みたい」。私はつげも三鬼も好きだが、この二人の世界を結びつけるとは、松岡だからこそ可能な荒業である。
「読書は男のケンカだ」の章では、『アラビアのロレンス』(ロバート・グレーブス)と『中央アジア探検記』(スウェン・ヘディン)の書評に大きく頷いてしまった。「ピーター・オトゥール主演の映画であまりにも有名になったものの、この原作とT.E.ロレンス自身が綴った『知恵の七柱』は、活字のみがもつ精巧な記録的興奮を『内側の必然性』から証してくれる」。「小学生の頃にリヴィングストンの絵本を読んで以来、僕の探検記遍歴は尽きることがない。なかでもヘディンの殺漠たる西域アジア踏破の記録は忘れられない。シルクロード・ブームの原点になった涙ぐましい奮闘記」。
「読書は大いなる遊戯である」の章では、『八犬伝の世界』(高田衛)を挙げねばなるまい。なぜなら、私が『八犬伝の世界』の素晴らしさを実感することができたのは、『千夜千冊エディション 本から本へ』(松岡正剛著、角川ソフィア文庫)で松岡がこの書を高く評価しているのを知り、慌てて手にしたという経緯があるからだ。「馬琴の『南総里見八犬伝』は日本文芸史上最高の伝奇ロマンだ。八犬士の関東幻想大戦を経て里見ユートピア・コミュニティをつくる大構想には不可思議な多神教的シンクレティズムが秘められる。本書はその解明に挑んだ」。
「読書を荒俣宏にまかせてしまう」の章では、『甲子夜話』(松浦静山)と『自然真営道』(安藤昌益)が目を惹く。「かつて中学時代に『随筆事典』の『奇談異聞篇』のなかで拾い読みして以来、今日まで一貫して魅惑されつづけている書物。怪談から世話話、見世物まで、江戸期の断面を活写する聞き書き文芸」。「今は消失した昌益の奇書を今にしのばせる。中央公論<日本の名著>シリーズ『昌益』編に口語訳でおさめられているから、ぜひとも一読をすすめたい。とくに老子、孔子、シャカなどの賢人を奇形児扱いするすごさ!」。
365冊目は、「読書で一番遠いところへ行く」の章の『荘子――内篇・外篇・雑篇』(荘子)となっている。「荘子こそ大いにアナーキーな遊学の人だった。これは読む本ではない。遊ぶようにしてなじむ『流れ』のようなものだ。365冊目においてはあるが、できれば明日にでも手にとってみてほしい。眼と心と体が洗われる」。『荘子』は、まさに、この評のとおりの書である。
「本は世界の波動を封じた玉手箱だということができるかもしれない。存在がとらえた世界の響きが、声となり文字となり、封じられていたものを開くとき、文字が織りなす響きにふれる者は、たちまちその響きをもった存在になる。読んだものは読まれたものにかぎりなく共鳴し、相似た精神の波動をもちながら、時代や場所に応じた色あいを介して、声を発し、音となし、色となし、文字に定着して、再び本として封ずるかもしれない。こうして読まれたものは読んだものになりつづけていくことで、世界そのものにつきあうことになる。そこに読むことの真の興奮があるにちがいない」。こういう読書の本質を鋭く捉えた文章に触れると、本当に興奮してしまう。「玉手箱」は、いかにも松岡らしい譬えだ。