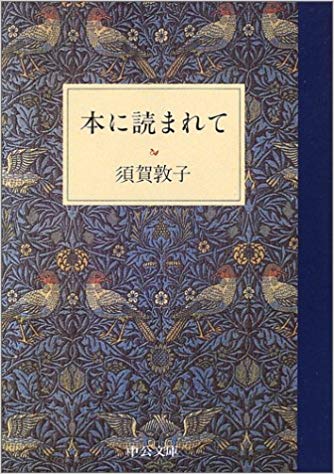須賀敦子が惚れた本たちに、私も惚れてしまいそうだ・・・【情熱の本箱(275)】
『本に読まれて』(須賀敦子著、中公文庫)は、私の好きな作家・須賀敦子の読書体験を覗き見する楽しさを与えてくれる。
須賀がアガサ・クリスティー好きだったとは、意外な感がする。クリスティーの『さあ、あなたの暮らしぶりを話して――クリスティーのオリエント発掘旅行記』が取り上げられている。
「この本は、1934年から38年にかけて、3回にわたって著者が参加したシリアでの発掘調査の冒険にみちた日常についての記録で、調査隊のリーダーは、著者の夫で著名な考古学者でもあった、マックス・マローワン氏。この人物の沈着で的確な判断によっていくつかの危機がつぎつぎと解決されるが、結婚してまもないクリスティーの熱い拍手がきこえるようだ。たとえば夫が選んだマックという『格子縞の毛布と日記帳』しか持ち物のない隊員を最初、著者は『人間的な反応のこれっぱかしもない』男として嫌悪するが、砂漠での日々を平穏に生きるにはその『鈍さ』こそが願ってもない特質だということに気づいて、夫の選択に脱帽するというエピソードは、マックという人物を描きながら、夫の洞察力をたたえるという仕掛けだ。・・・1944年に脱稿し戦後まもなく出版されたらしいが、書かれてから50年ちかく経った本が、これほど身近で生き生きと感じられるのは驚異的だし、クリスティー一流の、とぼけたようでいて、けっこう辛辣なことも平然といってのける語り口、するどい観察眼と文章のちからが読者をぐいぐいひっぱる」。私もぐいぐいひっぱられたくなったので、早速、『さあ、あなたの暮らしぶりを話して』を「読むべき本リスト」に加えた。
書評に触れることによって、これまで自分の知らなかった世界が広がることがある。ミロラド・パヴィチの『ハザール事典――夢の狩人たちの物語』は、そんな本である。「それを読むと一種の化学変化のようなものが自分の中で起きてしまい、すくなくとも何時間か、あるいは何日間か、いや、もしかしたらそのずっとあとまで、物の見方や考え方に微かなずれや歪みが生じるといった本がある。『ハザール事典』もそれに似た毒を秘めていて、小説好きの読書を存分に酔わせてくれる」。
「事典という斬新なかたちをとったこの作品は、幻想的な物語としても、あるいはさまざまな方角から論じられた小説論としても読むことができ」るというのだから、『ハザール事典』も「読むべき本リスト」に加わることになったのは言うまでもない。
須賀の池澤夏樹熱は相当なもので、「いま、私は現代の日本がこのように明晰で心優しい作家をもっていることを、ほこらしく思う」とまで、言い切っている。
「新しい救済の可能性を示唆する物語――池澤夏樹『スティル・ライフ』」は、このように論じられている。「『スティル・ライフ』の導入部で、意表をついた三角形を思わせるこんな文章に出会って、この作家はいったい、どこに読者を連れていこうとしているのかと不思議さにうたれ、さらに数行読むうちに、どこでもいい、ついていこう、と思ってしまう。この小説には、他の多くの池澤作品と同様、そんな魔法が冒頭から仕掛けられているようである」。これまで、池澤の著作はいくつか読んできたものの、彼の小説には関心がなかったが、須賀の通常ではない惚れぶりに影響されて、取り敢えず、『スティル・ライフ』を読んでみることにしょう。つい先日、都立富士高時代の同期生と話していて、池澤が我々の1年後輩だということを知った。
ポール・ボウルズの『シェリタリング・スカイ』も読みたくなってしまった。「愛情と信じられていたものが冷めて、すっかりぎくしゃくしてしまった裕福で知的なアメリカ人夫婦、ポートとキットが、いくつかの行き違いを経てサハラの奥地への旅を企てるのだが、夫のポートは不便な旅先で重いチフスにかかる。フランス軍の駐屯地でやっとあてがわれた倉庫の片隅で過ぎていく、恐怖とあせりに満ちた時間。襲いかかる死の暴力にあらがって正気/人間らしさを失っていく夫をまえにしたキットの底しれない孤独感が許容度を超えたとき、彼女は瀕死の夫を置きざりにして砂漠にさまよい出てしまう。ベルベル人の隊商と出会った彼女は、すくなくとも渇きと飢餓による目前の死からは救われるが、救済と思われたものは、あらたな、しかも決定的な精神の破綻にみちびく罠でしかなかった。苛酷な砂漠の性のかたち。そして自己の存在感が希薄になるほどの光の横溢と漆黒の夜。砂漠。夜がふたたび白んだとき、前日となにひとつ変わることなく行く手によこたわる、金色の砂漠と好物質の青い空」。これは、ベルナルド・ベルトルッチによって映画化された『シェルタリング・スカイ』に対する須賀の評である。
「(原作の『シェルタリング・スカイ』は)久ぶりに出会った読みごたえのある小説だった。この本が読者をつよい感動にさそうのは、この作品がはてしなくひろがる砂漠を背景にした凄絶なラヴ・ストーリーだからというだけでないのはもちろんだ。・・・キットの精神の出口のない漂流に気づいて、背すじに水が走るのを覚えるのは、私だけではないはずだ」。