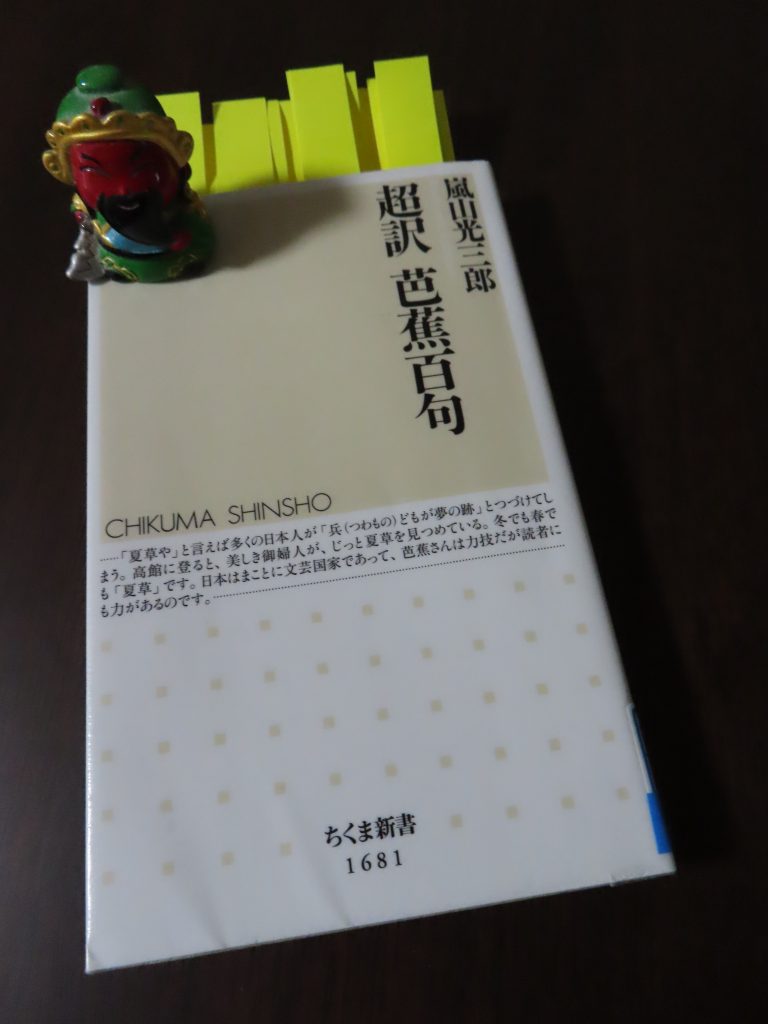幕府隠密であり、男色家であった俳諧師・芭蕉の実像・・・【情熱的読書人間のないしょ話(2782)】
故あって、本日は散策なしの読書三昧。我が家の餌台「空中楽園」にやって来るメジロ(写真1、2)、「カラの斜塔」の常連、シジュウカラ(写真3)、スズメ(写真4~6)は、撮影助手(女房)と私を楽しませてくれます。
閑話休題、『超訳 芭蕉百句』(嵐山光三郎著、ちくま新書)では、嵐山光三郎がこれぞという芭蕉の百句を選りすぐり、秘密にされてきた幕府隠密であったことや衆道(男色)に血道を上げたことなど、芭蕉の実像に鋭く迫っています。
●紅梅のつぼミやあかいこんぶくろ
●兄分(あにぶん)に梅をたのむや児桜(ちござくら)
「『われもむかしハ衆道好きの』に対して、研究家諸氏は『告白ではなく創作』といちように弁護するけれども、この時代は野郎歌舞伎が盛んで男色はいま以上に多かった。芭蕉が誇張して言っているかどうかを詮議する必要はなく・・・」。
「芭蕉の発句は、のちの枯淡なる独白、風雅なる旅の句も、基本的には作り話が多い。芭蕉の頭のなかには中国詩人や西行の吟ほか多くの雑多な古典の引用があって、風景などはさして見ていない。『おくのほそ道』にしても、観念としてある風景を現場にあてはめた。これは悪いことではなく、旅行記も俳席も、別世界を幻視するところに妙があり、晩年の芭蕉は作意を嫌った」。
「寺子屋卒(学歴が低い)の芭蕉は『貝おほひ』一冊の刊行によって花のお江戸の俳諧師になった。これぞ俳諧の魔法で、蕉門はしぶとい勢力となっていく」。
●あさがほに我は食(めし)くふおとこ哉
「朝顔の花を見ながら私は飯を食っておるのだよ。と、芭蕉は早起きを自慢しております。そんなことを自慢しなくたっていいのにね。これには、わけがある。一番弟子の其角が夜遊びの句を詠んだのを、からかいながら楽しんでいるのです。其角は日本橋堀江町の医者の息子で、十七歳のころから芭蕉の弟子となった。才気あふれる道楽者の弟子で、二十二歳のとき、其角撰による『虚栗』を出板した。芭蕉より十八歳も年下である」。因みに、「我が物と思えば軽し笠の雪――其角」は、私の一番好きな句です。
●旅人と我名よばれん初しぐれ
「芭蕉にとって『旅人』となることは、和歌の西行や、連歌の宗祇の系譜につながることを意味した。『旅しぐれに濡れながら、旅人とよばれる身になりたいものだ』という決意表明である。・・・西行、宗祇、雪舟、利休といった先人たちが求めた道を求めて、風雅の世界に生きる者は、四季の変化を友としている』と、述懐している」。
●あの中に蒔絵書たし宿の月
「芭蕉は絵がうまかった。プロの水墨画家であった。自分の句に絵を描きそえた画賛は売り物になった。芭蕉に経済的援助をしたスポンサーや友人に礼として渡した。金銭的余裕がなかった芭蕉にとって、自筆画賛は収入源になった」。
●あやめ草足に結ん草鞋の緒
「隠密(つまりは幕府公安)の要諦は、精度の高い情報探査にあり、三千風のように仙台に住みついて藩士や町の要人となじみ、藩内の抗争や事件を報告するケースと、芭蕉のように旅人を装って、藩の動向を探索するケースがある。観察眼にすぐれた俳諧師ならではの任務で、曽良の調査力と芭蕉の直観が合体すれば、情報の精度が増す」。
●夏草や兵(つはもの)どもがゆめの跡
「驚くべき早さで、やたらとあわただしい観光であった。片道一時間半として、平泉を見物したのは実質二時間であった。そんな短時間で『藤原三代の栄耀がほんの一眠りの夢のようにはかなく、秀衡の屋敷の跡がただの田野になっていた』と書く」。
●一家(ひとつや)に遊女もねたり萩と月
「芭蕉は求道的でありつつも世俗にたけ、江戸では色町(衆道専用の堺町)の句を詠んでいる。俗世間の風俗もとりこんで『ほそ道』を歌仙に仕立てる」。
「あとがき」には、こういう一節があります。「芭蕉は講釈好きであった。土芳編『三冊子』に出てくる訓戒には芭蕉の本音が見られる」。
「芭蕉は中肉中背で小肥りながら、健脚でがっちりとした骨格の人だ。屈強なる体躯をもてあまして、その反作用として弱々しい虚弱老人に見せかけようとした」。
説得力のある、そして、読み応えのある一冊です。