本書のおかげで、無神論者の私が禅宗に惹かれる理由がはっきりした・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3666)】
早朝、2階のヴェランダに洗濯物を干しにいった女房が、網戸にキマダラカメムシ(写真1)がいるわよ、と駆け下りてきました。庭師(女房)が駆虫剤も除草剤も使用しないので、我が家の庭は野鳥や昆虫の楽園です。サクラ‘カンザン’(写真2~4)、クルメツツジ(別名:キリシマツツジ。写真5~7)、セイヨウシャクナゲ(写真8)、ボタン(写真9)、ネモフィラ(写真10、11)が咲いています。カントウタンポポ(写真12)の種子(綿毛、冠毛)は幾何学的ですね。












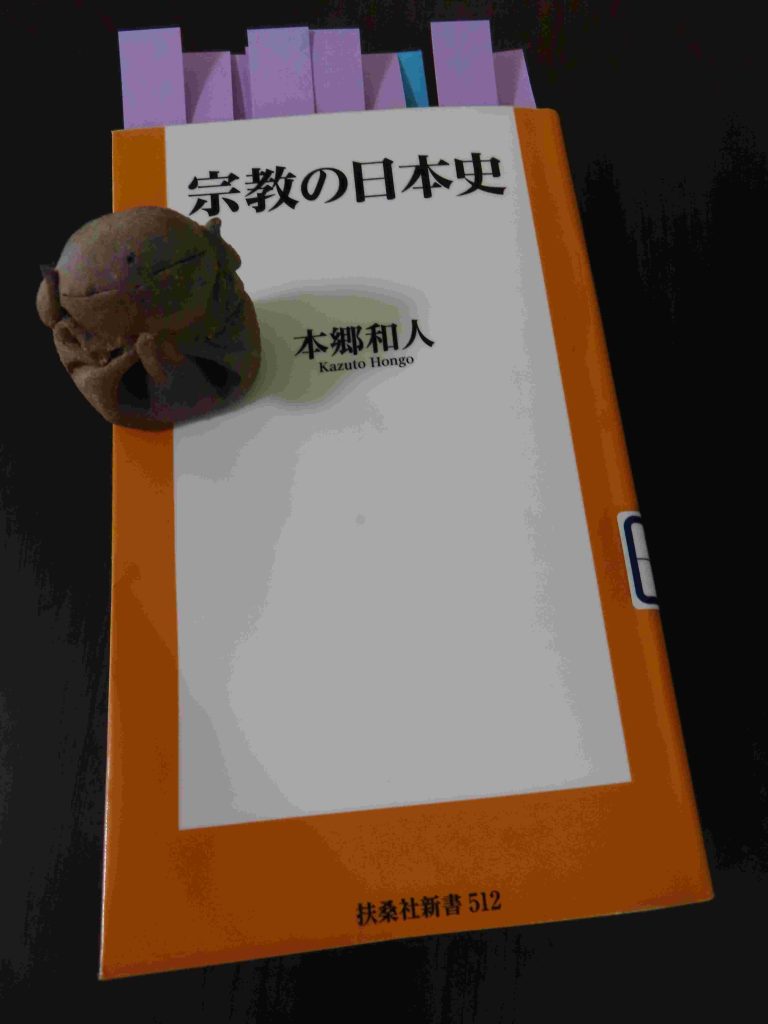
閑話休題、『宗教の日本史』(本郷和人著、扶桑社新書)で、個人的に、とりわけ興味深いのは、「鎌倉新仏教は庶民をスポンサーに」と「武士に好まれた禅宗の魅力」の章です。
国家を支える「顕密体制」と、弱者に寄り添う「鎌倉新仏教」が対比されています。民衆に寄り添い続けたのが鎌倉新仏教だというのです。
●「救済」を提供することで庶民の取り込みに成功した浄土宗。「理論は自分に任せて信じろ」と説いた法然。
●極楽よりも師・法然の教えを重視した親鸞。南無阿弥陀仏と称えれば極楽に行けるというシンプルな教え。
●その意味を知らなくても、南無阿弥陀仏と称えること自体に救いの力があると説いた一遍。
●南無妙法蓮華経と称えることが救いに繋がると説いた日蓮。彼は自ら日蓮宗を開こうとしたわけではなく、「法華経に帰れ」というシンプルな思想を打ち出しただけ。つまり、日蓮の運動は「天台宗の核心」に戻るべきだという主張で、「最澄の教えに帰れ」という運動とも言える。
本書のおかげで、無神論者の私が禅宗に惹かれる理由がはっきりしました。
「あらゆる宗教において、信仰とは基本的に『神を信じるかどうか』という問いかけからスタートしています。・・・しかし、禅宗の場合は何を信じるのかと問われても、信じる対象はありません。なぜなら、禅宗は信仰の宗教というよりも、『考え方』を重視する宗教だからです。最終的には、信仰ではなく、自己を見つめ、考え抜くことを通して悟りを求めるという姿勢が、特徴です。その点でも禅宗は他の宗教とは異なり、仏教の中でも独特の立場を築いているのです。・・・つまり、禅宗の教えとは、固定観念にとらわれず、融通無碍に物事を考えなさい、という非常に哲学的な教えなのです」。真理を一面的に見るのではなく、複雑な現実を多角的に捉え、あらゆる可能性を考慮せよと教えているのだという、著者の指摘には脱帽です。
