保元の乱に対する『愚管抄』の解釈は慈円の身贔屓だった・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3747)】
オナガ(写真1、2)、ハシブトガラス(写真3)をカメラに収めました。ムクゲ(写真4、5)、アガパンサス(写真6)、サボテン(写真7、8)が咲いています。ニホンヤモリ(写真9、10)が獲物を狙っているわよ! と撮影助手(女房)の声。










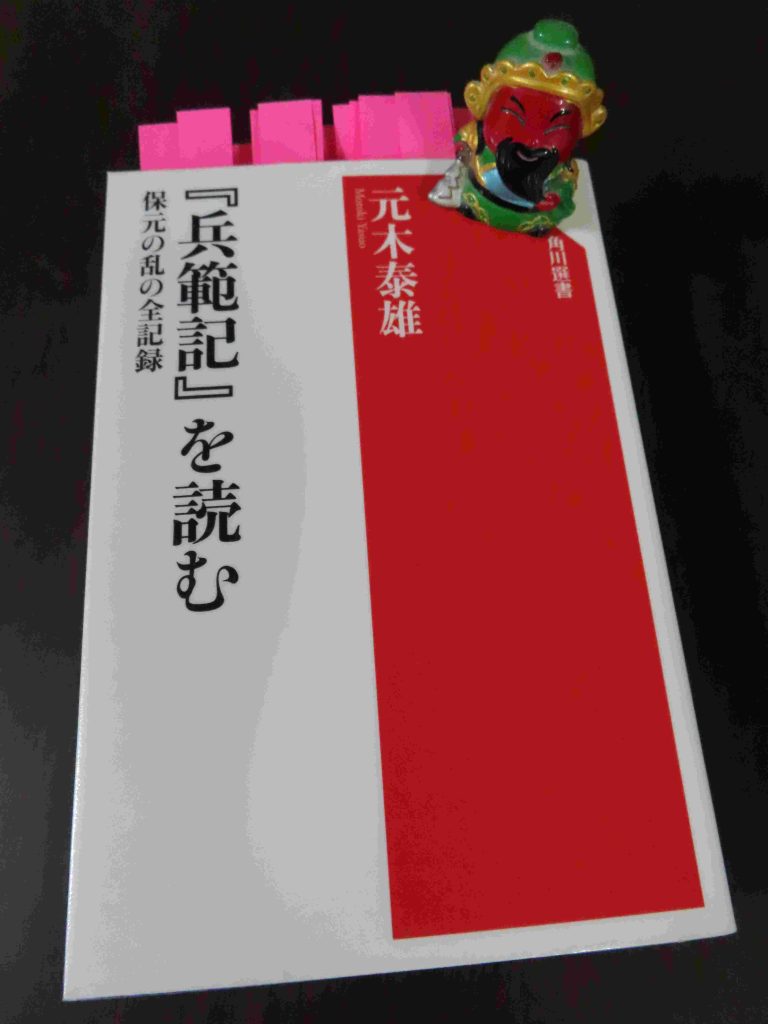
閑話休題、『<兵範記>を読む――保元の乱の全記録』(元木泰雄著、角川選書)に出会えてよかったと思えたのは、これまで客観的だと信じてきた、保元の乱に対する慈円の『愚管抄』の解釈が身贔屓だったと分かったからです。
本書は、保元の乱を間近で見聞きし、その内幕――乱に至る政治情勢、乱の経緯、乱後の措置――を知る平信範の手になる日記『兵範記』の解説書です。
<鶏鳴、清盛朝臣・義朝・義康ら、軍兵すべて六百余騎、白河に発向す(清盛三百余騎、二条の方より。義朝二百余騎、大炊御門の方より。義康百余騎、近衛の方より)>。鶏鳴、すなわち鶏が鳴くころを意味する明け方、平清盛・源義朝・源義康が率いる六百余騎の軍勢が、後白河天皇の命で、天皇の兄・崇徳院、左大臣藤原頼長が立てこもる鴨川東岸の白河北殿を目指して出撃していった様を、詳細に記しています。
乱に至る政治情勢について、『愚管抄』は、頼長を偏愛する父・藤原忠実が、摂関就任をせがむ頼長の願いを叶えるために息子・藤原忠道に摂関譲渡を申し入れたが、忠道は23歳年下の弟・頼長の器量・人格に問題があるとして譲渡を拒んだと記しています。この記述により、頼長は弟のくせに摂関を望み、父・忠実は彼を偏愛したとして、非はもっぱら忠実と頼長にあったと考えられてきたのです。
しかし、これは忠道の息子・慈円の評価であり、単純に従うわけにはいかないと、著者・元木泰雄は指摘しています。
忠道は男子に夭折され、存命の子息も母の身分の関係で出家していたため、保延2(1136)年当時、継嗣がないため、頼長を養子としていました。ところが、思いがけないことに、忠道は47歳の康治2(1143)年に基実、その2年後には基房、さらに兼実・慈円以下、次々と男子を儲けたのです。こうなると、忠道は当然、実子への摂関継承を望み、弟・頼長への譲渡を拒んだのです。このような背景を知ると、父権絶対の当時、実子誕生で父の方針を反故にした忠道に問題があり、単純に忠実の偏愛、頼長の身勝手な願望の結果とは言い難いと、元木は述べています。
乱の底流をなす忠実と忠道の不仲の根本的な原因は、摂関家家長の忠実にとって、忠道の父権に対する反抗を許せなかったことだとまで、元木は言い切っています。
一方、『兵範記』の記述からは、頼長がすぐに憤激し制裁や報復を好む性格であり、他の権門との衝突を避ける配慮が足りない人物であったことが伝わってきます。このため、頼長は最高権力者である鳥羽院、近衛天皇の不信を招き、遂には孤立し、失脚への道を歩んでしまったのです。
鳥羽院の息子・後白河天皇と、その兄・崇徳上皇が次の皇位を巡って対立した保元の乱の直前には、後白河・忠道側の兵力(清盛、義朝、義康ら)が崇徳・頼長側のそれ(義朝の父・源為義、義朝の弟・源為朝ら)を圧倒しており、崇徳・頼長側は政治的に追い詰められ、敵の挑発に乗せられ、敢えて負け戦に挑んでしまった経緯も、本書で明らかにされています。
歴史好きには堪えられない、読み応えのある一冊です。
