レジスタンス活動中に34歳で死去した行動する哲学者シモーヌ・ヴェイユの名言集・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3887)】
野鳥観察だけでなく、紅葉狩りも、と撮影助手(女房)に言われて、近くの公園へ。終わりかけているがカツラ(写真1)、ユリノキ(写真2~4)、イチョウ(写真5、6)の黄葉、ドウダンツツジ(写真7)、ニシキギ(写真8、9)、イロハモミジ(写真10~12)、ハナノキ(写真13、14)、モミジバフウ(写真15~17、17は撮影助手がスマホで撮影)の紅葉を堪能することができました。

















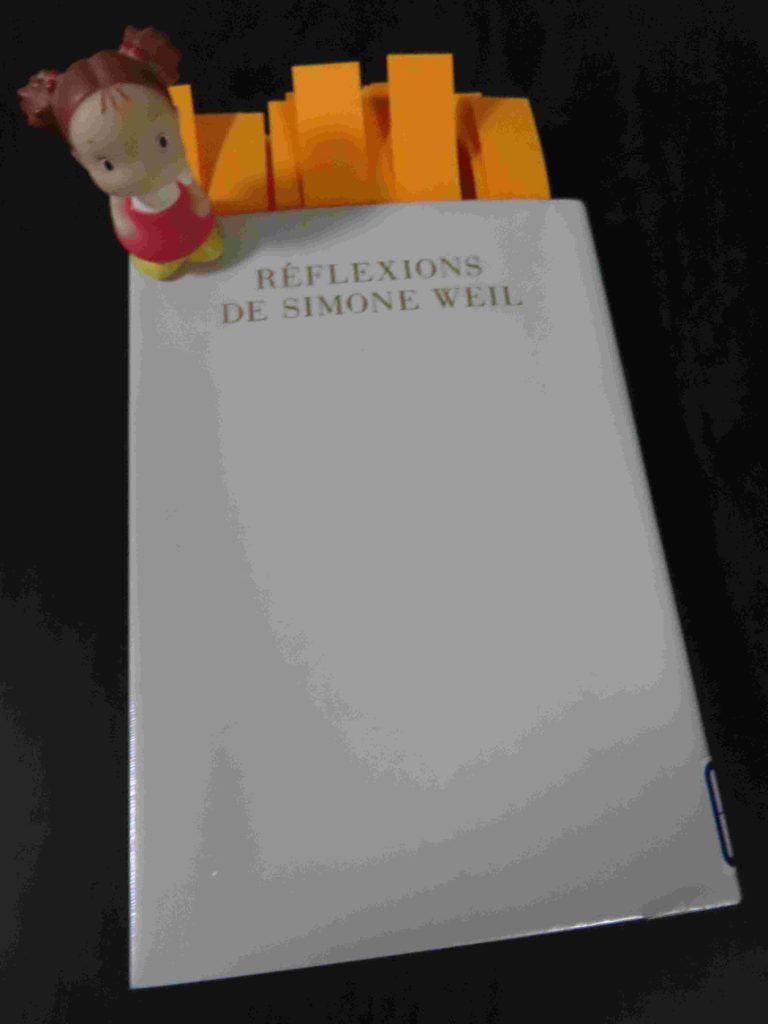
閑話休題、『シモーヌ・ヴェイユ まっすぐに生きる勇気』(シモーヌ・ヴェイユ著、鈴木順子編訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン)は、行動する哲学者シモーヌ・ヴェイユの名言集です。
ヴェイユは第二次世界大戦下のレジスタンス活動中に結核で34歳という若さで亡くなりました。彼女は『幸福論』で知られるアランの教え子で、死後、『異邦人』、『ペスト』のアルベール・カミュから高く評価され、我が国では大江健三郎、神谷美恵子、須賀敦子、高村薫、鷲田清一らが影響を受けました。
●大切なのは自分の人生を生き切ることです。
●他の人たちがあるがままに存在するのを信じることが、愛である。
●権力そのものがあるのでは決してなく、ただ権力への競争があるだけである。・・・このようにして権力への競争に、強者も弱者も含むすべての人間が隷従させられてゆく。
●マルクスが想像した共産主義は、この(自由についての)夢の最新形態である。すべての夢と同様、この夢は実現されずに終わった。たとえ慰めにはなりえたとしても、それはアヘンとしての慰めにすぎない。
●学問においては、つねに「推論」と「表象」の能力ばかりが養われ、「直観」の能力はまったく養われない。しかし、この「直観」の能力もまた、鍛えられねばならない。
●このとき、私は突然、キリスト教は何よりも奴隷たちの宗教であること、そして奴隷たちはそれを受け入れないではいられないのだということ、また私は彼らの中の一人だということについて確信を得たのでした。
●すべての出来事を愛さなければならない。その結果のためではなく、一つ一つの出来事の中に神がいるからだ。ただしこれは同語反復だ。すべての出来事を愛するとは、それらの中に神を読み取ることにほかならないのだ。
●魂の不死を信じるのではなく、全生涯を死の瞬間にむけた準備とみなすこと。神を信じるのではなく、宇宙を愛すること。つねに変わらず、苦しみにともなう苦悩のただなかにあってさえも、母国のように愛すること。これが無神論を経由した信仰への道程である。この信仰は宗教の諸表象において輝き出る信仰と同じである。しかし、この道程を経て信仰に達したとき、これら表象はまったく無用となる。
●おそらく死の瞬間には、聖なる魂の中には、神的な歓びの無限と、純粋な苦痛の無限とが同時に入り込み、魂を炸裂させ、存在の充溢のうちに消滅させるのだろう。他方、失われた魂は、恐怖と恐ろしいまでの自己陶酔とが混じり合う中で、虚無へと溶け去っていくのだろう。
●十字架上のキリストが、「わが神、わが神、なぜ私を見捨てたのですか」と叫んだこと、これこそが、神の栄光への完全な賛美である。私たちが、ここ地上での短くも果てしない、果てしなくも短い滞在のあいだに、このように叫びながら、やがて虚空へと消滅していくこと――それで十分なのだ。
私は、哲学にとって一番重要なテーマは死だと考えています。この書評を書き上げた段階で、ヴェイユは神の存在を信じていたのか、そして、死をどう考えていたのか、もう一つはっきりしない憾みがあります。そこで、ChatGPT5に「シモーヌ・ヴェイユは神の存在を信じていたのか、そして、死をどう考えていたのか、280字で教えてください」と教えを乞いました。その答えは、「シモーヌ・ヴェイユは、伝統的な信仰告白というよりも『神の実在』を直観的・体験的に深く信じた思想家でした。彼女は神を『絶対的な善』と捉え、受け入れることは『自己の消滅=自己放棄』と考えました。死についても、恐れるものではなく『神との一致』を可能にする境界と見なしており、苦しみや不条理の中に神の愛の現れを感じました。彼女にとって死は逃避ではなく、真理への帰還の契機でした」。おかげで、ヴェイユと、エピクロスの信奉者である無神論の私は、異なる考え方であることが分かり、スッキリしました。だからと言って、ヴェイユに対する敬愛の念に変化はありません。
