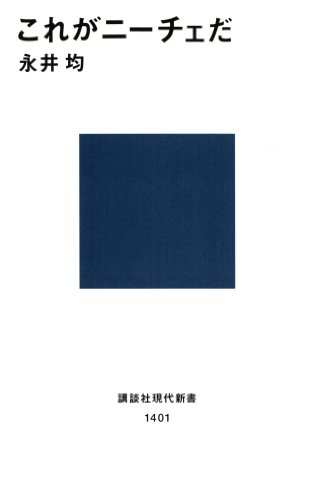かなりひねくれたニーチェ論だが、驚くべき指摘に満ちた一冊・・・【情熱の本箱(348)】
『これがニーチェだ』(永井均著、講談社現代新書)で展開されているのは、かなりひねくれたニーチェ論なので、ニーチェについて知りたいと初めて手にする場合の入門書には向いていない。
永井均は、「ニーチェは世の中の、とりわけそれをよくするための、役に立たない。どんな意味でも役に立たない。だから、そこにはいかなる世の中的な価値もない」、「思想家として見れば、ニーチェは完璧に敗北した。彼は、世界解釈の覇権を完全に奪われた思想家である。ニーチェに思想的な意義があるとすれば、それはこの敗北の完璧さにあるだろう。その敗北の完璧さによって、逆に、ニーチェは今日の時代の本質を射貫いている」と、言いたい放題である。
「彼は徹底的にルサンチマン的であるがゆえに、それを完全に克服する可能性を示唆しており、徹底的にニヒリストであるがゆえに、ただそうであるがゆえにのみ、ニヒリズムを克服する可能性を開くことができた。それは疑う余地がない。哲学をよく知らない人は、しばしば哲学者の仕事を、時代の病の的確な診断とそのすぐれた治療プランの作成のように理解し、哲学者をそれを編み出した医師のように捉える。そうではない。逆なのだ。彼らはみな、他に例のないほどの重病人であり、それゆえに自分の病と格闘せざるをえなかったにすぎない。歴史に残るような思想は、多分どれも、他になすすべがなかった人によって、苦しまぎれに、どうしようもなく作られてしまったものなのである。その病が、誰もが感じる時代の病と重なるかどうかは、ただ偶然のみが決めることなのである。その意味では、ニーチェは幸運だったとはいえる。ただそれだけのことにすぎない」。著者はこう断じているが、ニーチェの病と時代の病が一致していたということは、逆説的な表現でニーチェの偉大さを誰よりも認めていることになるだろう。
私にとって、何とも驚くべき指摘が、3つある。
第1は、ニーチェは無神論者ではないという指摘だ。「ニーチェはふつうの意味での無神論者ではないということである。いやむしろ、はっきりと有神論者であるといってもよい。だから、彼が神の死について語るとき、善悪(といった小賢しいもの)をはるかに超えた、この世界の存在そのものの神々しさと一体化した、本来の神が、キリスト教とその道徳によって、なぶり殺しにされてしまった、という嘆きの側面が確実にあるのだ。ここを押さえておかないと、永遠回帰や運命愛を語る第三空間(永井は、ニーチェの思考段階を第一空間、第二空間、第三空間という永井独自の用語で表現している)において、ニーチェが何を求めていたのかが、ちっとも実感できなくなってしまう。この側面から見れば、ニーチェの思索とは、『神』が、そしておよそ神性一般が、キリスト教の『神』とともに息の根を止められてしまうのを阻止し、『神』を生き返らせようとする思想運動にほかならない。だからこそ、彼の問題意識は、啓蒙主義や実証主義の無神論の精神と、まっこうから対立することにもなるのだ。ニーチェ空間の側から見れば、それらはしょせんキリスト教的な『神』空間の内部現象にすぎないからである」。
第2は、ニーチェを襲った2つの体験が永遠回帰の思想を深めたという指摘である。「1881年8月、ニーチェはスイスの山中で永遠回帰を体験する。・・・永遠回帰とは『一切が現在あるのと少しも違わない形と順序のまま、無限の時間の流れのうちで、無限回繰り返されること』である。重要なことは、ニーチェがそこで永遠回帰という思想の着想を得たのではなく、それをじかに体験してしまったということである。それは彼がつくった思想なのではなく、むしろ襲われた体験そのものなのである。だから、彼自身も、その体験をどう位置づけるべきか、最初から明確な考えを持っていたわけではない。にもかかわらず、この体験以降、ニーチェはこれまでとはまったく違う空間の中に入り込むことになる」。
「1882年の春、38歳のとき、ローマのサロンで、彼は21歳の聡明なロシア人女性ルー・ザロメと知り合い、恋愛感情を持った。・・・結局、ルー・ザロメは(恋敵の)パウル・レーとベルリンで同棲をはじめることになる。ニーチェは(ザロメの件で)妹や母と不仲になり、レーとの関係も気まずくなって、ますます孤独の影を深めることになるのである。この年の8月に、『悦ばしき知識』が出版されている。ここから本来のニーチェが始まる素晴らしい本である。・・・『神の死』も、『永遠回帰』も、この本から始まるのである」。ニーチェが『ツァラトゥストラはこう語った』の第1部を10日間で書き上げたのは、1883年1月のことである。
第3は、ニーチェは、來世はないと言っているという指摘である。「悪魔が永遠回帰を告げる。その内容をどう受け取るべきだろうか。ある観点からすれば、それは来世があるという内容である。繰り返すということは、この生が一度だけでなく、さらにもう一度、そして何度もある、ということなのだから。だとすればそれは、人生は一度きりで死ねば後にはもう何もないという考えに比べて、むしろキリスト教の考え方に近いのではないだろうか。その内容はともあれ、とにかく今のこの現実の人生以外のものがあるというのだから」。
「そうではない。来世はないのだ。これは、それがないということの強調なのである。私は、この生以外の生を生きる可能性はない。たとえ何度生まれたとしても、この人生しか生きられない。たとえ何度生まれたとしても、というこの譲歩は、この人生しかないという事実の強調のための譲歩なのである。だから、見かけに反して、回帰思想は来世があるという考え方の対極にある。とりわけそれは、死後にこの現世の生に対する後からの評価がなされるというような、現世に対してメタ的な位置に立つ生の存在可能性を強く否定し、その否定を誇張しているのである」。
巻末の著者のアドヴァイスは有益である。「ニーチェ自身の書いたものをお読みになりたい方は、自伝である『この人を見よ』を私は勧めたい。『悦ばしき知識』と『反キリスト』が私の愛毒素である。『ツァラトゥストラはこう語った』を最初に読んで途中で挫折する人が多いが、もしそれを読むならば、いきなり第3部から読み始めるべきである。幸いにして文庫本はどれも上下2巻本になっているので、下巻から読み始めればよいことになる」。