日本は移民を積極的に受け入れるべきか否か・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3094)】
生物観察仲間の山田純稔さんから情報が得られ、2時間半粘った甲斐があり、かなり遠くからだが、念願のキビタキの雄(写真1~3)と、雌と思われる個体(写真4~8)を撮影することができました。彼らはミズキ(写真9)の実を食べにきているのです。コゲラ(写真10)、コサギ(写真11)、ダイサギ(写真12)をカメラに収めました。ヒガンバナ(写真13)が咲いています。ススキ(写真14、15)の穂が風に揺れています。ススキの種(正しくは穎果<えいか>)からピローンと頼りなげに1本伸びているのが芒(のぎ)です(写真15)。因みに、本日の歩数は11,330でした。
















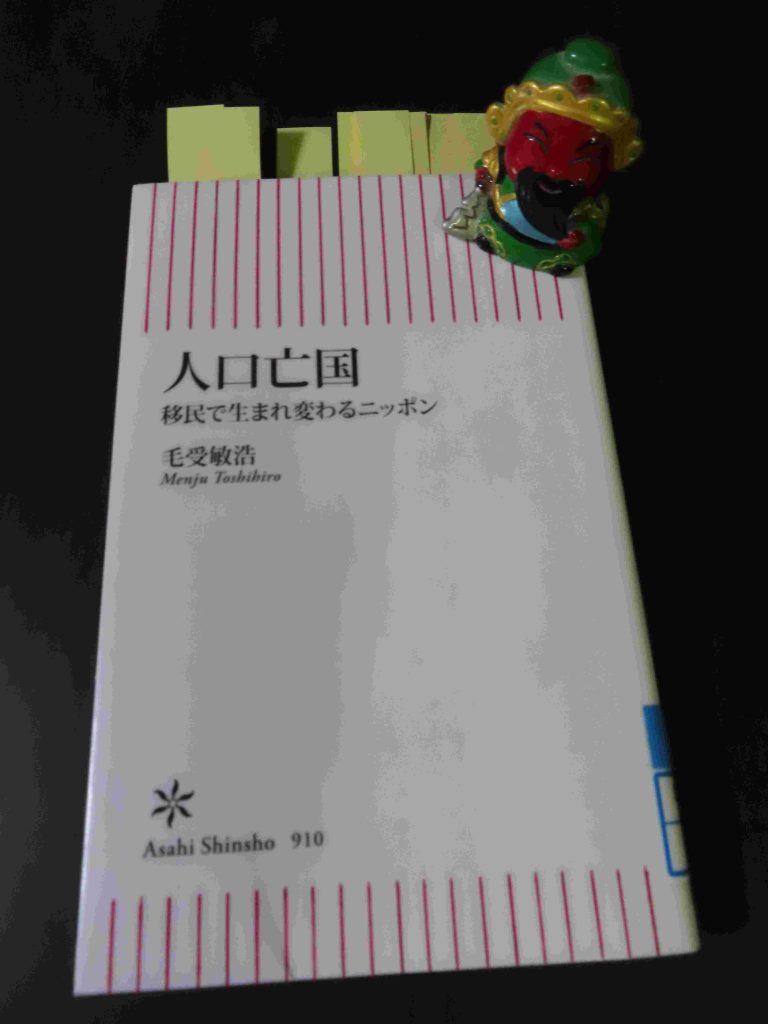
閑話休題、『人口亡国――移民で生まれ変わるニッポン』(毛受敏浩著、朝日新書)で、私が最も注目したのは、我が国が人口亡国を避ける具体的な方法です。
著者は、●移民たちの持つ可能性にかける、●2020年代が日本の正念場だ、●心を開くグローバル化――の3つを提唱しています。
●移民たちの持つ可能性にかける
「外国人は単なる労働力不足を補うだけではない。母国を離れ海外に移住を決意する移民は、そもそも成功意欲の高い人たちだ。ドイツの例では、2009年に設立された40万の企業のうち13万は、移民によって設立され、ドイツで起業した3人に1人が移民という計算になる。日本でも経済的な成功を夢見る外国人は多い。筆者は新宿区多文化共生まちづくり会議の委員を務めているが、新宿には日本語学校が集中している。そうした日本語学校や専門学校を卒業した外国人の若者は、数年、就職して一定のお金を貯める小さなレストランや雑貨店を20代で開業し、成功するとさらに店を増やし、新たな事業に手を広げていく。日本人の若者には見られない失敗を恐れないチャレンジ精神を彼らは持っている」。
「外国人が増える中で、外国人自身のコミュニティが日本社会の中で形成されている」。
「円安でも日本にチャンスは残されている。国際情勢を見れば、ウクライナ危機のように先行きが見えず、また専制国家の勢いも増している。ロシアや中国はその典型だが、SNSの普及で一般国民も世界とのつながりがよく見える中で、専制国家から逃げ出したい、自由な国へ出たいと考える若者が増えている。ロシアでは兵役を逃れる目的もあり、愛想をつかした青年の海外脱出が増えている。中国でも習近平への忠誠心が強く求められる時代錯誤的な国内の風潮に対して、海外留学経験者など、自由な世界の空気を吸った若者は耐えられないだろう。日本は曲がりなりにも民主主義が根付き、自由な国家であり、国民の教育水準も高い。低成長が続くとはいえ、清潔で安心、安全な日本はそうした人びとには魅力的と映るだろう。そうであれば、単に待ちの姿勢を続けるのではなく、積極的に海外から優秀な若者をリクルートする、そうした政策が求められるだろう」。
「それは単にIT技術者などの高度人材に限らない。彼らは世界中で引く手あまたであり、仮に日本の企業に就職しても、条件次第ですぐに他国に転出するだろう。受入れるべきは日本を好きになり、困難な日本語や日本文化を学ぶ意欲のある定住志向の若者だ」。
●2020年代が日本の正念場だ
「コロナ禍が明けたあと、これからの2020年代が日本にとって正念場となる。日本が『選ばれる国』として世界に認知されるのか、あるいはそうならないのか。在留外国人の労働、生活環境がどのように改善され、また新たに入国する外国人を日本がどのように迎え入れ、活躍できる土台を作れるのか、あるいは日本の若者の海外流出が本格化するのか、日本の将来を決することにもなるだろう」。
著者は日本の若者の海外流出にも目配りしています。「2023年2月1日にNHK『クローズアップ現代』は『 “安いニッポンから海外出稼ぎへ”――稼げる国を目指す若者たち』という特集を放送した。驚いたことに、小学校の教員をしていた若者や正看護師など、国家資格を持ち、安定した職を持つ青年が自主的に退職し、オーストラリアで日本よりはるかに高給の仕事に就き、満足に暮らす様子を放送した。この放送を見た日本人の青年は、自分も行きたいと思ったのではないか。・・・日本の若者のこの(自由度の高いワーキングホリデーの在留資格の)利用が雪だるま式に増えれば、日本は正式に移民受入れ国となる前に、移民送り出し国へのプロセスに入ってしまうのかもしれない」。私もこの番組を見て驚いた一人です。
”●心を開くグローバル化
「外国人受入れを成功に導くために最終的に必要になるのは、政治の力であり、また日本人の意識の変革だ。外国人を対等なパートナーとしてみなし、共に社会を作る人たちであるとの認識である。アジアの端に位置し、特殊な言語を話す国である日本に魅力を感じて、日本で働き、生活しようとする若者を日本人の青年と同様に大切にする。彼らの日本への思いに日本人は寄り添う姿勢を示す必要がある」。
日本は移民を積極的に受け入れるべきか否か悩んでいる人は、ぜひ、本書を手に取ってほしい。移民問題について、最新情報を踏まえ、説得力のある主張が展開されているからです。
