周囲との関係で自らを「カスタマイズ」しつつも、自らの特性を維持してきたユダヤ人・・・【情熱的読書人間のないしょ話(3685)】
幸運にも、電線で高く囀るヒバリの雄(写真1~5)を撮影することができました。アシ原で賑やかに囀る声はするものの、なかなかオオヨシキリの雄(写真6~9)を見つけることができません。しかし、粘った甲斐があり、全身ではないが、その姿を捉えることができました。ムクドリ(写真10)、ハシビロガモの雄と雌(写真11)をカメラに収めました。ユウゲショウ(写真12)、セイヨウカナメモチ(英名:レッドロビン。写真13~15)が咲いています。我が家の庭師(女房)から、シロバナコバノタツナミ(写真16)が咲いているわよ、との報告あり。因みに、本日の歩数は11,487でした。
















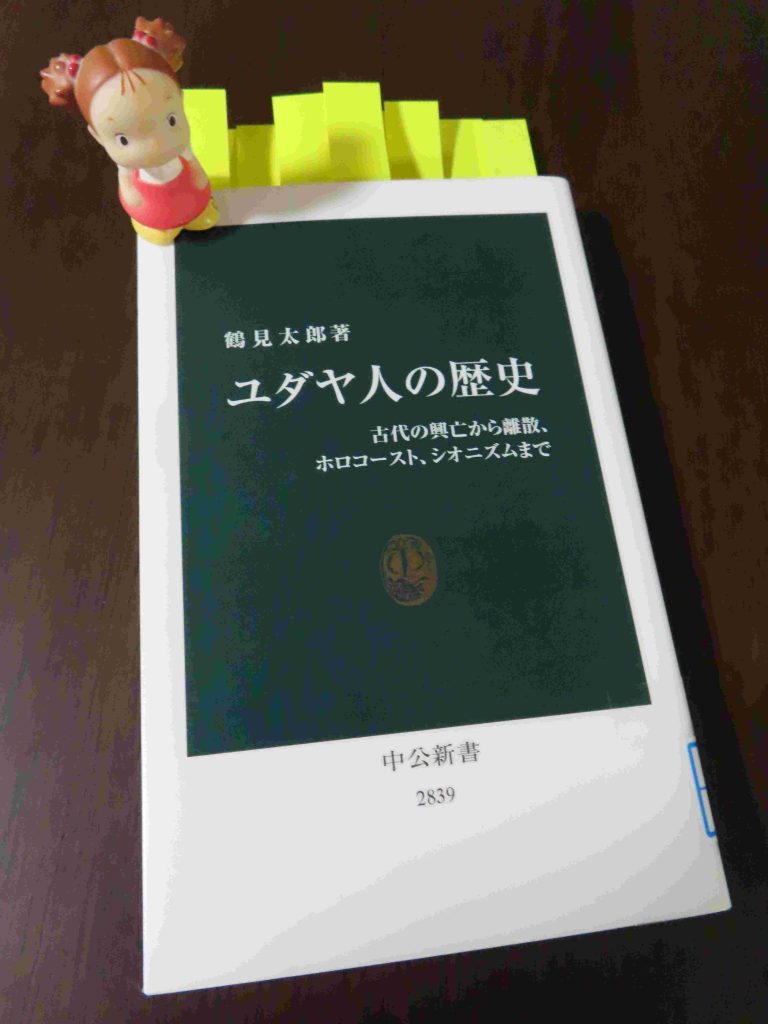
閑話休題、『ユダヤ人の歴史――古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで』(鶴見太郎著、中公新書)のおかげで、古代から現代に至るユダヤ人の歴史を知ることができました。
著者のユダヤ人観はユニークです。「居住国と折り合いをつけながら、自らの原則は貫く。そのことが仲間内の信頼につながり、ネットワークが維持されていく。重要なのは、状況に自分を合わせるということでは必ずしもないことだ。むしろ自らの特性とうまく組み合わさるところに入っていき、多少は周囲との関係で自らを『カスタマイズ』しつつも、自らの特性を維持することが周りのメリットにもなり、そのことで自らの居場所がさらに安定化するという好循環を目指すのだ。金融業で成功し、富豪として西洋社会に存在感を持つユダヤ人の存在も、こうした視点から読み解くことができる」。
しかし、こうした戦略が常に成功するわけではないことにも言及しています。その最悪の例がホロコーストです。
ベンヤミン・ネタニヤフは、ユダヤが何と組み合わさり生存するかを考えない点で、ユダヤ史の中では例外的存在だと指摘しています。
シオニズムに関する解説は勉強になりました。シオニズムは、パレスチナにユダヤ人の民族的拠点を打ち立てることを目指す思想・運動であり、今日のイスラエルの思想的基盤になっています。
シオニズムを率いたのは東欧出身のユダヤ人・アシュケナジームでした。当初はシオニズムから距離を置いていた中東・北アフリカ出身のユダヤ人・スファラディームも巻き込まれていったが、アシュケナジームはスファラディームを下に見ていたと書かれています。対アラブでは一枚岩のように見えるユダヤ人社会も、内部は複雑なのですね。
